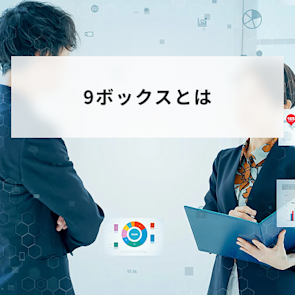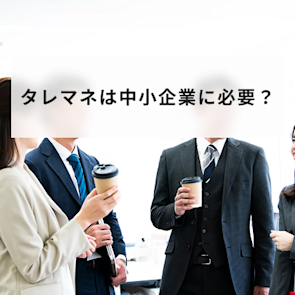人事制度設計のポイントとは?設計方法を3つの人事制度を交えて解説
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- 人事制度設計とは
- 人事制度設計のポイント
- 注目の人事制度
- 1on1
- 360度評価
- ノーレイティング
- 人事制度設計の具体的な手法
- 現状把握
- アウトラインの設計
- 運用面でのフォロー
- 人事制度を設計する際に利用する外部サービス
- 人事制度設計コンサルタント
- コンサルタントを利用する際の注意事項
- 納得度の高い人事評価制度の構築をHRBrainコンサルティングで実現
- HRBrain コンサルティングの特徴
人材を生かすために、大事な制度である人事制度。本記事では人事制度設計を行う際の基本的な心構えや、実際人事設計する際の具体的手順、注目の人事制度、外部サービスを使うときのポイントを解説致します。
調剤薬局での薬剤師業務と管理業務を経て、人事採用担当に。LINEを使った採用管理システムの導入や、オンプレミス環境での勤怠管理システム導入のプロジェクトマネージャーなど人事関連の幅広い知識を持つ。
人事制度設計とは
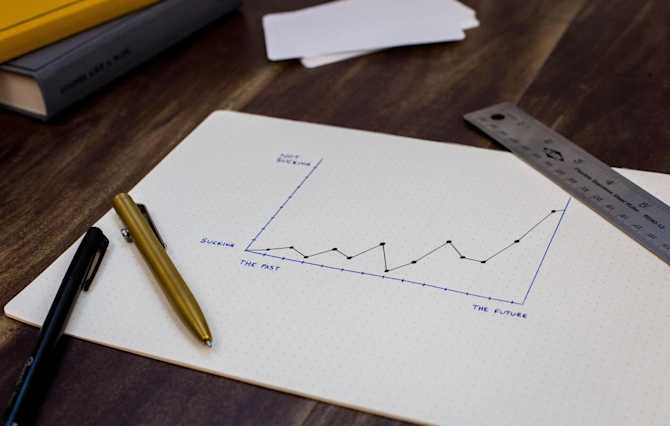
人事制度とは、企業の経営資源の根幹である従業員の給与、昇給を定めるだけでなく、従業員が快適に過ごすための条件や仕組みを表す制度です。現在では等級制度、評価制度、報酬制度の3種を指して人事制度と捉えることもあります。人事制度設計は煩雑で、自社で設計するのは難しいと感じる方もいるかもしれません。しかしポイントを押さえれば、自社で設計することは可能です。人事制度設計のポイントについて解説致します。
人事制度設計のポイント
人事制度設計は、人材を適切に処遇するだけでなく、業績にも直接影響があるため、企業の中でも特に重要な制度の一つです。実際の実務に合った人事制度設計を行う前に、ここだけは外せないというポイントを解説します。
人事制度の概念を明確にする
最近では人事制度を見直す企業も増えています。ただし、人事制度が単に古くなってきたから見直すというのはおすすめできません。最初に制度設計に伴って、自社が将来どうなっていきたいかという目標を明確にしましょう。その際、企業の理念や経営戦略に沿った制度設計にします。また、人事制度が成果主義なのか、プロセスを評価するのかなど、どのような場面で人材を評価するのかという概念を固めたほうが、制度設計時における正しい判断ができます。理念と概念に沿った設計でなければ、設計の段階でブレが生じるだけでなく、将来、大きな制度設計の修正が求められます。
完璧を求めすぎない
制度設計の段階で変更が難しくなるような、完璧なものの作成を目指すのは避けましょう。毎年制度の見直しをするようなものでは有りませんが、環境の変化や経営の変化に対応するために、ある程度幅を持たせるような制度が必要です。そのため、はじめから細かいところまで設定することもおすすめできません。まずは最重要な項目である評価制度、次に評価項目を設定する必要があります。ここがずさんな設定になると、社員の納得感や理解を得るのは難しいでしょう。
情報を開示する
制度設計の開始から終了まで従業員に開示しましょう。人事制度は従業員の将来に関わることです。そのため、会社が人事制度について具体的な情報を開示することが大切です。「密室で設計された制度」と従業員に受け取られてしまうと、どんなにいい制度であっても不信感などが募ってしまい、受け入れられ難い物となってしまいます。もちろん全てが従業員の望む通りに制度設計が行えるわけでは有りませんが、人事制度がスムーズに運用されるために、適時情報は開示する必要があります。
注目の人事制度

人事制度設計を見直す、または新しく作成する際に積極的に取り入れられるなど、今注目されている人事制度を3点ご紹介致します。
1on1
1on1とは人材育成を目的とした、上司と部下が一対一で行う面談のことを指します。人事制度の中に1on1を取り入れる企業が増えています。なぜ今注目されているかの背景や目的について解説します。
1on1が必要とされる背景
かつて上司と部下とのコミュニケーションは業務の教育や指導などの一方的なコミュニケーションが主流でした。業務の教育に関しては、インターネットの急速な普及に伴い、必要な情報は検索すれば調べることが可能になり、上司が部下に教えなければいけないことが減ってきているといえます。またミレニアル世代は価値観を一方的に押し付けられるのを好まない傾向があるといわれます。そのためより双方向型のコミュニケーションを積極的にとることが必要とされています。
1on1のメリット
1on1は1ヶ月に1〜2度行うように制度設計を行っている企業が多いです。細かい頻度で1on1をおこなうことで、部下の身体的、精神的な状態悪化を早期に察知することができ、早期離職を防止する効果が期待されるでしょう。また上司に細かい目標を承認されると、部下のやる気の向上にもつながります。部下のやる気が向上すると、自主的な行動を行う従業員の育成にも寄与できます。1on1についてもっと詳しく知りたい方は「1on1とは? 従来の面談との違いや効果を高めるコツ」を御覧ください。
360度評価
360度評価とは複数の立場の方が1人の従業員を評価する評価制度です。従来の人事評価は上司が部下を評価するのが一般的でした。なぜ360度評価を人事制度の中に取り入れるのでしょうか。
上司から部下の評価だけでは限界がある
上司が部下を評価する単独評価制度は、上司の好き嫌いが入ってしまい評価のエラーが起きてしまうことがあります。360度評価は複数の評価者が評価するためエラーを防ぐことができ、客観性が担保できます。
自分自身の問題点に気付ける
360度評価は評価本人の評価も自身で行います。これにより他社の評価と自分の評価のをくらべることにより、自分の問題を自身で気付くことができるのです。
ノーレイティング
人事評価として、従業員にランクを付けて評価することをレイティングと呼びます。ノーレイティングは従業員をランク付けせず、リアルタイムで目標を設定し、上司からフィードバックをもらいつつ、その都度に評価を行う制度です。最近は大手グローバル企業がノーレイティングの手法を用いて従業員を評価しています。なぜレイティングが見直され、ノーレイティングの手法が取り入れられているのでしょうか。
従業員の個性がレイティングでは評価しにくい
ノーレイティングは上司とのコミュニケーションを取り、絶えず評価を行います。新規事業などでは人材の個性が求められることもありますが、新規事業はなかなか目が出にくいケースも有るため、半年、一年など長期の評価目標設定を行うよりも、絶えず評価を行い個性を適切に評価できるノーレイティングでの評価が注目されているのです。
レイティングでは柔軟に評価できない
従来の目標管理制度であるMBOでは目標に到達できているか、出来ていないかで評価するため、目標未達の場合は評価が下がってしまいます。ノーレイティングは柔軟な評価を行うことができるため、従業員に納得感を持ってもらうことで、モチベーション向上につなげることが可能です。ノーレイティングについてもっと詳しく知りたい方は「管理職が給与を決定!?ノーレイティングについて徹底解説」を御覧ください。
人事制度設計の具体的な手法

人事制度設計のポイントや注目の人事制度について解説いたしました。ここからは人事制度設計の具体的な手段について解説致します。
現状把握
まずは自社がどのような状態にあるのかを把握しましょう。特に大事なポイントは2つです。
企業理念の確認
人事制度設計を行う際に、自社の企業理念を確認することは必須の要件となります。なぜならば人事制度は、企業がどうなっていきたいかという考えのもとに作成する必要があるからです。形だけの人事制度では、従業員に納得して受け入れてもらうのは難しくなります。まずは企業理念を再確認し、それに基づくような人事設計にすることを心がけましょう。
現状の分析をする
社内でアンケート調査を実施し、社内の人事制度についての意見を集めましょう。集めた意見で現状を分析し、課題を洗い出します。現在の賃金の妥当性や業績との相関など、より具体的な課題を浮き彫りにすると改善策が生み出しやすくなります。
アウトラインの設計
自社の理念、現状を把握したら人事制度の根幹である等級制度、評価制度、報酬制度を設計していきます。
等級制度
等級制度は人事制度の根幹とも言える制度です。社員の等級で給与水準を定めていきます。等級の構成要素は、課長、部長などの役職や営業職、事務職などの職種によって定め、等級が上がるためにはどのような条件をクリアすればいいかなどを定める必要があります。
評価制度
評価制度はどのような行動をとれば評価されるかを定める制度です。どのような行動をとれば評価されるかは、企業によって様々です。目標管理制度(MBO)や業績に結びつくような行動を評価とし、課題をクリアしていた企業もありましたが、ノーレイティングなどを取り入れた人事評価が、昨今では注目されています。
報酬制度
等級制度や評価制度で設計した内容を従業員の報酬にどのように反映するかを定めます。賃金、賞与、退職金、交通費などの規定を定めますが、売上や競合他社との賃金水準などを適切に見極め、バランスを考慮しながら設計しましょう。
運用面でのフォロー
各種制度設計ができたら次のステップに移ります。実運用に移った場合のポイントを解説します。
各種制度を公表する
完成した制度は必ず明文化し、全従業員に公表しましょう。全従業員に平等に公表しないと、納得感を持ってもらうのは難しいかもしれません。各種制度を実施する前に繰り返し説明を行うと、より納得感をもって各種制度を受け入れてもらえるでしょう。
リーガルチェックを行う
どんなに素晴らしい制度が出来たとしても、運用前に専門家にチェックしてもらう必要があります。既存の従業員に不利になる変更は不利益変更になり、法的なリスクを負う可能性があります。
制度の定着化
実運用が開始されたら、制度の理解が進んでいるかのアンケートや満足度調査を行います。人事制度は自社の理念に沿って設計されているはずなので、従業員の意識変化があるかもあわせて調査しましょう。また定着を阻んでいる要素を分析し、改善していく必要があります。
人事制度を設計する際に利用する外部サービス

ポイントを押さえれば自社で設計可能な人事評価制度ですが、外部サービスを利用すると、より良い人事制度の再構築ができる可能性があります。
人事制度設計コンサルタント
制度設計や実運用は自社でも可能ですが、やや主観が入ったり、自社の中に専門家がいない場合は正解を出すのがむずかしいかもしれません。人事制度設計コンサルタントは高い専門性と客観性を提供してくれます。人事制度設計コンサルタントを利用するメリットを解説します。
他社事例などの豊富な事例を提供
人事制度を設計する際は競合他社との水準も考慮に入れる必要があります。人事制度設計コンサルタントは他社事例を元に、専門的なアドバイスができるため、社内で納得感を持ったクオリティの高い人事制度を設計することができます。
プロのノウハウを吸収できる
人事設計コンサルタントは経営層だけでなく、人事担当者と連携しながら制度設計を進めます。コンサルタントから専門的なアドバイスを受けることで、人事担当者がプロのノウハウを吸収でき、人事制度上の課題の発見、問題の解決までをスムーズに行えるでしょう。
コンサルタントを利用する際の注意事項
高い専門性と客観性を持つコンサルタントですが、利用する際に注意する点を解説致します。
自社でやりたいことを決めておく
自社の企業理念の策定は自社でしか出来ません。自社がどのような方向に向かいたいかは最低でも決めておく必要があります。課題の抽出まで支援してくれるコンサルタントもいますが、何でも丸投げしてしまうようでは良い人事制度設計は行なえません。
コストがかかる
外注サービスなのでどうしても費用がかかります。しかし費用の安さだけでコンサルタントを選ぶのはおすすめできません。コストがかかったとしても自社にマッチしたサービスを選びましょう。またコンサルタントは得意分野があるため、得手不得手も必ず確認する必要があります。
納得度の高い人事評価制度の構築をHRBrainコンサルティングで実現
現行の人事制度に関してこのようなお悩みはありませんか?
「評価制度が上手く機能しておらず、運用が形骸化している…」
「評価者ごとに評価基準にバラつきがあり、社員から不満が出ている…」
「自社に合った評価制度をゼロから構築したいが、何から着手すればよいかわからない…」
人事制度コンサルティングを活用することで、自社にはない知見を取り入れながら、最適な人事制度構築が可能になります。
また、人事コンサルタントのサポートから新しく人事制度を導入したものの、制度の運用が上手く行かず、新たに別の人事コンサルタント企業に依頼することで、課題が解決した事例もあります。
人事制度に関する課題を感じた際には、一度HRBrain コンサルティングへの相談を検討してみてはいかがでしょうか。
HRBrain コンサルティングの特徴
業種・規模・目的に応じた100社100通りの柔軟な人事評価制度構築
評価制度は経営層と社員が対話するための共通言語であると捉え、お客様の「今」と「未来」に最適な制度設計を実現します。
制度構築だけでなく、制度定着まで中長期的に運用サポート
評価制度の構築だけで終わらず、制度の移行スケジュールの作成や制度説明会、評価者・被評価者研修に加え、制度の定着までをサポートし、組織の成長を生み出します。
“シリーズ累計2,500社以上” 業界トップクラスのサービス運用実績!
創業以来、累計導入社数2,500社以上※であるHRBrainシリーズ(タレントマネジメントシステム、組織診断サーベイ、労務管理クラウドなど)の運用支援をしています。あらゆる業種業態の成功事例・失敗事例を共有しながら、お客様とともに各社の特徴・ご要望に合わせた評価制度構築を提供します。
※2023年9月時点