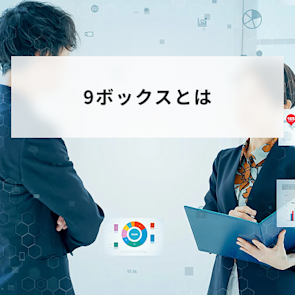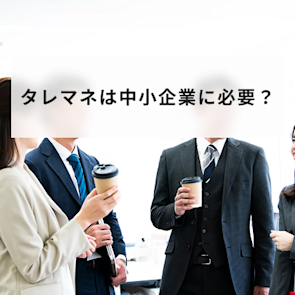人事評価はエクセルが便利?無料テンプレートとシステム移行の方法
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- 人事評価をエクセルで!すぐに使える無料テンプレートと活用方法
- 職業能力開発シート|厚生労働省
- 判定目安表(評価ガイドライン)|厚生労働省
- 人事評価をエクセルで管理するメリット3選
- コストが少ない
- 自社の用途に合わせてカスタマイズしやすい
- 操作性に慣れているため使いやすい
- 人事評価をエクセルで管理するデメリット3選
- ファイルやデータの管理が煩雑化しやすい
- 情報漏洩やデータ紛失のリスクがある
- 数式や関数のエラーに気づきにくいケースがある
- 人事評価でエクセルを使う際のポイント
- エクセルから人事評価システムに切り替えるべきタイミング
人事評価を効率的に行うためには、評価基準を明確にし、従業員ごとの成果や行動を記録できる仕組みが欠かせません。なかでもエクセルを活用した評価シートは、初期コストを抑えつつ短期間で導入できる方法として多くの企業で利用されています。
自社の等級や評価項目を自由に設定でき、配布や集計も簡単に行える点が特徴です。さらに、厚生労働省が公開している無料のテンプレートを活用すれば、公平で客観性のある評価体制をすぐに導入できます。
その一方で、組織の成長や従業員数の増加に伴い、エクセルでの運用に限界を感じ始める企業も少なくありません。
そこで本記事では、公式サイトで公開されているシートを用いたエクセルでの設計方法から活用ポイント、専用システムへの移行タイミングについて解説します。
【関連コンテンツ】
人事評価をエクセルで!すぐに使える無料テンプレートと活用方法
人事評価をエクセルで管理する際に役立つのが、厚生労働省が公式に配布しているシートです。これらは専門家の監修に基づき作られており、評価基準が明確で実務に直結する内容になっています。
ここでは代表的な2つを紹介します。
【関連コンテンツ】
職業能力開発シート|厚生労働省
厚生労働省が提供する職業能力開発シートは、従業員のスキルや行動を具体的な項目に沿って評価できるように設計されたテンプレートです。
このシートには、各職種で求められる具体的なスキルや能力要件が体系的に整理されており、基準に対して〇・△・×の評価を上司と部下それぞれが記入できるようになっています。
たとえば、営業職であれば「顧客開拓力」「提案力」「交渉力」などの項目が具体的な行動指標とともに定義されており、これをベースに自社の営業プロセスに応じて「新規開拓件数」「既存顧客深耕率」などの定量的指標を追加することで、オリジナルの評価シートを作成できます。
このシートを利用すると、評価者ごとに判断がばらつきにくくなり、従業員の成長度合いを数値で追跡可能です。実際の活用時には、職業能力開発シートをダウンロードし、自社の職種構成に合わせて必要な能力項目を抽出・編集してください。
出典:厚生労働省「キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード」
判定目安表(評価ガイドライン)|厚生労働省
厚生労働省の判定目安表は、評価の基準を統一するために活用できるガイドラインです。
各評価項目に対して具体的な行動指標や成果指標が示されており、A・B・C評価の判定基準が明確に定義されています。
たとえば「業務遂行力」を評価する場合、「自分の業務を計画通りに進められる」「周囲と協力して成果を出せる」などのような具体的な行動例と判定基準が示されています。これをエクセル上に組み込むことで、評価者全員が同じ目線で判断でき、評価のばらつき防止が可能です。
とくに複数の上司や部門間で評価を行う場合に有効で、納得感のある人事評価を実現できるでしょう。
出典:厚生労働省「判定目安表(評価ガイドライン)一覧表」
人事評価をエクセルで管理するメリット3選
人事評価にエクセルを利用することは、コストを抑えて柔軟な運用ができるため、とくに中小企業において多くのメリットがあります。以下では、具体的にメリットを3つ紹介します。
コストが少ない
自社の用途に合わせてカスタマイズしやすい
操作性に慣れているため使いやすい
人事評価をエクセルで始める際には、ぜひ参考にしてください。
コストが少ない
エクセルを用いた人事評価は、専用の人事評価システム導入費用やサーバー利用料が不要なため、低コストで運用できます。Microsoft Officeを契約している企業であれば、新たな投資なしで評価シートの作成・運用が可能です。
たとえば、厚生労働省が公開している無料テンプレートをダウンロードして利用すれば、初期設計にかかる工数も大幅に削減できます。
そのため、人事制度を整備中の企業や従業員数が少ない組織では、まずはエクセルで試すアプローチが効果的です。実際に運用を通じて課題を把握し、徐々に必要に応じてシステム導入を検討することで、費用対効果の高い評価体制を築けるでしょう。
自社の用途に合わせてカスタマイズしやすい
エクセルは行や列を自由に編集できるため、自社の等級制度や職種に合わせた評価項目を柔軟に設定可能です。
たとえば、営業職向けには「売上達成率」や「顧客対応力」を重視し、技術職向けには「問題解決力」や「技術習得度」を追加するなど、業務内容に直結した評価基準を簡単に組み込めます。さらに、関数や条件付き書式を活用すれば、自動集計や色分け表示によって評価結果を視覚的にわかりやすく表示できます。
標準化された専用システムでは柔軟性に限界があるケースもありますが、エクセルは小規模な改修を人事担当者自身で行えるため、企業の成長段階や組織の変化に応じてスムーズに評価シートを進化させられる点が魅力です。
操作性に慣れているため使いやすい
エクセルは多くの従業員がすでに慣れ親しんでいるツールであるため、導入時の教育コストや抵抗感を最小限に抑えながら、本格運用を開始できます。
具体的には、入力フォームに点数やコメントを入力する作業は、通常の業務での表計算や報告書作成と大きな違いがないため、マニュアルや特別な研修も不要です。また、ファイルをOneDriveやSharePointなどのツールで共有すれば、複数の評価者が同時にアクセスして作業できるため、評価業務の進行管理も容易になります。
操作面で新たな負担がない分、評価の正確性や公平性の確保などの本質的な改善に集中できる点がエクセル運用の大きな強みです。
人事評価をエクセルで管理するデメリット3選
人事評価にエクセルを利用することは手軽に始められる一方で、運用の段階でさまざまな課題に直面することがあります。
ここでは、人事評価をエクセルで管理する際の主なデメリットを3つ紹介します。
ファイルやデータの管理が煩雑化しやすい
情報漏洩やデータ紛失のリスクがある
数式や関数のエラーに気づきにくいケースがある
人事評価をエクセルで運用する際は、これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることで適切に利用できるでしょう。
ファイルやデータの管理が煩雑化しやすい
エクセルで人事評価を運用する際のデメリットは、評価シートの配布・回収・バージョン管理が複雑になりやすい点です。
たとえば、評価対象者が増えれば増えるほど、各評価者が入力したファイルが多数発生し、どのファイルが最新版なのか判断が難しくなります。また、過去のデータを蓄積して傾向を分析する作業は、ファイルを年度ごとに分けて保存することが多いため、横断的な比較に膨大な時間が必要です。
ファイル数の増加やボリュームが増大することによるファイルの煩雑化は、評価業務全体の効率を下げるため、とくに従業員数が多い組織では注意する必要があります。
情報漏洩やデータ紛失のリスクがある
人事評価をエクセルで運用する際には、ファイルの誤送信や不適切な共有により、機密性の高い評価データが漏洩するリスクが常につきまといます。
エクセルファイルは、メール添付や共有フォルダでの配布が一般的です。しかし、送信先の間違いやアクセス権限の設定ミス、パスワード保護の不備などにより、意図しない第三者に評価情報が漏洩する可能性もあります。また、個人のパソコンに保存されたファイルの紛失や、USBメモリでの持ち出しによるセキュリティリスクも無視できません。
そのため、実際の運用では、アクセス権限を細かく管理して定期的にファイルのバージョンを確認したり、専用システムの導入を検討したりするなどの対策が必要不可欠です。
数式や関数のエラーに気づきにくいケースがある
エクセルを利用する際には、複雑な数式や関数使用時に計算エラーが発生しても、目視での確認が難しく、誤った評価結果が出力されるリスクがあることを把握しておきましょう。
たとえば、セル参照がずれていたり、四捨五入処理が不適切だった場合でも、見た目は正しく表示されているように見えることがあります。その結果、誤った集計値や評価点が人事判断に利用され、従業員の評価に不公平が生じる可能性があります。
とくに複雑なシートを作成した場合、チェック体制を設けなければエラーの発見は困難です。人事担当者が関数の知識を十分に持っていないと、問題が長期間放置されるリスクもあります。
このようなエラーを防ぐには、複数人で検算を行う仕組みを設けることが効果的ですが、工数が増えるため、対策を講じる際には現場と相談しながら検討する必要があるでしょう。
人事評価でエクセルを使う際のポイント
エクセルで人事評価を運用する場合、正しいルールを設定しなければデータ管理や公平性の確保が難しくなります。そのため、効率的に活用するには以下の4点を押さえることが効果的です。
ファイル名の命名規則を定める
ファイルの更新や複製にルールを定める
データの改ざんや不正コピーに気を付ける
ファイルの持ち出しやメール添付に関するルールを決める
具体的な命名規則としては、最新版ファイルにはその旨を記載する、更新日付を記載するなどの例が挙げられます。その結果、最新版の特定が容易になり、ファイルを探す時間が削減されるはずです。また、OneDriveやSharePointを活用して更新ルールを決めておけば、複数人で同時に作業する際の混乱を避けられます。
さらに、パスワード・アクセス権限の設定や、社外への持ち出しルールを徹底することで評価データの漏洩リスク低減が期待できるでしょう。
これらの工夫を組み合わせることで、エクセル運用の弱点を補いながら、現場で実践しやすい評価体制を維持できます。
エクセルから人事評価システムに切り替えるべきタイミング
人事評価をエクセルで管理している企業でも、ある段階を迎えるとシステムへの切り替えが効果的になります。
具体的には、以下のタイミングでシステム移行するのが一般的です。
評価者や担当者の業務負担が増加したとき
過去の評価データを活用できていないとき
より公平な評価制度を構築したいとき
エクセルは導入のしやすさが魅力ですが、従業員数や評価項目が増えると管理が追いつかなくなり、制度全体の信頼性を損なう可能性があります。
たとえば、数十人規模ならエクセルでも対応可能ですが、数百人を超えると配布や集計に膨大な時間がかかり、ファイル管理に時間が取られてマネジメント業務に支障が出る可能性があります。また、過去データを参照して人材育成計画や昇進判断に活かしたい場合も、システムの一元管理機能を利用する方が効率的です。
さらに、評価の公平性や納得感を高めたい場合、システムに搭載された評価ガイドラインやワークフロー承認機能を用いることで、属人的な判断を防ぎやすくなります。
このように企業の成長段階に合わせながら、エクセルからシステムに移行すべきタイミングを見極めることが重要です。
【関連コンテンツ】