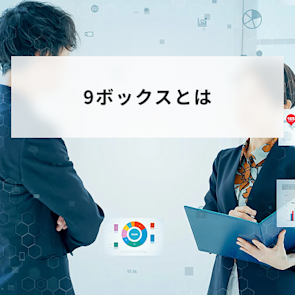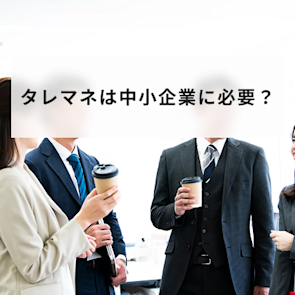甘辛調整とは?重要性や具体的な調整方法、評価制度の改善方法を解説
シンプルな操作で評価業務の効率化を実現
- 人事評価の甘辛調整とは
- 人事評価で甘辛調整がされる理由
- 評価者によって評価方法に違いが生じるため
- 評価基準が曖昧なため
- 被評価者のエンゲージメントを高められるため
- 甘辛調整の具体的なやり方
- 平均点を用いて調整する
- 標準的な評価者を基準に調整する
- 正規分布をもとに調整する
- 標準偏差を用いて調整する
- 評価者会議で調整する
- 甘辛調整をして人事評価を公正にする方法
- 定量評価と定性評価のバランスをとる
- 評価者の認識をすり合わせる
- 継続的なコミュニケーションで納得感を高める
- 人事評価システムを活用して効率化と透明性を両立する
- 甘辛調整に頼らない評価制度の作り方
- 「HRBrain 人事評価」で適切に甘辛調整をして、組織力を高めよう
「甘辛調整って何?」「なぜ重要視されるの?」という方のため、甘辛調整の基本や、従業員の納得感を高めるための具体的な方法を解説します。
また、甘辛調整の効果をさらに高めるためのツールや、甘辛調整に頼らない評価制度の作り方も紹介するので、従業員のエンゲージメント向上、組織の成長へつなげるためにお役立てください。
人事評価の甘辛調整とは
甘辛調整とは、評価者や部門によって生じる評価の「甘さ」や「辛さ」を補正し、全社員を公平な基準で評価するための工程です。たとえば、標準偏差やZスコアを用いて、ある上司の4.0点と別の部署の3.0点が、同程度の評価であることを数値で示します。
このように人事評価の甘辛調整は、評価を「修正」するのではなく、評価者ごとの尺度の違いを「標準化」する作業です。適切に甘辛調整をすると、不公平感の解消や納得感の向上、モチベーション維持につながります。
人事評価で甘辛調整がされる理由
人事評価で甘辛調整がされる理由は、以下の3つです。
評価者によって評価方法に違いが生じるため
評価基準が曖昧なため
被評価者のエンゲージメントを高められるため
甘辛調整の重要性を理解し、公正な評価によってさらに組織を成長させられるよう、上記3つの理由を詳しく見ていきましょう。
評価者によって評価方法に違いが生じるため
各評価者には、全体的に評価を甘くする「寛大化傾向」や、厳しくする「厳格化傾向」などがあり、主観によって評価基準が異なります。たとえば、特定の優れた点に引きずられる「ハロー効果」や、自身の能力を基準に評価する「対比誤差」も、評価の公平性を歪める一因です。
これらのバイアスを放置すると、被評価者が同じ社員でも誰が評価者になるかによって報酬や昇格に差が生じ、社員が不公平感を募らせたり、モチベーションの低下を招いたりするかもしれません。そういったことがないよう、評価の客観性を確保するために甘辛調整が実施されます。
評価基準が曖昧なため
主体性やリーダーシップといった評価項目は、評価者の主観に依存する部分があるため、甘辛調整で公平性を保つことが大切です。具体的には、同じ行動に対して、ある評価者は積極的に貢献したと評価し、別の評価者は協調性に欠けると判断する可能性があります。
このような評価基準の解釈の違いによって、部門間での評価基準の差を広げないため、甘辛調整が行われるべきです。
【関連コンテンツ】
被評価者のエンゲージメントを高められるため
甘辛調整をすると、被評価者である社員のエンゲージメントと組織への信頼感を向上させる効果を期待できます。評価者の違いによって辛く評価された際、甘辛調整で適切な評価に補正されれば、社員は評価制度を信頼し、フィードバックを前向きに受け止めやすくなります。
たとえば厳しい評価者のもとで働く社員は、評価基準が甘い評価者のもとで働く社員と比べ、自分の努力が正当に評価されていないと感じやすいです。そういった際、当初の評価が低くても、甘辛調整をしてもらえたとわかれば、組織全体のエンゲージメント向上につながります。
【関連コンテンツ】
甘辛調整の具体的なやり方
適切に甘辛調整をする方法は、以下の通りです。
平均点を用いて調整する
標準的な評価者を基準に調整する
正規分布をもとに調整する
標準偏差を用いて調整する
評価者会議で調整する
自社の評価制度にふさわしい調整方法を選び、より公平で納得感のある人事評価を実現するため、上記5点をチェックしていきましょう。
平均点を用いて調整する
平均点を活用した甘辛調整は、評価者ごとの「評点の平均値」と「組織全体の平均値」との差を出し、個人の評点に加減する手法です。たとえば、組織全体の平均が3.5点で、ある評価者の平均が4.2点だった場合、その評価者がつけた部下全員の評点から0.7点を減算します。
このように比較的シンプルに計算でき、Excelやスプレッドシートなどでも甘辛調整しやすい点が、平均点を用いて調整する方法の利点です。ただし、評価のばらつき(標準偏差)の違いを補正することは難しいといえます。
標準的な評価者を基準に調整する
標準的な評価者を基準とした甘辛調整は、以下のような手順により、組織内で最も妥当な評価傾向を示す評価者を「基準評価者」とし、他の評価者の評点を調整する方法です。
- 評価者間の一致度を分析する
- 全体平均に最も近い評価パターンを持つ評価者を特定する
- 他の評価者の評点をZスコア化(※)する ※数値の変換により、異なるデータを同じ基準で比較する手法。
- 基準評価者の基準で再変換する
標準的な評価者を基準とする甘辛調整には、実在する評価者の基準を使うため、現場の納得感が得やすいという利点がありますが、基準評価者の選定には客観性が求められる点を理解しておきましょう。
正規分布をもとに調整する
正規分布を基準とした甘辛調整は、評価結果を以下のような正規分布(ベルカーブ)の形に当てはめる方法です。
上位:10%
中上位:20%
中位:40%
中下位:20%
下位:10%
相対的なランク付けがしやすい、過度な甘辛調整になりにくいといった利点があるものの、正規分布をもとに調整する企業は少ないです。
なぜなら実際は正規分布でなく、一部のハイパフォーマーが突出するケースが多く、「不当な評価になる」「モチベーションを低下させる」というリスクを高めやすいからです。
標準偏差を用いて調整する
標準偏差を用いた甘辛調整は、以下の手順で評価者ごとの平均点と標準偏差の両方を考慮する方法です。
- 個人の評点を評価者基準でZスコア化する
- 1で得たZスコアを組織全体の分布に変換する
上記のように標準偏差を用いると、評価者の甘辛加減だけでなく、評価者全体のばらつき方の違いも補正できます。統計的根拠が明確で説明責任を果たしやすく、人事評価システムに標準搭載されていることが多い点も特徴的です。
評価者会議で調整する
評価者会議(キャリブレーション会議)による甘辛調整は、数値的な補正だけでは解決できない評価の質を是正するための手法です。評価者会議では、事前に部門別の評価データや、評価の根拠となる具体的な行動証拠を共有し、客観的な議論をします。
このような進め方により、評価者同士が基準をすり合わせ、全参加者のコンセンサスを得て最終決定します。評価者会議は、統計的手法だけでは捉えきれない個別事情や成長の兆しを反映でき、評価者間の基準合わせにも効果的です。
【関連コンテンツ】
甘辛調整をして人事評価を公正にする方法
甘辛調整で人事評価の公正性を確保するためには、以下の方法により、評価プロセス全体を改善することが大切です。
定量評価と定性評価のバランスをとる
評価者の認識をすり合わせる
継続的なコミュニケーションで納得感を高める
人事評価システムを活用して効率化と透明性を両立する
人事評価の公正性を確保し、組織の成長を促進するため、上記4つの方法を見ていきましょう。
定量評価と定性評価のバランスをとる
甘辛調整の精度を高めるためには、評価項目を成果(What)と行動(How)に明確に分離し、定量評価と定性評価の適切なバランスを設計することが大切です。売上達成率などの定量評価は客観的な数値で測定でき、リーダーシップなどの定性評価は評価者の主観に依存します。
定性評価については、評価段階ごとに具体的な行動例を明示するなどの工夫をして、評価者間の解釈のブレを最小限に抑え、甘辛調整後の結果に対する従業員の納得感を高めましょう。
【関連コンテンツ】
評価者の認識をすり合わせる
適切に甘辛調整をするため、評価者研修などを実施し、評価者間で評価基準の認識を統一することが大切です。たとえば、ハロー効果や中心化傾向といった評価バイアスについて、具体的な事例を学んでおくと、適切に甘辛調整を実施できます。
また、判断が難しいケースについて評価者全員で話し合い、認識を統一する方法もよいでしょう。
【関連コンテンツ】
継続的なコミュニケーションで納得感を高める
甘辛調整をして公正な評価を実現するためには、被評価者とのコミュニケーションにより納得感を高めることが大切です。評価期間中は、1on1ミーティングやフィードバック面談を通じて、評価基準や期待される行動を具体的に伝えましょう。
評価結果のフィードバック時に調整前後のスコアや順位を示し、甘辛調整の根拠と効果を具体的に説明すると、従業員は評価制度への信頼を深め、フィードバックを成長の機会として受け止めやすくなります。
【関連コンテンツ】
人事評価システムを活用して効率化と透明性を両立する
甘辛調整を賢く進めるためには、人事評価システムを活用して、業務効率と透明性を高める方法がおすすめです。標準偏差調整や平均点調整、ベルカーブ調整など、甘辛調整に用いる手法を設定できる人事評価システムを選べば、解釈による評価のばらつきを防げるでしょう。
また人事評価システムに、調整前後の分布比較や部門間格差の可視化といった機能があれば、甘辛調整の根拠を示す際にも役立ちます。
【関連コンテンツ】
甘辛調整に頼らない評価制度の作り方
甘辛調整に頼らず、根本的に公正な評価制度を構築するため、以下のような仕組みを作りましょう。
仕組み | 概要 | 効果 |
|---|---|---|
BARS(行動基準評定尺度) | 各評価項目に対し、具体的な行動例を明文化する。 | 評価者による解釈のブレを最小限に抑え、評価の一貫性を高める。 |
複数評価者制度 | 一人の従業員を複数人が多角的に評価する。 | 単一の評価者による偏りを構造的に防ぎ、評価の客観性を高める。 |
評価手法の組み合わせ | 行動面を測るコンピテンシーと、成果を測るOKRを組み合わせる。 | 成果(What)と行動(How)の両面から評価することで、測定可能な公正な評価基準を設定する。 |
上記の仕組みを作ると、評価の主観や偏りを抑え、透明性を高めやすくなります。結果として従業員は「なぜその評価になったか」を理解しやすくなるでしょう。成果だけでなく行動も評価されるため、自律的な成長が促され、組織全体の生産性向上にもつながります。
【関連コンテンツ】
「HRBrain 人事評価」で適切に甘辛調整をして、組織力を高めよう

評価者ごとに評価スコアの甘辛を可視化して調整できる点から、人事評価の公平性を保ちたい場合、HRBrain 人事評価がおすすめです。HRBrain 人事評価なら、前回の評価結果と比較し、変動が大きいメンバーや支援が必要なメンバーの確認もできます。
また、シートカスタマイズ機能を使えば、評価項目にあわせてレイアウトを自由に変更できるうえ、合計や平均などの独自ロジックを設定し、自社に合う評価方法を模索することも可能です。
他にも「人事評価プロセスにあわせてワークフローを設定できる」「スマホで評価シートの閲覧・入力が可能」など、効率良く評価するための機能がある点もHRBrain 人事評価の魅力です。HRBrain 人事評価が気になる方は、以下から詳細をチェックしてみましょう。