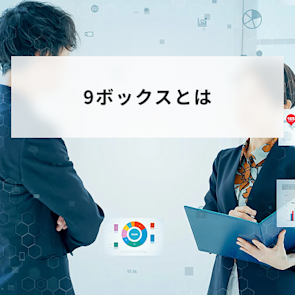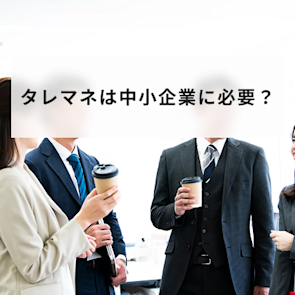360度多面評価って意味あるの?バレない?失敗を防ぐための準備とは
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- 360度多面評価について
- 360度多面評価が導入されるようになった背景と目的
- 360度多面評価導入の背景
- 360度多面評価導入の目的
- 360度多面評価のメリット・デメリット
- 360度多面評価のメリット
- 360度多面評価のデメリット
- 360度多面評価が有効な企業
- 上司ひとりで多数の部下を管理している
- 社内のコミュニケーションが希薄
- 360度多面評価の失敗例
- 費用対効果が合わない
- 社内の人間関係の悪化
- 評価に対する納得度の低下
- 従業員のモチベーションの低下
- 現場の負荷が大きい
- 360度多面評価を失敗しないためにすべきこと
- 360度多面評価の実施目的を周知する
- 評価ガイドラインの作成
- 360度多面評価の実施計画を立てる
- 評価対象者に適切なフィードバックを行う
- 評価対象者の行動計画を作成する
- 360度多面評価を失敗しないためのシステム導入
- 運用負荷の軽減
- 匿名性の担保
- 正確なフィードバック
- 360度多面評価を意味ある評価へ
- 「バレる?」「意味がない?」など360度多面評価の不安を解消
「360度多面評価」は複数の従業員が関わるからこそ、事前にしっかりと設計しないと「評価がバレないのか?」「実施の意味があるのか?」と不安を抱く従業員が出てしまう場合があります。
今回は、「360度多面評価」を失敗しないために、360度多面評価の「失敗例」や「失敗しないためにすべきこと」について解説します。
顧客満足度No.1*のタレントマネジメントシステムHRBrainが提供する「HRBrain 360度評価」では、人事評価に対する納得度向上や従業員のスキルの見える化を実現します。
設問テンプレートも完備されており、初めてでも評価シートの設定や配布・集計までを簡単に行うことができます。
360度多面評価について
360度多面評価は、評価対象者に対して、上司・同僚・部下など立場の異なる人が多面的に評価をする手法です。
「360度評価」「360度フィードバック」「多面評価」と呼ばれることもあります。
360度多面評価は、「評価」と名前がついていますが、もともとは「能力開発の手法」としてアメリカで誕生しました。
そのため、人材育成の手法として用いられる場合もあります。
▼「360度評価」についてさらに詳しく
360度評価とは?導入目的や手順、メリット・デメリットについて詳しく紹介!
360度多面評価が導入されるようになった背景と目的
360度多面評価が、さまざまな企業で導入されるようになった「背景」や「目的」について確認してみましょう。
360度多面評価導入の背景
360度多面評価が導入されるようになった背景には、「ワークスタイルの多様化」があり、上司ひとりの評価では、公平な評価が難しくなってきていることがあげられます。
また、企業がピラミッド型組織からフラットな組織へと変革してきていることをうけて、さまざまな企業で、360度多面評価が取り入れられるようになりました。
360度多面評価導入の目的
360度多面評価の目的について確認してみましょう。
客観的な評価を得るため
評価対象者に成長を促すため
企業文化や価値観の浸透のため
評価対象者の日常行動を可視化するため
360度多面評価は、複数の立場が異なる従業員から「客観的な評価」を得るための手段として有効です。
複数の立場の人からの「客観的な評価」は、日頃上司の目が届きにくい従業員の日常行動を可視化することや、評価対象者に成長を促すことができます。
また、自社の評価基準を浸透させて、評価を実施することで、自社の企業文化や価値観を浸透させることも期待できます。
360度多面評価のメリット・デメリット
360度多面評価を失敗しないためにも、360度多面評価のメリットとデメリットについて確認してみましょう。
360度多面評価のメリット
客観的なフィードバックによって「強み」「弱み」を発見できる
評価への納得感が高まる
人材育成につながる
社内のコミュニケーションが活性化する
会社への帰属意識が芽生える
360度多面評価のデメリット
運用の手間が増える
不適切な評価が行われる可能性がある
上司が部下に厳しくなくなる可能性がある
360度多面評価が有効な企業
360度多面評価を導入することによって、効果が出やすい企業には、どのような特徴があるのかを確認してみましょう。
上司ひとりで多数の部下を管理している
上司ひとりに対して、部下が7名以上おり、上司ひとりでの評価が難しい場合や、上司が忙しいなどの理由で、上司ひとりでは「部下の状態が把握できない」状況が発生し、部下から不満が出ている場合、360度多面評価は有効です。
さまざまな立場から評価を行うことで、上司ひとりではなかなか気付けない部下の状態を可視化して把握することができ、評価にも納得感が生まれるでしょう。
また、上司の評価スキルが不足している場合には、人事評価制度研修を実施するようにするとよいでしょう。
▼「人事評価制度研修」についてさらに詳しく
人事評価制度研修はなぜ必要?研修の目的や被評価者メリットについて解説!
社内のコミュニケーションが希薄
上司と部下や、従業員同士のコミュニケーションが希薄な場合にも、360度多面評価は有効です。
360度多面評価の振り返り(改善行動の進捗)を行う「1on1ミーティング」を導入することが、コミュニケーションの活性化につながるでしょう。
▼「1on1ミーティング」についてさらに詳しく
1on1とは? 従来の面談との違いや効果を高めるコツ
360度多面評価の失敗例
360度多面評価は、立場の異なる人が多面的に評価に関わるため、通常の評価制度では想定できないような、失敗が発生する可能性もあります。
360度多面評価が意味のないものになってしまったり、失敗してしまうケースには、どのようなことが考えられるのか確認してみましょう。
費用対効果が合わない
360度多面評価は、従業員の成長や人材育成を目的として導入される場合が多いため、360度多面評価を導入してから、効果が見えるまでに、年単位の時間がかかります。
そのため、360度多面評価が、長期的な施策であることを周知できていないと、導入コストに対して費用対効果が見合わないと感じてしまう場合があります。
社内の人間関係の悪化
360度多面評価を導入することで、従業員同士での遠慮が増え、「評価を気にして言いたいことが言えない」など、円滑なコミュニケーションが取れなくなってしまう場合があります。
また、従業員同士で評価しあうことで、不信感が生まれ、業務に支障が出てしまうこともあります。
評価に対する納得度の低下
360度多面評価では、評価に慣れていない従業員も評価者として参加するため、評価スキルがなく、業務とは関係のない私情が反映されたり、主観的な目線で評価をしてしまうことがあります。
そのため、評価対象者が評価に納得ができないということがあります。
従業員のモチベーションの低下
360度多面評価での評価に納得ができない場合はモチベーションも低下してしまいます。
また、評価内容によっては、落ち込んでしまったり、意欲を失ってしまう場合もあります。
上司が評価を受ける場合、部下からの評価によっては、マネジメントに支障が出てしまう場合もあります。
現場の負荷が大きい
360度多面評価では、従業員ひとりひとりが、複数の評価を行うことになるため、従業員の負担が大きくなります。
360度多面評価に時間を取られ、業務に支障が出てしまう場合もあります。
また、従業員によっては作業に追われ、適当に評価を終わらせてしまうこともあるかもしれません。
360度多面評価を失敗しないためにすべきこと
360度多面評価を失敗しないためにも、すべきことを確認してみましょう。
360度多面評価の実施目的を周知する
360度多面評価は多くの従業員が関わることになります。
導入のタイミングで「なんの目的のために導入するのか」をしっかりと伝えていないと、従業員の理解が得られず、「無駄な仕事が増えた」と思われてしまいます。
そうなると、積極的な参加は望めません。
「自分のためにも、会社のためにも良い施策である」という気持ちになってもらうために、経営陣からメッセージを伝え続けることが重要です。
また、360度多面評価は即効性のある施策ではありません。
長期的な目線で取り組む施策であることも周知しておく必要があるでしょう。
評価ガイドラインの作成
360度多面評価は多くの従業員が関わるため、評価にバラつきが発生してしまう場合があります。
そのため、事前に「評価ガイドライン」を作成し、全体の評価基準を統一しておくことが大切です。
360度多面評価の実施計画を立てる
360度多面評価を実施するためには、実施計画を立て、実施計画の流れに沿って運用する必要があります。
360度多面評価の実施計画の流れ
評価基準・項目を設定する
評価者と評価対象者を設定する
実施方法を決定する
スケジュールを立てる
評価の取り扱いの仕方を決定する
評価者への配布方法を決定する
これらの流れは、「360度評価システム」の導入で工数を削減することも可能です。
▼「360度評価システム」についてさらに詳しく
360度評価システム導入の比較ポイントは?メリット・導入前準備まとめ
評価対象者に適切なフィードバックを行う
評価対象者に評価の結果を確認させるだけにとどまらず、上司から対面でのフィードバックを行うようにしましょう。
評価対象者の良かった点、改善すべき点をしっかりとフィードバックすることで、評価対象者に「見られている」「評価されている」という意識が育ちます。
これは、「従業員自身にも360度多面評価のメリットがある(自分に還元される)」と実感してもらうためにも重要なプロセスです。
評価対象者の行動計画を作成する
評価者はフィードバックを受けて「終わり」にするのではなく、フィードバックをもとに、「行動計画」を作成しましょう。
自身の強み、見つかった改善点を踏まえて、具体的なアクションプランに落とし込むことで360度多面評価は成果を発揮します。
360度多面評価を失敗しないためのシステム導入
360度多面評価を失敗しないためのシステム導入のメリットについて解説します。
運用負荷の軽減
匿名性の担保
正確なフィードバック
運用負荷の軽減
360度多面評価は、ひとりの従業員の評価に複数の従業員が関わるため、通常の評価精度と比べると、運用負荷がかかります。
システム導入をすることで、設問設計、評価シートの作成、配布、回収、未回答者への催促、集計、データの可視化など、360度多面評価に関わる業務を効率化することができます。
また、集計結果を一元管理できるため、人材育成や人事評価への反映もスムーズに行えるようになります。
さらに、スマホからの回答が可能な場合、回答がスムーズに行え、現場の負荷を軽減することもできます。
匿名性の担保
360度多面評価は、匿名性を担保することで、評価者が率直な評価を行うことができるようになります。
システムを導入することで、より匿名性を担保することができ、「360度多面評価がバレてしまうのではないか?」というような、従業員の不安も減らすことができるでしょう。
正確なフィードバック
システムを導入することで、評価データを一元管理することが可能です。
360度多面評価で収集したデータを、自動で集計でき、データの見える化も可能なため、データにもとづいた正確なフィードバックができるため、評価に対してより納得感が得られます。
また、データをもとに、人材育成や人事評価、マネジメント層の育成にもつながります。
360度多面評価を意味ある評価へ
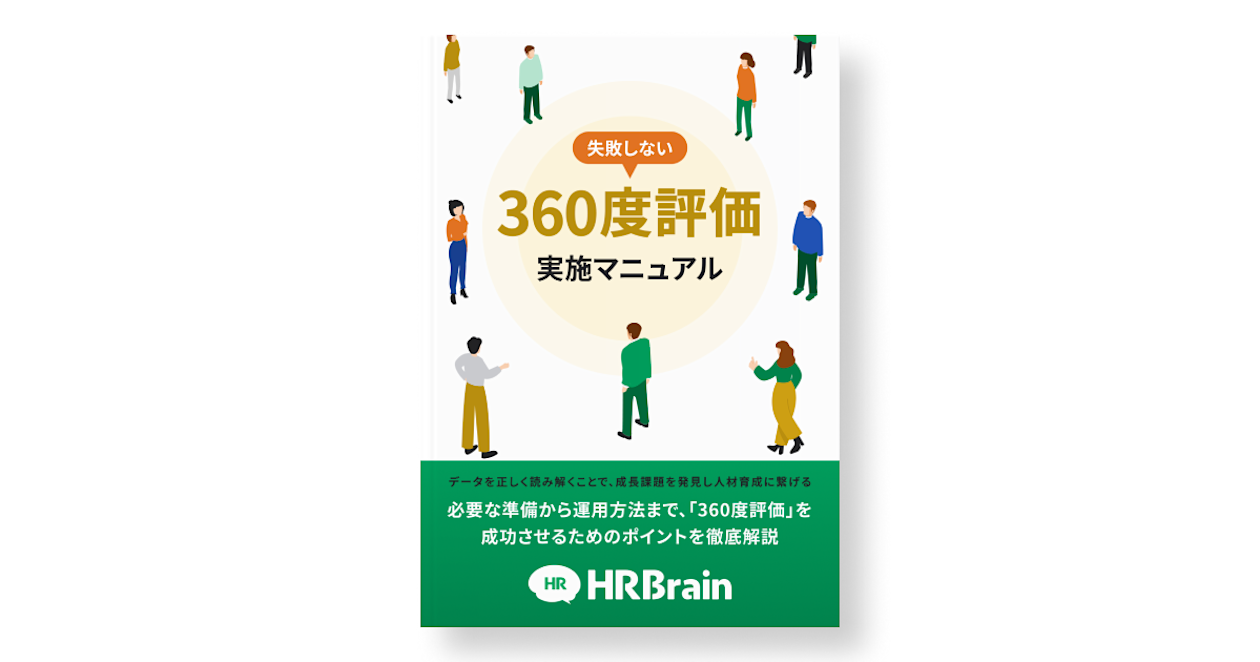
360度評価実施マニュアル
360度評価とは、評価対象者に対して上司・同僚・部下など立場の異なる人が多面的に評価をする手法です。
本書では、そんな360度評価の実施目的やメリット、開始までのステップをご紹介しています。
この資料で分かること
360度評価とは
360度評価のメリットと実施にかかる課題とは
360度評価を成功させるための3つのポイント
360度評価の運用を3STEPで解説
360度評価STEP別チェックシート
360度評価システム/コンサルティングサービス紹介
「バレる?」「意味がない?」など360度多面評価の不安を解消
360度多面評価の実施に対して、評価が従業員に「バレる?」「筒抜けになってしまう?」「意味がないのでは?」などの不安を持つ従業員もいるのではないでしょうか。
360度多面評価は、しっかり運用を行えば、客観的なフィードバックによって、評価対象者が自身の「強み・弱み」を発見し、スキルアップにつなげることが出来るというメリットがあります。
また、上司だけでなく複数の人から評価されることで、評価に「納得感」を得ることができます。
そして、評価対象者の成長(人材育成)や、能動的な改善行動につながるのです。
また、360度多面評価のフィードバックを行い、「改善点」を行動計画に落とし込み、定期的な「1on1」を行うことは振り返りとして重要であるとともに、社内コミュニケーションの活性化にも貢献します。
360度多面評価の実施にあたって、発生する情報管理や、実施工数の削減、匿名性の担保などは、システムを導入することで、大きく改善されます。