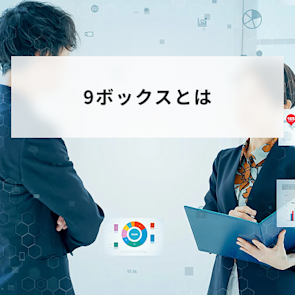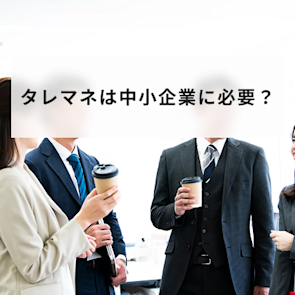営業利益とは?経常利益との違いや計算方法と目安を簡単に解説
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- 営業利益とは
- 営業利益の内訳
- 売上高
- 販売費及び一般管理費
- 売上原価
- 営業利益の計算方法
- 営業利益を英語で表すと
- 売上高営業利益率とは
- 売上高営業利益率の計算方法
- 売上高営業利益率の目安
- 営業利益と各種利益との比較
- 粗利
- 経常利益
- 純利益
- 営業キャッシュフロー
- 営業利益と営業キャッシュフローの違い
- 営業キャッシュフロー以外のキャッシュフロー
- 黒字倒産
- 損益計算書
- 営業利益の使い方
- 営業利益と人件費の関係
- 人件費の中で見直すべき項目
- 売上高営業利益率は賞与原資にも
- 営業利益の見直しのための「人事評価システム」の活用
営業利益とは、法人が「本業で稼いだ利益」を指し、企業の決算書などにも出てくる重要な指標で、各種利益用語の中でも重要な意味を持ちます。
この記事では、営業利益の意味や利益との違い、各種利益用語の解説、営業利益の計算方法、営業利益の目安として何パーセントが理想的か、営業利益と人事制度との関係について解説します。
営業利益の大きなウェイトを占める「人件費」の見直し
営業利益とは
営業利益とは、法人が「本業で稼いだ利益」を指し、損益計算書に記載される利益のひとつです。
また、個人事業主であれば収入から必要経費を差し引いた「所得金額」が営業利益になります。
営業利益の内訳
営業利益の内訳と詳細について確認してみましょう。
営業利益は「売上高」「販売費及び一般管理費」「売上原価」の3項目から算出されます
営業利益の内訳
売上高
販売費及び一般管理費
売上原価
売上高
売上高とは、「サービスの提供や商品を販売しどれだけ稼いだか」を指し、売上高が高ければ高いほど企業の利益が増えるため、売上高を増やすことは企業の命題となります。
販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費とは、「人件費や、交際費、通信費など」を指し、これらをうまくコントロールすることで企業の利益が確保できるため重要な指標です。
売上原価
売上原価とは、「販売した品物の仕入れに必要な合計総額」を指し、売上原価が低ければ低いほど営業利益が増えるため重要な指標です。
営業利益の計算方法
営業利益の計算方法について確認してみましょう。
営業利益の計算方法
営業利益=売上高−売上原価−販売費及び一般管理費
営業利益を増やすためには、売上を上げて、売上原価を下げ、人件費などをコントロールすることが大切です。
営業利益を英語で表すと
営業利益は英語で、「Operating income」と表記します。
また、営業利益の他に英語で表記される単語について確認してみましょう。
売上高
売上高は英語で、「Net Sales」と表記します。
販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費は英語で、「Selling, general and administrative expenses」と表記します。
営業利益の計算方法
営業利益の計算方法を英語で表すと、「Operating income」=「Net Sales」-「Selling, general and administrative expenses」となります。
売上高営業利益率とは
営業利益と同じような言葉で「売上高営業利益率」という言葉があります。
売上高営業利益率とは、「営業利益の売上高に対する割合」を指し、「本業でどれだけ効率的に稼ぐことができたかの割合」です。
売上高営業利益率の計算方法
売上高営業利益率の計算方法と平均的な割合について確認してみましょう。
売上高営業利益率の計算方法
売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100(%)
売上高営業利益率は、計算した結果が高ければ高いほど「企業の本業が好調」ということになりますが、もし0%に近い場合は、売上高を上げる、管理費を下げる、人件費を下げるなどの抜本的な改善を行う必要があります。
売上高営業利益率の目安
各業種における売上高営業利益率の目安はどの程度なのか、全業種の中央値について確認してみましょう。
また、企業別に取引の内容、管理費、売上原価などがバラバラであるため、各業種の売上高営業利益率の目安を確認してみましょう。
全業種の売上高営業利益率の中央値
全業種の売上高営業利益率の中央値は、「およそ4.5%」です。
不動産業の売上高営業利益率
不動産業の売上高営業利益率は、「おおよそ10%」ですが、取引の増減で割合に変動があります。
また、不動産取引が昨今減少しているため、「9%程度」まで中央値が変動しています。
不動産業は販売取引数自体は少ないですが、一取引での売上が高く、高付加のものを取引するため、売上高営業利益率が高くなる傾向があります。
小売業の売上高営業利益率
小売業の売上高営業利益率は、「おおよそ3%台」です。
小売業のように1回の取引額が低く、取引回数が多い、いわゆる「薄利多売」のビジネスモデルの業種は売上高営業利益率は低くなる傾向があります。
営業利益の大きなウェイトを占める「人件費」のための「人事評価」の見直し
⇒「ゼロから始める人事評価 資料3点セット」をタウンロード
営業利益と各種利益との比較
営業利益とあわせて、よく使われる利益用語で損益計算書にも載っている各種利益用語や、企業の利益を理解する際に重要な「損益計算書」と「財務三表」について確認してみましょう。
粗利
粗利とは、「売上総利益」のことで会社の儲けの源泉でもあります。
粗利の計算方法
粗利=売上高−販売原価
粗利に注目する理由
粗利に注目する理由は、粗利以上に経費を使わなければ会社に利益が残るためで、会社の利益の根本となり、重要な項目です。
経常利益
経常利益とは、企業が「本業以外も含めて経常的に得た利益」を指し、営業利益との違いは、資産運用益や利息なども含める点です。
経常利益の計算方法
経常利益=営業利益+営業外収益−営業外費用
営業外利益
営業外利益とは、「利息や不動産賃料」などが代表的なもので、利息や不動産賃料で得た利益が本業によるものならば「売上高」に区分されます。
営業外費用
営業外費用とは、「社債の債権者に支払う利息や有価証券を売却した際の損益など」が含まれます。
純利益
純利益とは、「経常利益から払う税や臨時的に発生した利益や損失を計算し最終的に企業に残ったお金」を指します。
純利益の計算方法
純利益=経常利益+特別利益−特別損失−住民税・法人税・事業税
特別利益
特別利益とは、「不動産などの固定資産を売却した際に得られた利益」ですが、特別利益かどうかの絶対的な基準はなく、一事案について個別の判断が必要です。
特別損失
特別損失とは、「火災や災害などの被害で被った損失」を指します。
営業キャッシュフロー
営業キャッシュフローとは、「本業を行った結果手元のお金がいくら増減したか」がわかる項目です。
営業利益と営業キャッシュフローの違い
営業キャッシュフローと営業利益は似たような意味ですが、イコールでは結びつきません。
営業キャッシュフローは「現金」がどれだけ増えたかを示す項目ですが、営業利益は「掛取引」があるため現金を受け取るタイミングにラグがあります。
例えば、お客様が飲食をした際に、現金でお支払いされたときと、クレジットカードでお支払いされたときでは、企業が受け取る現金にラグが発生するような状況です。
営業キャッシュフロー以外のキャッシュフロー
営業キャッシュフロー以外のキャッシュフローには、「投資活動によるキャッシュフロー」と「財務活動によるキャッシュフロー」があります。
投資活動キャッシュフロー
固定資産の売却や有価証券の購入などのキャッシュの出入りを表す項目です。
財務活動キャッシュフロー
銀行からの借り入れや返済などのキャッシュの出入りを表す項目です。
黒字倒産
黒字倒産とは、「営業利益は出ているのに支払いに必要な資金が不足してしまうこと」です。
営業利益も大事ですが、キャッシュフローがプラスになるように経営を行わなくてはいけません。
損益計算書
損益計算書とは、会社の利益や損失を知ることができる「財務諸表」で、英語では「Profit and Loss Statement」と表記し、「P/L(ピーエル)」と略されることもあります。
損益計算書は「収益−費用=利益」を見ることができるもので、「各種計算項目」から構成されていて、「粗利」や「営業利益」などは利益の一部分を切り取った値です。
損益計算書の各種計算項目
売上高
売上原価
販売管理費
営業外収益
営業外費用
特別利益
特別損失
法人税や住民税及び事業税
その他の財務諸表
賃借対照表(バランスシート)
キャッシュフロー計算書
損益計算書は「企業の利益」がわかる表ですが、賃借対照表は「企業の資産をどのように集めてきたか」がわかる表です。
キャッシュフロー計算書は「どのようにキャッシュが出入りしたか残高がどれほど残っているか」がわかる表です。
▼「財務諸表」についてさらに詳しく
財務諸表は財務三表とは違う?財務諸表の読み方や分析方法を解説
営業利益の使い方
営業利益の構成項目のうち、費用の大きな部分を占めるのが「人件費」です。
人事担当者として、営業利益と人件費の関係とあわせて、営業利益をどのように使えば良いかについて確認してみましょう。
営業利益と人件費の関係
営業利益のマイナス部分である「販売費及び一般管理費」の中でも、大きな比率を占めるのが「人件費」です。
そのため、人件費の見直しを行ったりコントロールをすることで、企業の利益に大きく貢献することができます。
人件費の中で見直すべき項目
人件費の見直しを行う際に、見直すべき3つの項目について確認してみましょう。
人件費の中で見直すべき項目
- 所定時間内賃金
- 所定時間外賃金
- 退職金
所定時間内賃金は、「成果主義型賃金制度」を導入すればベースアップに対するコントロールが可能になります。
所定時間外賃金は、企業が設備投資などを行い効率化することでコントロールが可能になります。
また、成果主義型賃金制度を導入する際は明確な評価制度があると納得感が生まれます。
退職金は、勤続年数に応じた定額制や、基本給に規定の定数を掛けて算出する制度を設けている企業があります。
単なる在籍年数で退職金の支給額を決定するのではなく、会社への貢献度、役割等級、人事評価などで支給額を決定する「ポイント制」など柔軟な制度に切り替えると人件費をコントロールすることができます。
▼「成果主義」についてさらに詳しく
成果主義とは?メリットとデメリットや能力主義との違いをわかりやすく解説
▼「役割等級」についてさらに詳しく
役割等級とはどんな制度?メリットとデメリットや制度の作り方と事例を解説
▼「人事評価」についてさらに詳しく
人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介
営業利益の中でも多くのウェイトを占める人件費のコントロールには「人事評価」の設計や見直しが必要です。人事評価設計に役立つマニュアルを確認してみましょう。
⇒「ゼロから始める人事評価 資料3点セット」をタウンロード
売上高営業利益率は賞与原資にも
これまで賞与は、基本給に対して一律何ヶ月分などで支給を決める「給与連動型」が一般的でしたが、現在は業績に応じて賞与総額を決める「業績連動型」が主流となっています。
配分する賞与原資が決まったら、人事評価制度に基づいた算出を行うことで、従業員エンゲージメントの向上につながります。
▼「従業員エンゲージメント」についてさらに詳しく
従業員エンゲージメントとは?向上施策・事例も紹介
従業員エンゲージメントを高める重要なポイント
営業利益の見直しのための「人事評価システム」の活用
営業利益の大きなウエイトを占める人件費をコントロールするためには、人件費などの賃金制度の見直しが必要かもしれません。
人件費の見直しには「人事制度」の見直しや設計が必要になります。
改めて自社の「人事制度」について考えてみても良いかもしれません。
ゼロから始める人事評価資料3点セット

また、複雑で手間の掛かる人事評価の設計や運用は「人事評価システム」を導入することで、工数削減をしつつ効果的に実施する事が可能になります。
「HRBrain人事評価」では人事評価プロセスの見える化によって「評価の納得度の向上」を促進します。
人事評価コメントやフィードバック面談の履歴などのデータをクラウド上で管理することで、評価プロセスのブラックボックス化や、評価のバラつきなどを防ぐことが可能になります。
また、目標設定や目標に対しての進捗管理、従業員のスキルデータや育成記録なども、一元管理できるため、人事評価プロセスの透明化と合わせて、従業員の成長記録の蓄積も可能になります。
HRBrain人事評価の特徴
制度や目的に合わせたテンプレートが豊富
OKR、MBOなどの「評価テンプレート」や、1on1やフィードバックなどに使用する「面談シート」が充実しています。
企業ごとのプロセスに合わせて承認フローや項目を自由に設定
評価シートやワークフローのカスタマイズが可能なため、評価制度の変更にも柔軟に対応す
ることができます。
評価の集計や調整もシステム上で完結
部署別など任意の項目で集計が可能で、評価結果の調整もシステム上で完結できます。