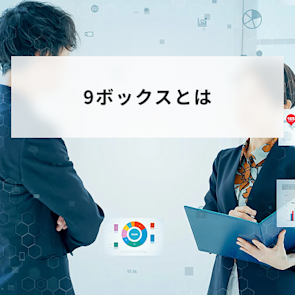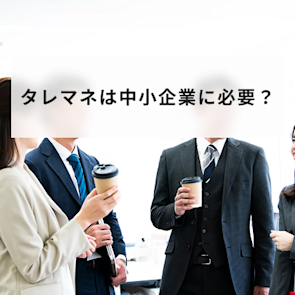フィードバック面談とは?マイナス評価の部下への伝え方も解説!
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- フィードバック面談とは
- フィードバック面談のポイント
- 事前準備をする
- 一方的に話をしない
- フィードバック面談の効果
- モチベーションが上がる
- パフォーマンスが上がる
- 評価への納得感が高まる
- コミュニケーションが取れる
- フィードバック面談の流れ
- 事前準備
- アイスブレイク
- 部下に自己評価をしてもらう
- 人事評価の結果を伝える
- 課題の解決について話し合う
- フィードバック面談で「マイナス評価」を伝える際のポイント
- 事実を根拠にする
- 成長のためであることを伝える
- 行動に対する改善を求める
- フィードバック面談で「納得度」の高い人事評価へ
- フィードバック面談の記録や人事評価を一元管理
フィードバック面談とは、人事評価において、上司から部下に評価結果を伝え、課題について話し合う面談のことを指します。
フィードバック面談で、人事評価の根拠を明確に示せることは、評価に対しての「納得度」を高めるために欠かせないことです。
この記事では、フィードバック面談の意味と実施する際のポイントについて解説します。
納得度の高い評価とは?
フィードバック面談とは
人事評価におけるフィードバック面談とは、上司から部下に人事評価の結果を伝え、課題について話し合う面談のことを指します。
フィードバック面談の目的は、評価に対する納得感を高め、部下の成長を促すことです。
株式会社O:(オー)が行った「上司・部下の評価コミュニケーションの実態調査」によれば、フィードバック面談を実施したグループでは、73%が人事評価に納得していると回答した一方で、フィードバック面談を実施しなかったグループでは、納得しているという回答は56%にとどまりました。
この結果から、 フィードバック面談の実施と人事評価の納得度には一定の相関性があると考えられます。
株式会社O:(オー) 上司・部下の評価コミュニケーションの実態調査
▼「納得度の高い人事評価」について解説
納得度の高い評価とは?目指すべき状態やアクションについて
フィードバック面談のポイント
フィードバック面談を実施する際に、上司側が気をつけるべきポイントについて確認してみましょう。
フィードバック面談のポイント
事前準備をする
一方的に話しをしない
事前準備をする
フィードバック面談の前に、事前準備は必ず行いましょう。
評価結果や課題に対する根拠、課題へのアドバイスについて事前に考えておく必要があります。
曖昧な根拠やアドバイスしか示すことができない場合、部下からの信頼を損なったり、評価への納得感を下げてしまったりする恐れがあります。
また、面談の冒頭では雑談をして場を和らげておくと、その後の話をスムーズに進めることができます。予め雑談の話題についても考えておきましょう。
一方的に話をしない
結果や課題を上司から部下へ一方的に話すのではなく、必ず部下からの意見も聞くようにします。
その場合、部下の意見を頭ごなしに否定するのではなく、傾聴する姿勢を忘れないようにしましょう。
一方的になってしまうと、評価を押し付けられたと感じ、納得感が得られにくくなる恐れがあります。
▼「1on1ミーティング」のポイントについてさらに詳しく
1on1とは? 従来の面談との違いや効果を高めるコツ
1on1ミーティング入門書
フィードバック面談の効果
フィードバック面談は、時間と労力を必要としますが、それに見合う効果を発揮します。
フィードバック面談の効果について確認してみましょう。
フィードバック面談の効果
モチベーションが上がる
パフォーマンスが上がる
評価への納得感が高まる
コミュニケーションが取れる
モチベーションが上がる
フィードバック面談では、プラス評価を上司から直接伝えてもらえる場になるため、部下のモチベーションアップが期待できます。
マイナス評価となった場合でも、課題についてきちんと話し合うことで目標が明確になり、次のステップへのモチベーションにつながります。
パフォーマンスが上がる
フィードバック面談は、上司と部下の双方で、部下の課題や今後の業務に関しての希望について擦り合わせる場となります。
そのため、部下本人が課題を認識できることはもちろん、上司側が部下の成長を支援する策について考えることもできます。
本人の意識が高まるだけでなく、上司から成長のための協力も得やすくなるため、パフォーマンスの向上が期待できます。
評価への納得感が高まる
人事評価は、紙に書かれた評価結果を渡されるだけでは、評価された部分がどこか、課題はどこか、ということを具体的に知る機会がなく、納得感が得られにくくなります。
フィードバック面談を行うことで、評価への具体的な根拠を上司から直接伝えてもらうことができるため、評価への納得感が高まることにつながります。
コミュニケーションが取れる
上司と部下の間でコミュニケーションは日々行われるべきものではありますが、フィードバック面談の機会を設けることで、上司と部下の双方で、現状把握や課題の整理などについてじっくり話し合う機会が得られます。
また、部下の今後のキャリアについて話し合う場にもなり、日常では難しい深いコミュニケーションを取ることができます。
フィードバック面談の流れ
フィードバック面談はどのような流れで行うのが効果的なのでしょうか。
効果的なフィードバック面談の流れをご紹介します。
フィードバック面談の流れ
事前準備
アイスブレイク
部下に自己評価をしてもらう
人事評価の結果を伝える
課題の解決について話し合う
事前準備
面談を行う部下の評価を確認し、その結果の根拠、今後の課題を考えます。
また、質問がありそうな内容を想定し、それに対する回答も準備しておくとスムーズです。
そして、アイスブレイクのための雑談についても考えておきましょう。
アイスブレイク
フィードバック面談では、部下が緊張している場合があります。
緊張をほぐし、円滑なコミュニケーションが取れるようにするため、面談の冒頭でアイスブレイクを行うことがおすすめです。
季節や天気、趣味の話などの雑談で場をなごませましょう。
また、アイスブレイクが長すぎて本題を話す時間が足りなくならないように注意することも必要です。
部下に自己評価をしてもらう
アイスブレイクの後、まずは、部下から自身の自己評価とその理由について説明してもらいます。
このとき、傾聴の姿勢を大切にし、話の途中で否定や反論することは避けましょう。
否定や反論をしてしまうと、部下からの本音が引き出しにくくなってしまう恐れがあります。
また、うなずく、あいづちを入れる、メモをとるなど関心を持って聞いていることを態度で示し、部下が話しやすい雰囲気を作りましょう。
人事評価の結果を伝える
部下の自己評価が終わったら、人事評価結果を伝えます。
自己評価とのギャップがあった場合、その根拠を詳しく説明しましょう。
このギャップを丁寧に埋めることが評価への納得感につながります。
また、部下の意見も聞き、不満を解消することも大切です。
頭ごなしに否定するのではなく、一度部下の意見を受け止めることを心がけましょう。
課題の解決について話し合う
評価結果から浮かび上がった課題について話し合いましょう。
上司から一方的に解決策を押し付けず、部下が自分自身で解決策や目標について考えられるよう誘導できると良いでしょう。
このとき、本人のキャリアプランについても確認し、それに沿った目標を設定できるようにします。
面談の最後には、今後への期待を伝え、部下のモチベーションを喚起できるようにしましょう。
フィードバック面談で「マイナス評価」を伝える際のポイント
人事評価のフィードバック面談で、部下に良い評価を伝える場合は簡単ですが、マイナス評価を伝える場合は、なかなか伝えにくいものです。
マイナス評価を伝える際のポイントについて確認してみましょう。
マイナス評価を伝える際のポイント
事実を根拠にする
成長のためであることを伝える
行動に対する改善を求める
事実を根拠にする
実際に起こったことなどの事実を根拠に評価していることを説明します。
いつ頃、どこで、どのようなことがあった、というように、できるだけ具体的なことを伝えられるようにしましょう。
そのためには、日頃から部下のパフォーマンスをしっかり把握し、記録しておくことが大切です。
成長のためであることを伝える
本人の成長のためのアドバイスであることを強調します。
上司自身、過去に同じようにアドバイスを受け成長したことがある場合は、その経験を伝えます。
そうすることで、アドバイスから成長できることを理解してもらいましょう。
また、改善することによってどのような成長が得られるのかを具体的に示すことも効果的です。
行動に対する改善を求める
性格について指摘するような発言は避け、あくまでも行動に対して改善を求めるようにしましょう。
性格を変えることは簡単ではなく、性格の指摘には抵抗を感じることがあります。
行動の改善であれば、従業員自身も受け入れやすく対応しやすいと言えます。
フィードバック面談で「納得度」の高い人事評価へ
人事評価に対する納得度は多くの企業の人事が抱えている問題のひとつです。
評価への納得度が低いと、従業員エンゲージメントの低下を招いてしまいます。
また、評価の納得度について、人事が課題として認識していても、経営層は重視していないケースがあります。
評価の納得度は企業全体の生産性にも関わるため、人事だけでなく経営層も着目すべき観点です。
上司から部下への「フィードバック面談」を適切に行うことは、人事評価に対する納得度が高まる理由の一つです。
納得度の高い人事評価を目指すためにすべきことについて解説します。
納得度の高い評価とは?目指すべき状態やアクションについて

この資料で分かること
評価の納得度について目指すべき状態
評価の納得度が下がる原因
納得度改善アクション
評価の納得度を向上させた具体的な成功例
HRBrainのプロダクトラインナップ
フィードバック面談の記録や人事評価を一元管理
人事評価において、フィードバック面談で、評価の根拠を明確に示せることは重要なポイントになります。
「HRBrain 人事評価」は人材管理と人事評価を確かな成長につなげる「人事評価クラウド」です。
人事評価のプロセスや面談の記録など、評価の根拠を、クラウド上にしっかりと残すことができます。
「HRBrain 人事評価」の特徴
「膨大な業務」をクラウドで効率化
人事評価シートの作成から、催促、集計までをワンストップで効率化。
従業員の評価入力もスムーズに行えるため、従業員の工数も大幅に削減します。
評価基準やプロセスの見える化で「評価納得度を向上」
目標、面談、評価のデータを一元管理し、ブラックボックス化しがちな評価基準やプロセスを見える化します。
評価に関するデータを一元管理することで、評価納得度の向上を実現します。
蓄積した人材データの活用から分析までを実現
蓄積されたデータをもとに、離職防止や活躍人材の発掘も可能です。
評価の甘辛調整や離職防止や人事評価だけでなく、タレントマネジメントまでを実現できます。
「HRBrain 人事評価」について詳しく知りたい方はこちら
「HRBrain 人事評価」について資料請求したい方はこちら
▼「フィードバック面談」関連記事
360度評価(多面評価)とは?メリットとデメリットや評価項目とフィードバック方法を解説