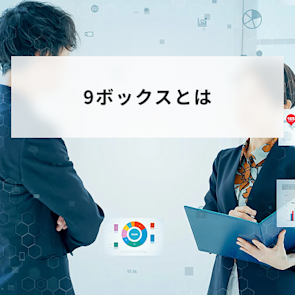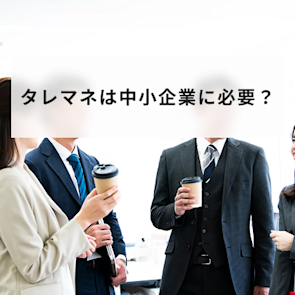働きがい改革とは?働き方改革との違いや具体的取り組みも解説
組織状態の把握から分析・課題抽出までワンストップで実現
- 働きがい改革とは?働き方改革との違いを解説
- 働きがい改革が必要とされる背景
- 働きがい改革と働き方改革の違い
- 働きがい改革で期待できる3つの効果
- 企業の生産性や業績が向上する
- 従業員の心理的安全性や満足度が高まる
- 優秀な人材の定着・獲得につながる
- 働きがいを構成する5つの要素
- 会社に対する信用
- 公正な対応
- 仲間との連帯感
- 従業員への尊重
- 仕事への誇り
- 働きがい改革の具体的な取り組み
- 評価制度の見直しを行う
- 柔軟な働き方を採用する
- 適性に合わせた人材配置を行う
- 働きがい改革を成功させた企業事例
- 働きがいのある組織づくりには「HRBrain 組織診断サーベイ」を活用しよう
働きがい改革は、従業員が仕事に誇りや意味を感じられるようにする取り組みです。
従来の「働き方改革」では、残業削減や柔軟な働き方の推進など、制度面の改善が中心でした。しかし、それだけでは従業員の満足度や定着率は十分に高まりません。そこで注目されているのが「働きがい改革」です。
本記事では、働きがい改革の定義や必要とされる背景、そして働き方改革との違いをわかりやすく解説します。
働きがい改革とは?働き方改革との違いを解説
働きがい改革とは、従業員が仕事に誇りや意義、やりがいを感じられるよう、組織全体で制度や環境を根本的に見直す取り組みを指します。
具体的な施策としては、誰もが納得できる公正な評価制度を導入して昇進や報酬の基準を明確にすることや、社内公募やジョブクラフティングによって個人の強みを活かせる役割を担えるようにすることが挙げられます。
近年、多くの企業が働きがい改革に注目していますが、従来の働き方改革と混同されることも少なくありません。より効果的な施策を実行するために、以降では、働きがい改革が必要とされる背景やそれぞれの具体的な違いを解説します。
【関連コンテンツ】
働きがい改革が必要とされる背景
働きがい改革が重要視される背景には、労働市場の変化や多様な価値観の広がり、優秀な人材の獲得競争の激化があります。
従来は、人材定着には給与や雇用の安定が重視されていましたが、近年は「やりがい」や「自己成長の機会」を重視する傾向が強まっています。
たとえば、透明性のない評価制度や心理的安全性の欠如は、離職やモチベーション低下を招く要因です。そのため、企業は優秀な人材を確保し、定着させるために、従業員が長期的に働きたいと思える魅力的な職場の創出に迫られています。
さらに、人的資本開示の義務化で離職率や育成投資などを外部に示すことが求められていることにより、働きがい改革は企業が競争力を維持するための必須条件となっているのです。
働きがい改革と働き方改革の違い
働き方改革と働きがい改革の違いは、アプローチする領域と目的にあります。
働き方改革は、労働時間の短縮やテレワーク導入などの、働き方の改善に焦点を当てています。一方、働きがい改革は、仕事に対する意味付けや成長機会の提供など、働く人の内面的な満足感の向上が重要です。
たとえば、働き方改革で残業が減っても、評価基準が不透明なままでは従業員の納得感は高まりません。働き方改革を導入したうえで、働きがい改革で目標や役割を明確にすることで、従業員は主体的に働く姿勢を取りやすくなります。
このように両者は相互に補完し合う関係にあるため、働き方改革で環境を整え、働きがい改革で意欲を高めることで、企業は持続的な成長を実現できるのです。
働きがい改革で期待できる3つの効果
働きがい改革は、従業員と企業双方に多くのメリットをもたらします。具体的な効果として、以下の3点が挙げられます。
企業の生産性や業績が向上する
従業員の心理的安全性や満足度が高まる
優秀な人材の定着・獲得につながる
単なる制度変更ではなく、従業員のやりがいに直結する取り組みを行うことで、企業は持続的に競争力を高められるでしょう。
企業の生産性や業績が向上する
働きがい改革は、生産性や業績の向上に直結します。従業員が自分の役割に納得し、成長実感を得られる職場では、主体的に業務へ取り組む姿勢が強まるからです。
たとえば、社内公募制度や自分の仕事内容を見直すジョブクラフティングを導入し、個人の強みと業務内容を一致させます。その結果、スキルを発揮しやすくなり、無駄な人員配置の削減が期待できます。
また、評価基準を公開して成果と報酬の関係を明確にすれば、努力が正当に評価されると感じることでモチベーションの維持が可能です。
従業員の心理的安全性や満足度が高まる
働きがい改革は、従業員の心理的安全性や満足度の向上にもつながります。心理的安全性が確保されると、従業員は安心して自分の意見を述べられ、失敗を恐れずに挑戦が可能です。
具体的には、1on1ミーティングを定期的に行い上司と部下が率直に話せる機会をつくる方法があります。上司とオープンに話せる場があることで、従業員は、会社が自分を大切にしてくれていると感じやすくなり、心理的安全性の向上に効果的です。
また、会議で発言しやすいルールを設けると、組織全体で自由なアイデアが出やすくなります。その結果、イノベーションも生まれやすくなり、組織の課題解決スピードも向上します。
【関連コンテンツ】
優秀な人材の定着・獲得につながる
働きがい改革を行うことで、優秀な人材の定着を期待しやすくなります。働きがいを感じている従業員は、企業への愛着や忠誠心が高まり、離職を考える可能性が低くなるためです。
たとえば、透明性の高い評価制度や、キャリアアップの道筋が明確に示されている企業では、従業員は自身の将来像を描きやすく、長期的に働く意欲の高まりが期待できるでしょう。
さらに、社内の雰囲気がよく、従業員が活き活きと働いている姿は、外部からも魅力的に映ります。SNSや口コミサイトを通じて、企業の働きがい改革の取り組みが広く知られるようになると、転職希望者や新卒者にとっての魅力的な選択肢となることで、優秀な人材の採用につながります。
【関連コンテンツ】
働きがいを構成する5つの要素
働きがいはひとつの要素で決まるものではなく、以下のような複数の観点が組み合わさって形づくられます。
会社に対する信用
公正な対応
仲間との連帯感
従業員への尊重
仕事への誇り
これらを満たすことで従業員は安心して働ける環境を感じ、意欲的に業務へ取り組めるでしょう。
会社に対する信用
働きがいの基盤となるのが「会社を信頼できるかどうか」です。
経営状況や将来性に透明性があり、方針や数字が正しく社員に共有されている企業は、従業員に安心感を与えます。
会社に対する信用が高まれば、従業員は将来に不安を感じることなく日々の業務に集中でき、自律的に貢献しようという意欲が向上します。
公正な対応
働きがいを構築する要素として、公正な対応も重要な要素です。どれだけ成果を出しても評価基準が不透明であれば、従業員は不満を抱きやすくなります。
公正な対応とは、評価や報酬、昇進、教育の機会などが、従業員全員に対して公平に与えられている状態のことです。
公正性を担保する具体的施策として、評価・昇格の基準を文書化して全社員に公開する、昇進の際には複数人で評価会議を行うなどの取り組みが効果的です。
このように部門間の不公平感が払拭されることで、従業員は努力が正当に報われると感じ、より主体的に業務に取り組むようになります。
仲間との連帯感
仲間との信頼関係や一体感は、働きがいを高める強力な要素です。孤立した職場では成果が出ても喜びが共有できず、働く意欲は低下する可能性があります。
チームメンバーが互いの成功を喜び、困難な状況では助け合う文化がある職場では、従業員は孤立感を覚えることなく、安心して働けます。
仲間との連帯感を醸成するための具体的な施策として、チームビルディングの機会を設けたり、部署横断のプロジェクトを推進したりすることが効果的です。また、1on1や定期的なミーティングを通じて、困りごとを共有できる文化を育むことも有効です。
仲間との強い結びつきは、チーム全体のパフォーマンスを向上させ、仕事のやりがいを高める重要な要素となります。
従業員への尊重
従業員が尊重されていると感じられる環境に身を置くことは、働きがいの向上に直結します。従業員への尊重とは、一人ひとりの意見やアイデアが真剣に受け止められ、大切に扱われている状態を指します。
たとえば、従業員からの改善提案を積極的に採り入れたり、業務の進め方にある程度の裁量権を与えたりすることで、従業員は「自分は組織に必要とされている」と感じ、仕事への責任感や誇りが高まります。
従業員が尊重されていると感じる環境では、個人の主体性が育まれ、より良いアイデアや創造性が生まれやすくなります。
仕事への誇り
自分の仕事に誇りを持てるかどうかも、働きがいに影響を与えます。仕事への誇りは、自分の仕事が社会や他者にとって価値あるものであると信じ、そのことに喜びや達成感を得られている状態のことです。
たとえば、企業が掲げるミッションやビジョンが明確で、自分の業務がどのように貢献しているのかが理解できると、従業員は仕事に意味を見出します。また、自分の専門性やスキル、成果が正当に評価されたりすることで、仕事への誇りはさらに高まるでしょう。
誇りを醸成するための施策としては、会社のミッションを社員の目標とつなげるストーリーテリングを行い、成果を可視化して顧客からの感謝の声を共有することが効果的です。
仕事への誇りが芽生えることで、自発的にスキルを磨き、より高い成果を目指す姿勢が強まるでしょう。
働きがい改革の具体的な取り組み
働きがい改革を進めるためには、抽象的なスローガンだけではなく、実際の制度や日常業務に落とし込む必要があります。具体的には、以下の方法があります。
評価制度の見直しを行う
柔軟な働き方を採用する
適性に合わせた人材配置を行う
これらを計画的に実践することで、従業員は自身の努力や成長が正しく反映され、安心して挑戦できる職場環境を得られるでしょう。
評価制度の見直しを行う
働きがいを高めるためには、公平で透明性のある評価制度を整えることが効果的です。
評価制度がブラックボックス化していることは、若手やハイパフォーマーの離職要因となりやすく、組織全体のモチベーション低下に直結します。
具体的な見直し施策として、年功序列や曖昧な評価基準から脱却し、個人の成果やスキルを正当に反映する評価制度を設計します。MBO(目標管理制度)やOKR(目標と主要な結果)などを導入したうえで、評価基準を従業員に公開することも透明性を高める有効な方法です。
このような施策を実施することにより、従業員は自身の努力が正当に報われると納得して、意欲的に業務に取り組むようになるでしょう。
【関連コンテンツ】
柔軟な働き方を採用する
働きがいを実感できる環境を整えるためには、従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を導入することが効果的です。従業員が自分に合った働き方を選択できることで、仕事とプライベートのバランスが取りやすくなり、ストレスの軽減につながります。
たとえば、テレワークやフレックスタイム制度を導入することで、育児や介護と仕事を両立しやすくなり、離職の防止が期待できます。また、週4日勤務や短時間勤務など、多様な雇用形態を設けることも有効です。
柔軟な働き方によって従業員は私生活と仕事を両立しやすくなり、心身ともに健康な状態で働けることが結果として生産性の向上につながります。
適性に合わせた人材配置を行う
従業員が自分の強みを発揮できる配置を行うことは、働きがいを向上させる効果的な施策です。従業員が自身の強みを活かせない役割を担うことは、個人のパフォーマンス低下だけでなく、やりがいの喪失と離職リスクの増大を招きます。
適性に合った人材配置により、従業員は自己効力感を高め、成果を出すことで成長意欲が高まる好循環が生まれます。
具体的な施策として、従業員自身が業務内容や人間関係を工夫し、仕事の捉え方を変える手法であるジョブクラフティングや部署異動、職務変更の機会を設ける内部公募制度を導入することが効果的です。
さまざまな制度を活用しながら適性に合った仕事を担うことで、従業員はやりがいを持ち、成果に直結する仕事ができるようになります。
【関連コンテンツ】
働きがい改革を成功させた企業事例
ここでは、働きがい改革を成功させた事例として、驚異的な成長と働きがいの両立を実現させた株式会社Unitoを紹介します。
「暮らしの最適化の追求」をミッションに掲げ、新しい暮らしを開発しているスタートアップ企業である株式会社Unitoは、以下の課題を抱えていました。
従業員のエンゲージメントや働きがいを定性的にしか把握できていない
多様な人材採用のために第三者評価がほしい
同社は、上記の課題を解決するために以下のような3つの柱を整えました。
3つの柱 | 具体的アクション |
|---|---|
人材育成 | ・若手の積極採用 |
コミュニケーションの仕組み | ・社内連絡ツール活用の活性化 |
評価と承認 | ・社内連絡ツールのメッセージの内容での評価 |
上記のような取り組みを行うことで、結果としてGreat Place To Work®の「働きがいのある会社」認定も受けています。
さらに、採用イベントの出展時に「働きがいのある会社」としてアピールすることで、認定前と比較して応募数が約2.3倍に増加した嬉しい効果も得られました。
参考:働きがいのある会社認定取得後、採用応募数が2.3倍増!株式会社Unitoの事例|Great Place To Work®
働きがいのある組織づくりには「HRBrain 組織診断サーベイ」を活用しよう

働きがい改革を効果的に進めるには、感覚的な判断ではなく、データに基づいた組織の現状把握が必要です。
その際に役立つのが「HRBrain 組織診断サーベイ」です。このサービスを導入することで、従業員の働きがいや心理的安全性を定量的に可視化し、改善ポイントを明確にできます。
主な機能は、以下のとおりです。
従業員満足度やエンゲージメントの測定
離職予兆分析やクロス分析などの分析
アクションレポートのような課題の把握・アクションの示唆を提供
上記のようなさまざまな機能を活用することで、評価制度の見直しや配置転換、コミュニケーション施策など具体的な改善策につなげやすくなります。
働きがい改革を単なるスローガンで終わらせず、継続的な取り組みに変えるには、科学的な診断と改善サイクルの運用が実現できる「HRBrain 組織診断サーベイ」を活用してみてください。