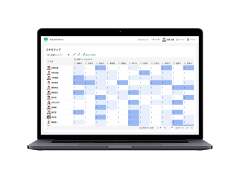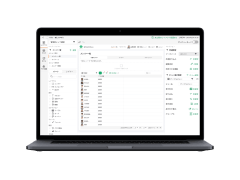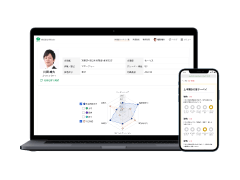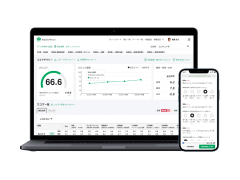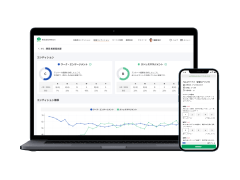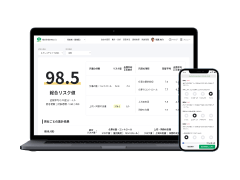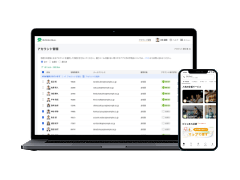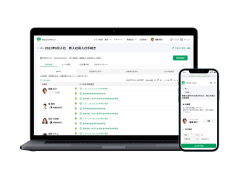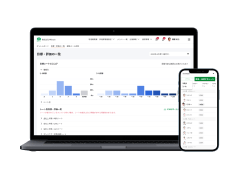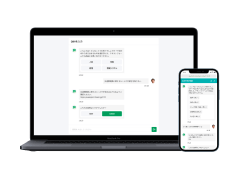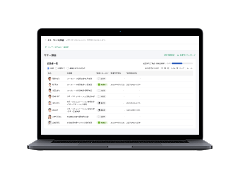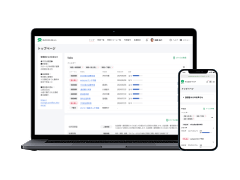7,000名を超える技術者の成長を支える人事戦略。AKKODiSが描く、キャリア形成の未来とは
AKKODiSコンサルティング株式会社 取締役 兼 People Success本部 本部長
奥田 幸江 様
株式会社HRBrain 副社長 CRO
白井 崇顕
- 人材
- 1001名~
- 人事評価や目標管理の運用を効率化したい
- 人材データの分析・活用を行いたい
- 人事制度の見直しをしたい
- 人材データを一元管理したい
- スキル管理を行いたい
- タレントマネジメント
HRBrain導入開始:2023年02月01日
7,000名を超える技術者の成長を支える人事戦略。AKKODiSが描く、キャリア形成の未来とは
世界最大級の人材サービス企業Adecco Groupの一員として、「日本企業を、世界企業へ、現場変革から。」という壮大なビジョンを掲げるAKKODiSコンサルティング株式会社。7,000人以上のエンジニア・コンサルタントを擁し、「人財躍動化」を経営の根幹に据える同社が、さらなる事業成長と人事戦略の進化を目指し、人事評価・タレントマネジメントシステム「HRBrain」を導入しました。すでに精緻な人事制度を運用していた同社が、なぜシステムの刷新を決めたのか。そして、HRBrainの導入がどのような変化をもたらしたのか。人事領域の責任者である奥田様に、同社の先進的な取り組みと未来への展望を深掘りしました。
日本企業を、世界企業へ。実現の鍵は、“現場”にあり
白井:
まずは改めて御社の事業と、掲げられているビジョンについてお聞かせいただけますか。
奥田様:
当社は、現場を熟知したコンサルタントが企業の生産性の向上やAIトランスフォーメーションの実現を支援するテックコンサルティング事業を展開しています。
今年からスタートした5カ年の中期経営計画では、「日本企業を、世界企業へ、現場変革から。」というビジョンを掲げました。ご存知の通り、日本は人口減少という課題に直面し、生産性の向上が大きな課題です。私たちのお客様である日本の企業様と共に世界のマーケットを視野に事業の拡大を目指し、AKKODiSがAdecco Groupの一員として持つグローバルアセットも活用していきたいと考えています。
白井:
その壮大なビジョンを実現する上で、御社ならではの特徴や強みについて教えてください。
奥田様:
特徴としては「現場からの変革」を重視している点です。また、私自身もバックグラウンドはコンサルティングなのですが、当社の強みは、お客様の日常業務、つまり現場に入り込んでいるエンジニアが多く在籍していることです。例えば、お客様の経営層がトップダウンで素晴らしい施策を打ったとしても、それを実行する現場が変わらなければ本当の変革は起きません。だからこそ、私たちがお客様の現場に寄り添い、ボトムアップで変革を支援していく。この「デリバリーモデル」こそが、私たちならではのユニークな立ち位置だと考えています。
白井:
なるほど。会社としてのビジョンそのものも、現場の従業員の方々を巻き込みながらつくられたと伺いました。
奥田様:
そうですね。今回の中期経営計画は、半年ほどかけて現場のエンジニアや管理部門の社員を巻き込んでつくり上げました。外部の経営コンサルタントや経営陣がつくったものではなく、「自分たちも一緒につくったんだ」という当事者意識が生まれることを大切にしたんです。トップクラスのエンジニアが、自分たちの部署の声を拾い上げ、時にはアンケートまで実施してくれました。さらには、お客様にもヒアリングを行い、私たちがどういう存在になりたいかを言語化していきました。ホームページに記載されているビジョンの言葉も、一つひとつ「この表現がいいか、この単語がいいか」と、みんなで議論を重ねて生み出されたものなんです。

エンジニアのキャリアを広げる、「対話」と「可視化」
白井:
「現場」を支えるのは、まさに「人」なんですね。御社の人材育成、特にエンジニアの方々のキャリア支援における考えや、具体的な取り組みについて教えてください。
奥田様:
私たちは人材を最も大切にしており、社内では「人財」という言葉で表現しています。その育成ノウハウをお客様に提供する「アカデミー」という事業があり、試行錯誤して積み上げてきたコンテンツを惜しみなく社外へも提供しています。企業理念として「人財の輩出」も掲げていて、当社で育ったエンジニアがお客様の会社に転籍することも社会貢献の一つだと捉えています。
また、エンジニア自身のキャリアビジョンを描く支援として、「キャリアプランナー制度」を設けています。これはグループ会社であるアデコ株式会社が推進している「ビジョンマッチング」の一環で、エンジニア本人の自発的な「こうなりたい」という気持ちを重視しています。単にお客様からいただく依頼の条件だけでマッチングするのではなく、お客様の部署のビジョンなどもヒアリングし、エンジニアのビジョンとお客様のビジョンを、プランナーが紐解きながらマッチングさせる。まだまだ途上ですが、ここを目指しています。時にはキャリアの提案が受け入れられない場合でも、プランナーが「そこに至るにはまずこれを経験することで、こういう道が開ける」といった対話を重ねながら、キャリア形成をサポートするという理想を目指しています。
白井:
そこまで徹底されているんですね。さらに、そのキャリア形成を具体的にイメージするための仕組み「キャリアマップレインボー」についても、改めてお聞かせいただけますか。
奥田様:
技術分野が多岐にわたる中で、エンジニアがどのようなステップでキャリアを歩めるかを可視化したAKKODiS Japan独自の仕組みですね。実は、グローバルに先駆けて、2011年から日本で本格的に導入したものです。一つのキャリアパスを登るだけでなく、横にスライドしたり斜めに進んだりして、虹(レインボー)のように自分のキャリアの幅を広げられるようになっています。
白井:
日本で生まれたというのは意外でした。具体的にはどのような仕組みなのでしょうか。
奥田様:
「分野」と「職能(スキルレベル)」という2つの軸で構成されています。「分野」はインフラ、ソフトウェア、メカトロニクス、エレクトロニクス、ケミストリーといった幅広い技術領域を網羅し、「職能」は5段階のスキルレベルで定義されています。エンジニアはこのマップを参考にキャリアプランナーやチームリーダーと対話し、キャリアを形成していきます。また、「職能」は等級になっており、社内の評価制度や給与制度にもしっかりと紐づいている、非常につくり込まれたものなんです。
白井:
とてもユニークな仕組みですね。グローバルでも、今まさにキャリアパスを提示する動きが活発化していると伺いました。

奥田様:
そうですね。世界的なエンジニア不足を背景に、グローバル全体でも「キャリアパスを明確に示し、教育研修と結びつけよう」という動きが昨年あたりから始まりました。グローバル全体で同じレベルでエンジニアのスキルを把握し、適財適所の配置を目指そうとしています。そのため、エンジニア一人ひとりの希望やこれまでの経験といったデータと、案件情報をAIでマッチングするシステムの導入を考えています。
日本ではすでにキャリアマップレインボーを運用しているので導入しやすい一方で、定着しているがゆえにグローバルで導入しようとしている新しいキャリアパスフレームワークとどう統合していくか、フィット&ギャップを見極めているところです。
決め手は、自分たちで「カスタマイズ」できること
白井:
それほど精緻につくり込まれた人事制度がある中で、今回HRBrainを導入いただくに至った背景や理由についてもお聞かせいただけますか。
奥田様:
2023年4月にジョブ型の導入など新しい人事制度へ移行するタイミングがあり、そこが大きなきっかけでした。これまでは、評価制度の運用をすべてExcelで行っていたのですが、制度を進化させていく上で、より効率的で戦略的な運用ができるシステムが必要だと考えたんです。以前は別のツールで管理していた部分もあったのですが、それも限界に来ており、スコア付けなどはすべてExcelという状況でした。
白井:
なるほど、会社の進化に合わせて、それを支えるプラットフォームも進化させる必要があったんですね。
奥田様:
そうですね。そういった経緯から複数のサービスを検討した結果、HRBrainの導入を決めました。
決め手はいくつかあるのですが、一つは、これまで情報システム部門に頼んでいた評価シートの作成などを、人事部門が自ら柔軟にカスタマイズできる点です。評価点数の計算なども、人事が考えた通りに関数を組んで実装できる。このカスタマイズ性の高さは大きな利点でした。
それに加え、部門ごとにアクセス権限を細かく設定でき、上長は自分の部下の情報しか見られない、といったセキュリティを担保できることも重要でした。また、グループ会社のアデコ社が先行導入していたため、グループ内で転籍した従業員が同じインターフェースで違和感なく使える、という点も非常に重要な要素でしたね。
工数の大幅な削減と、数字で語る「戦略人事」の実現
白井:
実際にHRBrainを導入されて、どのような効果や変化を感じていらっしゃいますか。
奥田様:
最も分かりやすい効果は、工数の大幅な削減です。以前は、評価の時期になると部門ごとにExcelシートを切り出して配布し、それをまた回収して一つに合わせる、という膨大な作業が発生していました。今はシステム上で各々が完結してくれるので、人事部門は全体を見るだけでよくなりました。最終評価の調整や承認もシステム上で一気通貫できるので、人事の工数は圧倒的に削減されましたね。
白井:
それは大きな変化ですね。工数削減によって生まれた時間で、他の業務にも良い影響はあったのでしょうか。
奥田様:
人事の役割がより「戦略的」になったと感じます。2023年からHRBP(事業部担当人事)制を導入したのですが、タレントレビューの運用が大きく変わりました。事前にマネージャーがHRBrainに情報を入力し、会議ではそのデータを見ながら人財の分布を確認するので、その場で評価を更新したり、育成計画のコメントを書き込んだりできます。
白井:
なるほど、即座に反映できるんですね。
奥田様:
そうなんです。すべてがシステム上に記録として残るので、その後のアクションをトラッキングできますし、経営会議への報告もデータを元に行えるようになりました。まさに「数字で語れる人事」が実現し、人事の本来あるべき姿に近づいたと感じています。今では評価やタレントレビューに関しては、システム情報を正として議論が出来るようになったと感じています。

オープンな企業文化が拓く、AI時代の人事戦略
白井:
素晴らしい成果ですね。そうした先進的な人事制度を支えている、御社の企業文化についても少しお聞かせいただけますか。
奥田様:
もともと当社は経営との距離が非常に近い会社だったのですが、一時期、急激な人員増に伴ってその文化が弱まり、エンゲージメントや業績にも影響したことがありました。そういった過去の反省から、「経営セッション」という経営陣と従業員が直接対話する場を月1〜2回というハイペースで昨年から復活させました。経営陣が自ら地方にも足を運び、一人ひとりと向き合うようなコミュニケーションを大切にしています。また、社長に直接チャットで質問が来ることも日常的で、役職に関わらず対話できる文化があります。
白井:
すごくオープンな企業文化が根付いているんですね。
奥田様:
はい。こうした風通しの良さは、多様な人財が活躍できるDE&Iの推進にもつながっています。すべての従業員が働きやすい環境を目指した結果、例えば男性の育休取得率が70%以上となっています。取得期間も2ヶ月が最も多く、最長1年間取得するなど、お互いを支え合う文化が根付いていますね。社内公募制度も非常に活発で、エンジニアだった従業員が、この制度を使って人事に異動した事例もあります。
白井:
エンジニアから人事へ、というキャリア形成は非常に珍しいですよね。これまでのお話から、なぜ従業員の皆様が自律的にキャリアを築けるのか、その背景がよくわかりました。
最後に、今後の展望についてお伺いします。新しいテクノロジーを、今後の人材活用やビジネスにどう活かしていきたいとお考えですか。
奥田様:
将来的には、従業員の入社から活躍、そして退職まで一連の体験、いわゆる「エンプロイージャーニー」のデータをAIなどで分析し、より高度な人財戦略につなげていきたいと考えています。例えば、活躍している従業員が持つ能力やコンピテンシーを可視化できれば、採用や育成に反映できますよね。
私たちは、マネジャーなどの管理職には手続きや分析といった「作業」ではなく、部下との対話など「人間にしかできないこと」に時間を使ってほしいと考えています。先日も、あるエンジニアが「上司との面談の前に、AIを相手に予行練習がしたい」と提案してくれました。各種手続きや分析はAIに任せ、人間は対話に集中する。その世界観を実現するためのプラットフォームとして、HRBrainにはこれからも大いに期待しています。従業員が自律的に学び、成長を振り返り、納得感のあるキャリアを歩んでいく。そんな「ラーニングカルチャー」を組織に根付かせるための仕組みづくりを、HRBrainと共に推進していきたいですね。
白井:
ありがとうございます。AI領域は我々も非常に強化している分野ですので、ご期待に沿えるよう尽力してまいります。本日は誠にありがとうございました。

※掲載内容は、取材当時の2025年7月時点のものです。