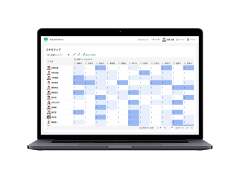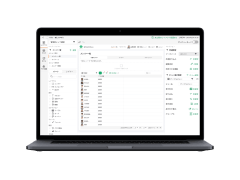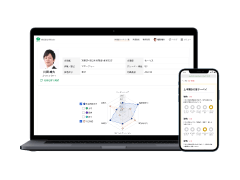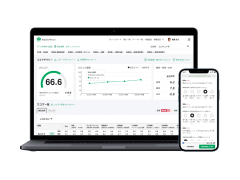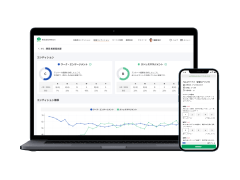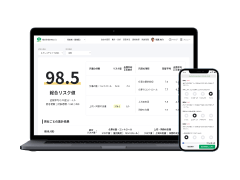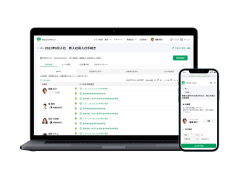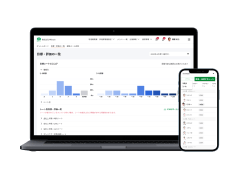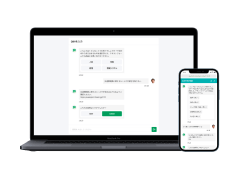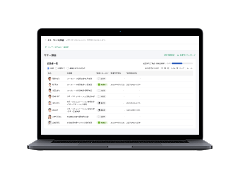離職率が大きく改善! 従業員の「本音」と向き合うDOWAの組織改善の舞台裏とは
DOWAホールディングス株式会社 人事部長 兼 人材開発室長
金子 将司 様
DOWAホールディングス株式会社 人事部 課長
友野 裕 様
- 製造・メーカー
- 1001名~
- 人的資本開示への準備がしたい
- 組織の課題把握・分析がしたい
- 従業員エンゲージメントを向上させたい
- 組織診断サーベイ
HRBrain導入開始:2022年10月01日
離職率が大きく改善! 従業員の「本音」と向き合うDOWAの組織改善の舞台裏とは
- 課題背景
- 上司に「本音」が言えずに従業員が問題を抱え込み、突然の退職に至るケースがあった。
- 事業体が多岐にわたるため、他部署の仕事が見えず、従業員が自らのキャリアを主体的に描きにくかった。
- 人事制度などの必要な情報が社内に散らばり、従業員が知りたい情報にたどり着きにくい状態だった。
- 打ち手
- 「期待と実感のギャップ」で本音を可視化し、他の人事制度も効果的に活用することで、従業員の表に出ない感情や課題を的確に把握。
- 自律的な学びを促す「教育プラットフォーム」 を導入し、主体的なキャリア形成を力強く後押し。
- 社内制度や情報を一元管理するポータルサイトを新設し、必要な情報を見つけやすくした。
- 効果
- 「本音と向き合う文化」が醸成され、離職率が改善傾向に転じた。
- 従業員が主体的に学んでキャリア形成し、プロとして成長できる文化の土台ができた。
- 具体的な施策が従業員のポジティブな体験につながり、「会社制度」に関するスコアが明確に改善した。
従業員の「直接言いづらい本音」をどう掴むか
Q. まずは、「DOWAホールディングス」の事業内容と、直近の経営状況についてお聞かせください。
金子様:
当社は、環境・リサイクル、製錬、電子材料、金属加工、熱処理という5つの事業を柱とする、資源循環型の総合素材メーカーです。創業時は、非鉄金属の地金を作る「鉱山・製錬」から始まり、それを加工して自動車や電子機器に使われる製品を作る「金属加工」や「電子材料」、金属の強度を高める「熱処理」へと事業を広げてきました。
当社の最大の特徴は、お客様が使用し終えた製品を回収し、有害物質を処理しながら、再び資源として生まれ変わらせる「環境・リサイクル」事業です。当社の事業そのものが「資源循環」を形成しており、ユニークなビジネスモデルを構築しています。
足元の業績は、環境・リサイクル事業や製錬事業を中心に堅調に推移しています。その一方で、為替や金属価格の影響を受けやすく、また、近年では脱炭素の動きや、エネルギー価格の高騰、地政学リスクの影響等、事業環境は絶えず変化しています。こうした中、世界的な潮流で日本政府も推進する「サーキュラーエコノミー(循環経済)」への転換は、当社にとって大きなチャンスだと捉えており、この時代の流れを受けつつ「循環のクオリティ」をさらに高めていくことが重要だと考えています。
Q. なぜ、従業員エンゲージメントの向上に取り組もうと考えられたのでしょうか?
金子様:
「人的資本」が重要視される現代において、当社でも人的資本の強化をサステナビリティマネジメントのマテリアリティの一つとして取り組んでいます。私たちは、取り組みの大きな柱として「勝ち抜ける人材層の拡充」「働きたいと思う組織づくり」「社内外に開かれた会社」という3つのビジョンを掲げています。
まず「勝ち抜ける人材層の拡充」ですが、これは主に採用と育成です。当社に興味を持ってくれる学生や求職者に当社のことをより魅力的に思っていただけるように努力するとともに、入社いただけた方には、自ら学ぶ文化の中でプロフェッショナルとして成長するための教育基盤も提供しています。また若手が成長し、キャリアをイメージできるようにOJTにも注力しています。マネージャー層がしっかりと若手を見ながら、育成に取り組んでいます。
二つ目の「働きたいと思う組織づくり」では、従業員の定着を重要視しています。労働環境の整備や、ダイバーシティの推進といった取り組みをすることで皆が安心して働ける職場を目指しています。従業員エンゲージメントの向上は、この「働きたいと思う組織づくり」の中心に位置づけられています。
三つ目の「社内外に開かれた会社」は情報のフラットさ、オープンさを意味しています。戦略や方針を、従業員一人ひとりに理解してもらうことが重要なのはもちろんのこと、社外に対しては、株主の方々はもちろん求職者の方やパートナー、お取引先様といった全ステークホルダーに向け、当社のことをより理解していただけるように情報発信を意識しています。
このように、「勝ち抜ける人材層の拡充」「働きたいと思う組織づくり」、そして「社内外に開かれた会社」であること。これら3つの大きな目標を達成するためには、まずその基盤となる従業員が今、何を思い、何を感じているのか、その「本音」を客観的に把握することが、すべての出発点になると考えました。

Q.生じている組織課題について教えて下さい。
金子様:
当社には事業体が複数あることもあり、組織課題は散在しています。中でも課題に感じていることは、「心理的安全性」と「びっくり退職」です。
友野様:
当社では以前から、従業員の異動希望や将来のキャリアを把握する目的で、自己申告制度を運用してきましたが、その申告内容を活かした上司・部下間でのコミュニケーションが十分に取られていないことが課題でした。そこで、上司と部下のコミュニケーションを促すことを目的として、2018年に自己申告制度の内容を大幅に見直し、申告内容も結婚や育児、介護といった私生活の項目も加えて、より広く従業員の状況を把握しようと努めてきました。さらに、面談も義務化する傍らで、国内の主要拠点に人事部の人間が直接出向いて説明会を実施するなど、制度の浸透を図ってきました。
ただ、やはり課題になるのは、「上司に直接言いづらい側面がある」という点。従業員の本音、特にキャリアに関する悩みや、職場に対するデリケートな意見は、直属の上司が間に入る仕組みではどうしても表面化しにくいものです。そのため、従業員が溜め込んでしまい、最終的に突然の退職に至るという課題がありました。
この「表面化しない課題」を対処するためには、従来の仕組みでは限界を感じていました。
サーベイを起点にした具体的なアクションで、明確にスコアが改善。
Q. なぜ、数あるサービスの中からHRBrainの組織診断サーベイ「EX Intelligence」を選ばれたのでしょうか。
友野様:
「上司に直接言いづらい本音を拾い上げる」という目的が明確だったため、サーベイの仕組みは非常に重要視しました。その中でHRBrainを選んだ最大の決め手は、従業員の「期待」と「実感」のギャップを可視化できる点です。 単に満足度(実感)を測るだけでは、スコアの良し悪ししか分かりません。
しかし、従業員が会社に対して「何を期待しているのか」を同時に把握し、そのギャップを見ることで、従業員の表に出ない感情や、本当に解決すべき課題の優先順位が見えてくると考えました。スコアの背景にあるものまで理解することで、離職率を低減させる以上の、本質的な組織改善を期待しました。
Q. EX Intelligenceを導入してから、包括的にどのような取り組みをされたのか教えてください。
友野様:
サーベイの結果を補完するため、従業員一人ひとりの「本音」を把握する「従業員ヒアリング」も始めました。このヒアリングでは、職場の上司や同僚との協働関係や、将来のキャリア等に関する「本音」、「不安」や「不満」という深層の思いが顕在化されるよう、まず上司への開示希望を確認します。その上で、サーベイ結果と合わせて必要に応じ従業員と個別に面談することで、突然の退職に対する包括的な取り組みを進めました。
また、サーベイ全体の傾向を見ると、特にスコアが低かったのは「会社制度」と「キャリア」に関する項目でした。離職率低減を第一の課題と捉えていましたが、それ以外に従業員が感じている課題も抽出できたことで、従業員全体のエンゲージメント向上に向けた現状把握を進めることができました。
「会社制度」については、各種制度に関する情報が社内のあちこちに散らばっていて分かりにくい、という声が多くあったので、人事関連の制度や情報を一元的に閲覧できる社内ポータルを新設しました。その中で、福利厚生なども含め、必要な情報に誰でも簡単にアクセスできる環境を整えました。
「キャリア」については、将来のキャリアが描きにくいという課題が見えてきたため、2025年度にキャリア教育を実施予定です。従業員一人ひとりがキャリアを考える機会や、自分のいる部署以外にも社内で様々な経験が積めることを知ってもらえるような機会を設け、情報発信を増やします。また、従業員の自律的な学びを促すために、上司の承認なしで自由に研修を受けられる教育プラットフォームを昨年10月より導入しました。これらを活用して従業員が視野を広げ、自ら能力開発してもらえるように取り組みます。
今後は、サーベイで見えてきたキャリアに関する課題への対応と、この教育プラットフォームを連携させ、従業員一人ひとりが自分のキャリアを考え、主体的に学べるような支援をさらに強化していきたいと考えています。

Q. こうした取り組みを通じて、どのような成果がありましたか?
友野様:
具体的な成果として、社内ポータルサイトを新設した翌年のサーベイでは、「会社制度」に関するスコアが明確に改善しました。「制度が分かりやすくてありがたい」という声も実際に聞こえてきており、情報へのアクセシビリティを高めるという施策が、従業員のポジティブな体験につながったことをデータで確認できました。
また、離職率も改善傾向にあります。具体的には2022年度の3%強から、2024年度には2%半ばまで、1%弱程改善しています。また、「3年後離職率ゼロ」を目標として意識的に取り組んできた結果、2024年度入社の社員については、現時点では離職ゼロという状況を作り出せております。従業員の声に耳を傾ける姿勢が、何らかの良い影響を与えているのかもしれません。
サーベイを通して今まで見えなかった従業員の「本音」と向き合うきっかけができました。この本音にこそ、組織改善のヒントがあるんだと実感しています。
サーベイを使いこなし、グループ全体で組織改善を推進できる会社へ。
Q. 今後の展望として、HRBrainのサービスをどのように活用していきたいとお考えですか。
金子様:
冒頭でもお伝えした通り、当社グループでは、「勝ち抜ける人材層の拡充」「働きたいと思う組織づくり」「社内外に開かれた会社」という3つのビジョンを掲げており、サーベイの活用は、この3つすべてに関わってきます。
目指すべきは、従業員が胸を張って「この会社でずっと働きたい」と言えるような状態です。そのために、サーベイの活用方法そのものを進化させていきたいと思います。
これまでは、私たち担当者が課題を見つけて施策を打つという流れでしたが、今後は、サーベイを「うまくツールとして使う」ことも考えています。
サーベイの結果単体での活用のみを目的にするのではなく、あくまでツールとして使いこなし、様々な人事諸制度と組み合わせて施策展開することで改善に繋げていければ良いと考えています。その結果として「組織が本当に良くなった」と全員が実感できる状態が理想ですね。また、個別の課題も担当部署任せにならないよう、今後は人事部や事業体の人事担当部署とも連携し、グループ全体としてより大きな流れで組織改善に取り組んでいきたいと思います。

※掲載内容は、取材当時の2025年6月時点のものです。