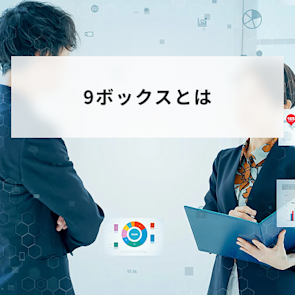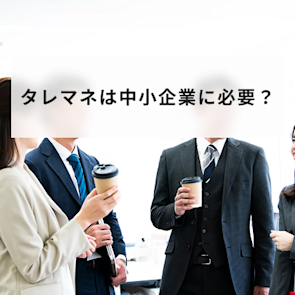コンピテンシー評価とは?項目例やシートの書き方、導入手順も詳しく解説
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- コンピテンシー評価とは
- コンピテンシー評価と類似する評価制度の違い
- 職能資格制度(能力評価)との違い
- バリュー評価との違い
- パフォーマンス評価との違い
- MBO(目標管理制度)との違い
- コンピテンシー評価を導入する4つのメリット
- 評価への納得感が高まりやすい
- 企業のビジョンが浸透しやすくなる
- 人材育成の方向性が明確になる
- 評価者の負担を軽減できる
- コンピテンシー評価で注意したい3つのデメリット
- 評価モデルの設計に時間がかかる
- 環境変化への対応が難しい場合がある
- 形骸化のリスクがある
- コンピテンシー評価の導入手順と設計ステップ
- 1.ハイパフォーマーやモデル対象へのヒアリング・分析
- 2.コンピテンシー項目の検討・策定
- 3.コンピテンシーをもとにして行動モデルを作成
- 4.企業ビジョンや経営戦略とマッチした評価項目を選定
- 5.運用・評価・改善を繰り返す
- 【職種別】コンピテンシー評価シートの評価項目の具体例
- 全従業員向けの評価項目
- 管理職の評価項目
- 営業職の評価項目
- コンピテンシー評価シートの書き方
- コンピテンシー評価を成功に導く3つのポイント
- 目的を見失わず成果も評価する
- コンピテンシーモデルにとらわれ過ぎない
- 評価基準・項目は定期的に見直す
- システムを活用しながら効果的にコンピテンシー評価を導入しよう
- コンピテンシー評価で組織の成長を加速させよう
「自社の評価制度は基準が曖昧で、社員の行動や貢献を正しく評価できていない」と感じていませんか?
高パフォーマーの行動特性を評価軸に組み込む「コンピテンシー評価」は、その解決策ですが、導入や運用が難しいと感じる方も少なくありません。
本記事では、コンピテンシー評価とは何か、そのメリット・デメリットから、具体的な項目設定や評価シートの書き方まで、失敗しないための方法を解説します。また、システムを導入することで効果的にコンピテンシー評価を取り入れる方法も紹介します。
この記事を読めば、自社に合った評価制度を設計し、社員の納得感と組織の生産性を高められるでしょう。
コンピテンシー評価とは
コンピテンシー評価とは、企業内で高い成果を上げている人材に共通して見られる行動特性を分析し、それを評価基準として活用する人事評価の手法です。コンピテンシー評価は、具体的には「主体的に動く」「周囲と円滑に連携する」などの行動パターンが対象になります。
この制度の特徴は、「できる人の行動をモデル化し、他の社員にも求める」という点です。スキルや知識そのものではなく、それをどう発揮するかに着目することで、実践的かつ公平な評価が可能になります。
従来の職能評価や成果主義では見落とされがちな過程を評価するため、組織内の行動基準をそろえやすくなる効果も期待できます。導入することで、評価制度と人材育成の連動がしやすくなるのがメリットです。
年功序列から成果主義へと人事評価制度がシフトしていく昨今、社員を公平に評価できることで人材の定着も狙えるという点で近年注目を集めています。
【関連コンテンツ】
コンピテンシー評価と類似する評価制度の違い
コンピテンシーとよく似た概念に、以下のような制度があります。
職能資格制度(能力評価)
バリュー評価
パフォーマンス評価
MBO(目標管理制度)
それぞれ比較されることが多いため、よく理解したうえで使い分ける必要があります。
職能資格制度(能力評価)との違い
職能資格制度は、従業員の持つ能力やスキルの高さを評価基準とする制度です。一方、コンピテンシー評価は、その能力を「どのような行動として発揮しているか」に注目します。
職務資格制度 | コンピテンシー評価 | |
|---|---|---|
評価対象 | 従業員の持つ能力やスキルの高さ | 高い成果を出すために発揮された行動 |
注意点 | その能力が実際の業務で成果に結びついているかまでは問わない | 専門知識が豊富でも、それを活かした行動が伴っていなければ評価されない |
職能資格制度は知識やスキルの高さに注目し、コンピテンシー評価は行動の質や成果への貢献度に着目するという違いがあります。
そのため、職能資格制度は勤続年数に応じて等級が上がる年功序列的な運用の温床となりやすい点がデメリットです。
一方、コンピテンシー評価は専門知識や研修受講歴などが豊富でも、それを活かした行動が伴っていなければ高く評価されない可能性があります。実際の仕事の場面において、どのように動くかを重視するのがコンピテンシー評価の特徴です。
バリュー評価との違い
バリュー評価との違いは、評価する行動の目的と適用範囲にあります。
バリュー評価 | コンピテンシー評価 | |
|---|---|---|
評価基準 | 企業が掲げる理念や価値観を社員がどれだけ行動で体現できたか | 高い業績につながる具体的なやり方 |
目的 | 企業文化の浸透や組織の一体感の向上 | 個々のスキル向上や成果の最大化 |
バリュー評価はあるべき姿に対しての評価であり、コンピテンシー評価は成果に直結する行動の評価といえます。
両者は対立するものではなく組み合わせることで、自社らしいやり方で、高い成果を出しているかを多角的に評価できるようになります。理念浸透と業績向上を同時に実現する、戦略的な評価制度の設計が実現できるでしょう。
パフォーマンス評価との違い
パフォーマンス評価は、従業員が実際に出した業績や成果そのものを評価する制度です。一方、コンピテンシー評価では成果を生み出すまでの行動プロセスが評価対象となります。
パフォーマンス評価 | コンピテンシー評価 | |
|---|---|---|
評価対象 | 業績や成果そのもの | 成果を生み出すまでの行動プロセス |
たとえば、営業職で成績が振るわなくても、顧客への丁寧な対応や提案力など、成果に向けた適切な行動をしていれば、コンピテンシー評価では高評価となる場合があります。逆に、偶然や外的要因で成果が出たとしても、再現性のない行動であれば高く評価されません。
こうした観点から、プロセス重視のコンピテンシー評価は、個々の努力や成長を可視化しやすい制度として注目されています。
MBO(目標管理制度)との違い
MBO(目標管理制度)との違いは、評価の焦点が結果かプロセスかにあります。
MBO(目標管理制度) | コンピテンシー評価 | |
|---|---|---|
評価対象 | 自らが設定した目標への達成度 | 目標に向かう行動 |
注意点 | 自己管理を促しやすい反面、「どうやって達成したか」という行動面の評価は行われにくい傾向がある | 目標未達であっても、適切な行動ができていれば評価対象となる |
MBOが目標達成という結果にフォーカスするのに対し、コンピテンシー評価は成果につながる行動の質を見る点が大きな違いです。結果にフォーカスすることは、目標達成への意欲を高めるうえでは有効ですが、結果さえ出せばよいという成果至上主義に陥るリスクを伴います。
そのため、組織として行動基準を明確にしたい場合には、コンピテンシー評価の方が適しています。
コンピテンシー評価を導入する4つのメリット
コンピテンシー評価を導入するメリットは、4つあります。
評価への納得感が高まりやすい
企業のビジョンが浸透しやすくなる
人材育成の方向性が明確になる
評価者の負担を軽減できる
以下で、それぞれのメリットについて詳しく紹介します。
評価への納得感が高まりやすい
コンピテンシー評価には、評価の納得感を高めやすい利点があります。なぜなら、評価基準が成果を生むための具体的な行動に基づいているからです。
多くの社員が評価に不満を抱く根源は、「なぜこの評価なのかわからない」という基準の曖昧さにあります。
たとえば、評価面談の場で上司から「もっと主体的に」といわれるだけでは、具体的にどのように行動すればよいかわからない人も多いでしょう。「君の行動は『指示された業務を遂行する』レベル2に当たる。次のステップとして『自ら課題を見つけ改善提案をする』レベル3の行動を期待する」と具体的な基準で伝えられれば、部下は評価を受け入れやすく、次のアクションも明確になります。
評価プロセスが明確になることで、社員は自分の行動が正当に評価されていると感じられるため、モチベーションの向上や優秀な人材の離職防止も期待できます。
企業のビジョンが浸透しやすくなる
コンピテンシー評価を導入すると、企業のビジョンや価値観が現場レベルに浸透しやすくなります。コンピテンシー評価は、理念や価値観を評価されるべき具体的な行動へと落とし込み、日々の業務と結びつけることが可能です。
たとえば、企業が挑戦というバリューを掲げているとします。これをコンピテンシー項目として「現状維持に満足せず、新しい手法や前例のない課題に積極的に取り組む」と定義し、その行動を高く評価する仕組みを構築します。
社員は、評価されることを意識して、自然と会社が大切にしている価値観に沿った行動を取るようになり、組織全体に浸透していくでしょう。
コンピテンシー評価を通じて理念に基づいた行動を評価することは、組織のベクトルをひとつに束ね、ビジョン実現に向けた実行力を高めることにつながります。
人材育成の方向性が明確になる
コンピテンシー評価は、評価と育成をシームレスにつなぎ、人材育成の方向性が明確にできる点がメリットです。
評価に用いるコンピテンシー項目は、具体的な行動レベルで定義されているため、社員自身が「どの行動を強化すればよいか」を明確に把握できます。また、上司からのフィードバックも行動ベースで行えるため、指導や研修の的確さが向上します。
たとえば、組織全体の評価データを分析すれば、「若手層では交渉力が共通の課題である」という傾向がわかり、的を絞った研修プログラムの企画が可能です。
コンピテンシー評価は、単なる査定ではなく、成長を促すための指針として機能するのです。
評価者の負担を軽減できる
コンピテンシー評価は長期的な視点で見れば、評価者である管理職の心理的・時間的な負担を軽減する効果があります。
従来の評価制度では、成果が出た理由や業務プロセスの把握が曖昧で、主観に頼る場面も多くありました。しかし、コンピテンシー評価では、あらかじめ定められた行動モデルに沿って評価を行うため、判断基準が明確です。
そのため、評価者は自信を持って判断を下すことができ、評価の迷いが軽減されます。具体的には、期末に記憶を頼りにコメントをひねり出すのではなく、期中に記録した内容を評価項目に当てはめるだけで、客観的で説得力のある評価が作成できます。
評価業務が標準化・効率化されることで管理職は評価の作業から解放され、部下の成長支援というより本質的なマネジメント業務に、エネルギーと時間を費やすことが可能です。
コンピテンシー評価で注意したい3つのデメリット
コンピテンシー評価には多くのメリットがある一方で、導入・運用において注意すべきデメリットも存在します。主に以下の3点が挙げられます。
評価モデルの設計に時間がかかる
環境変化への対応が難しい場合がある
形骸化のリスクがある
制度の効果を最大化するためには、メリットだけでなくデメリットを正しく理解したうえで導入・運用することが重要です。
評価モデルの設計に時間がかかる
コンピテンシー評価の導入における最初のハードルは、評価モデルの設計に相応の時間と労力がかかる点です。
この制度では、自社で成果を出している社員の行動を分析し、それを評価基準として体系化する必要があります。そのため、他社の評価項目をそのまま流用しても、自社の事業内容や文化に合わず機能しません。
ヒアリングや観察を通じてハイパフォーマーの共通する行動を洗い出す工程には、多くの人手と専門的な視点が必要です。
そのため、短期間での導入を期待してしまうと、設計が不十分になり、適切に評価できないおそれがあります。手間を惜しまず、自社に合ったモデルを構築することが、後の成功につながります。
環境変化への対応が難しい場合がある
コンピテンシー評価を導入した後に注意すべきなのが、環境変化への対応が難しくなる可能性があることです。コンピテンシー評価は、一定の行動特性を基にモデル化するため、一度策定した評価基準が固定化されやすい傾向にあります。
たとえば、組織の方向性が変わったり、業務内容が大きく変化したりした場合でも、以前の基準のままでは現場とのズレが生じるおそれがあります。
評価モデルを最新の実態に合わせて柔軟に更新するには、継続的な見直し体制と経営・人事部門の連携が必要です。制度を形だけで運用するのではなく、常に現場と照らし合わせていく姿勢が求められます。
対策として、2〜3年に一度は必ずモデルを見直すプロセスを制度に組み込み、常に環境変化に適応させていく仕組み構築が重要です。
形骸化のリスクがある
どれほど精緻な評価モデルを設計しても、運用段階で十分に活用されなければ、制度が形骸化してしまうリスクがあります。
評価者がコンピテンシーの定義や行動レベルを正しく理解していなければ、社員の納得感は得られません。具体的には、評価項目が多すぎて現場で把握しきれなかったり、評価者の理解が浅く適切なフィードバックができなかったりするケースが挙げられます。
これを防ぐためには、評価者を集めて匿名の評価サンプルについて議論し、評価基準の解釈を統一するための機会を設けることが有効です。制度導入と評価者研修を必ずセットで計画して継続的なトレーニングと制度の見直しを行うことで、形だけの評価にならないよう注意しましょう。
コンピテンシー評価の導入手順と設計ステップ
コンピテンシー評価を効果的に活用するためには、正しい導入手順と設計ステップを踏むことが重要です。以下の5つの流れを意識することで、制度として定着しやすくなります。
- ハイパフォーマーやモデル対象へのヒアリング・分析
- コンピテンシー項目の検討・策定
- コンピテンシーをもとにして行動モデルを作成
- 企業ビジョンや経営戦略とマッチした評価項目を選定
- 運用・評価・改善を繰り返す
「仕組みが複雑で何から手をつければよいかわからない」という不安な方は、上記を意識することで着実に導入を進められるでしょう。
1.ハイパフォーマーやモデル対象へのヒアリング・分析
コンピテンシーモデル設計の出発点は、自社で継続的に高い成果を上げている社員の思考様式や行動パターンを徹底的に分析することです。
この段階では、実際に高い成果を出している社員に対してインタビューを行い、その人の行動パターンや考え方、判断の基準などを詳しく聞き取ります。加えて、日常業務の様子を観察しながら、何が成果につながっているのかを多面的に分析します。
そのためには、最近の業務でもっとも成功した体験について語ってもらうのが効果的です。具体的な行動やきっかけについて深掘りし、その背景にある価値観や意思決定プロセスを解明していきます。
ヒアリング対象は1人ではなく、複数人に実施することで、客観性の高い行動特性が浮かび上がります。
2.コンピテンシー項目の検討・策定
次に、ハイパフォーマー分析で得られた膨大な行動事実の中から、ハイパフォーマーに共通して見られる行動パターンを抽出し、評価項目としてグルーピング、言語化します。
具体的な手法としては、抽出した行動エピソードを付箋などに書き出し、似た内容のものを集めてグループ化していく方法が有効です。
たとえば、「顧客の隠れたニーズを引き出した」「相手の意見の真意を汲み取った」などのエピソードが集まれば、「対人理解力」という項目が浮かび上がります。
この作業では、抽象的すぎる表現を避け、誰が見ても理解できる具体的な言葉に置き換えることが大切です。 また、職種や階層によって求められる行動が異なるため、必要に応じて階層別・職種別に分類しておくと、より実践的な評価制度になります。
3.コンピテンシーをもとにして行動モデルを作成
コンピテンシー項目が決まったら、それを具体的な評価に活かすために行動モデルを作成します。行動モデルとは、コンピテンシーがどのような行動として現れるのかをレベル別に示したものです。
たとえば、「主体性」という項目であれば、「上司の指示を待たずに行動できる」「周囲に働きかけて業務を改善する」など、実際の職場で観察できる行動として明文化します。 さらに、1~5段階などの評価レベルを設けて、「どのレベルの行動が高評価になるか」も明示することで、評価者の判断を統一しやすくなります。
このように、誰が読んでも同じ情景が思い浮かぶレベルの行動に変換することで、実効性のある制度の完成です。
4.企業ビジョンや経営戦略とマッチした評価項目を選定
続いて行うのは、企業ビジョンや経営戦略と一致した評価項目の選定です。ここまでのステップで作成したコンピテンシー項目が、自社のミッションや経営戦略と完全に整合性が取れているかを厳密に検証し、最終的な評価項目として絞り込む工程です。
たとえば、ハイパフォーマー分析で「卓越した個人スキル」という特性が抽出されたとしても、会社が今後組織連携の強化を戦略として掲げているのであれば、「チームワークへの貢献」という項目を追加・重視する必要があります。
そのためには、戦略とコンピテンシー項目を一覧表にして、一つひとつ整合性をチェックしていく作業が有効です。この工程を省いてしまうと、制度が会社の方向性とずれてしまい、社員にも評価の意味が伝わりにくくなってしまいます。
この検証は、経営陣や各部門責任者と連携しながら、事業計画と人材戦略の接点を明確にしておくことで、制度全体の一貫性が高められるでしょう。
5.運用・評価・改善を繰り返す
精緻なモデルが完成したら、最後は導入と運用のフェーズです。しかし、いきなり全社導入するのはリスクが高いため、慎重なステップを踏むことが重要です。
まずは、特定の部署や階層に限定して試験的に導入して、評価シートのわかりやすさや基準の妥当性を検証し、現場からのフィードバックを収集します。その結果をもとにモデルを改善し、全社展開へと進めます。
その際に重要なのが、評価者研修です。管理職を集めて、評価基準の目線合わせを徹底しながら制度を育てていく姿勢が求められます。
また、2〜3年に一度、モデルが陳腐化していないかを見直して改訂していくプロセスを計画に組み込むことが重要です。「導入→運用→効果測定→改善」というPDCAサイクルを回し続けることで、制度は組織に深く定着し、その効果を発揮できるようになります。
【職種別】コンピテンシー評価シートの評価項目の具体例
「理論は理解できたが、具体的にどのような評価項目を作ればよいのかわからない」という人のために、すぐに使えるコンピテンシー評価の項目例を、具体的な行動レベルの記述とセットでご紹介します。
全従業員向けの評価項目
管理職の評価項目
営業職の評価項目
自社の評価シートを作成したり、既存の項目を見直したりする際のたたき台として、ぜひ活用ください。
全従業員向けの評価項目
すべての従業員に共通して求められるコンピテンシーの評価項目には、以下のような「基本的な業務遂行能力」や「組織行動」が含まれます。
報告・連絡・相談を適切に行う
チームメンバーと円滑に協力できる
指示された作業を正確に遂行できる
たとえば、「基本的な業務遂行能力」では以下のような基準が考えられます。レベル1とレベル5を紹介するので、レベル感について参考にしてみてください。
レベル1:指示された業務を責任をもって遂行する
レベル5:担当範囲を超え、組織全体の課題を自分事として捉え、解決のために率先して行動する
また、「組織行動」では以下のように設定できます。
レベル1:チームのルールを守り、協力的な姿勢を示す
レベル5:チーム内の対立を乗り越え、多様なメンバーの力を結集し相乗効果を生み出す
これらはあくまで一例ですが、自社の行動指針を、このような具体的な行動の言葉に翻訳し直すことが、自社独自のモデルを作成する第一歩となります。
管理職の評価項目
管理職には、個人のプレイヤーとしての成果だけでなく、チームや組織の成果を最大化するためのマネジメント能力が求められます。具体的には、一般社員とは異なる「マネジメント能力」や「戦略的思考力」が求められます。 代表的な評価項目は以下のとおりです。
部下の育成や指導ができる
チームの目標を明確にし達成に導く
経営方針を部門に適切に落とし込む
感情的にならず冷静に判断できる
たとえば、「マネジメント能力」という項目では以下のような基準が設定できます。
レベル1:部下の業務進捗を管理し、必要な指示を行う
レベル3:部下一人ひとりの強み・弱みを把握し、定期的な1on1を通じて計画的に成長を支援する
レベル5:部下のキャリアプランを共に描き、挑戦的な機会を提供することで次世代リーダーを育成する
管理職の行動は、部下のモチベーションや成長、また部署全体の生産性に影響を与えます。そのため、その重要な役割にふさわしい行動を明確に定義し、育成・評価することが強い組織を作る上で必要不可欠です。
営業職の評価項目
営業職には「顧客との関係構築」や「目標達成への行動力」など、現場での成果につながる行動が求められます。具体的には、以下の評価項目が考えられます。
顧客の課題を的確にヒアリングできる
提案内容をわかりやすく伝えられる
計画的にアプローチ件数を増やす
たとえば、「顧客関係構築力」では、以下のような基準が考えられます。
レベル1:担当顧客と良好な関係を維持する
レベル3:顧客のビジネスを深く理解し、信頼されるパートナーとしての地位を築く
レベル5:顧客組織内のキーパーソンと強固なネットワークを構築する
これらはあくまで一例です。エンジニア職であれば「論理的思考力」、企画職であれば「情報収集力」など、職種ごとに盛り込むべき項目は異なります。
自社のハイパフォーマーの行動を分析し、ぜひ言語化してみてください。
コンピテンシー評価シートの書き方
コンピテンシー評価シートを作成する際には、評価期間中の「具体的な行動事実(エピソード)」に基づいて記述することが重要です。「頑張った」「よくやっている」などの抽象的な感想や所感でシートを埋めてしまうと、結局は従来の曖昧な評価と変わらず、公平性が担保できません。
客観的な行動事実を振り返るプロセスそのものが、自己の強み・弱みの客観的な認識や、次への改善アクションの発見に直結します。
たとえば、コンピテンシー項目「計画力」の自己評価で、「〇〇プロジェクトを計画的に進めた」と書くのではなく、「〇〇プロジェクトにおいて、関係部署へのヒアリングから潜在リスクを3点洗い出し、詳細なWBSを作成したことで、手戻りを防ぎ計画通りに完了できた」と記述します。
「できているかどうか」だけでなく「どの程度できているか」も示すことで、評価の納得感と説得力が増すでしょう。上司からのコメントも同様に、具体的な行動を承認し、「リスクを特定した行動は『計画力』レベル3に合致する。来期は代替案まで計画に盛り込むと、さらに上のレベルを目指せる」と、評価基準と紐づけて次の成長課題まで示唆することが重要です。
さらに、シートの最後に自由記述欄を設けることで、数値では表現しきれない成果や成長を記録できます。評価シートは、評価のためだけでなく、育成やフィードバックのためのツールとして設計することが重要です。
コンピテンシー評価を成功に導く3つのポイント
コンピテンシー評価を制度として効果的に運用するためには、いくつかの工夫が必要です。ここではとくに重要な3つのポイントをご紹介します。
目的を見失わず成果も評価する
コンピテンシーモデルにとらわれ過ぎない
評価基準・項目は定期的に見直す
上記のポイントを意識することで、形だけの評価制度に終わらせず、社員の成長と組織の成果を両立させる制度運用が可能になります。
目的を見失わず成果も評価する
コンピテンシー評価は行動を評価しますが、それだけを評価対象にしてしまうと本来の目的を見失うおそれがあります。本来、評価制度は人材の育成と企業の成果向上を両立させるためのものです。
行動が目的ではなく、成果にどうつながったかという視点を持つことが大切です。全く成果が出ていない社員を高く評価してしまうことのないように、「よい行動」が「よい結果」に繋がっているかを検証する視点を持つ必要があります。
結果評価とプロセス評価を組み合わせ、「正しいやり方で、正しい結果を出す」人材を育てるという本来の目的を決して見失わないようにしましょう。
コンピテンシーモデルにとらわれ過ぎない
コンピテンシーモデルは、理想的な行動を明確にするために有効なツールですが、それに固執しすぎると現場での柔軟な運用が難しくなります。
企業の環境や組織構造、職種の特性は常に変化しています。そのため、過去に作成したモデルがすべての場面で有効とは限りません。
モデルに書かれていない予期せぬ貢献や、個人のユニークな強みを柔軟に拾い上げ、評価する余地を残しておくことが、社員の主体性とイノベーションを育むうえで重要です。
評価の基本軸としつつも、モデルでは測れない価値ある行動を見つけて賞賛する文化が、組織の活力を生み出します。
評価基準・項目は定期的に見直す
評価制度は一度作れば終わりではなく、常に見直しと改善が必要です。とくにコンピテンシー評価では、行動基準が業務の実態に合っているかを定期的に確認する必要があります。
具体的な見直しの仕組みとして、中期経営計画が更新されたタイミングや「3年に一度」など、モデルをレビューするルールをあらかじめ制度に組み込んでおくことが効果的です。
その際には、社員や評価者からのフィードバックを積極的に取り入れることで、より納得感の高い制度に成長させることができます。制度が現場と乖離してしまうと形骸化しやすくなるため、制度を育てる意識で運用していくことが成功のポイントです。
システムを活用しながら効果的にコンピテンシー評価を導入しよう
コンピテンシー評価は、評価の公平性と納得感を高め、人材育成と組織の成果向上を両立させる、現代の組織経営において強力な仕組みです。
しかし、これまで見てきたように、その導入・運用には評価モデルの設計が複雑である点や運用の工数がかかるなどの課題が伴います。
この課題を解決し、導入効果を最大化するために有効なのは、最新の人事評価システムやタレントマネジメントシステムです。システムを使えば、評価項目の設定・配信・集計を自動化できるため、評価者の負担が軽減されます。また、評価データを蓄積・分析できるため、社員ごとの成長傾向や組織の課題を可視化することも可能です。
たとえば、『HRBrain タレントマネジメントシステム』は、評価運用の効率化だけでなく、人材データの一元管理や、1on1ミーティングにおけるサポートなど多彩な機能を備えています。そのうえ、はじめてシステムを利用する方でも使いやすい操作性であるため、手軽に導入できます。
コンピテンシー評価の導入は、単なる制度変更ではなく、組織の価値観を問い直す戦略的プロジェクトです。評価制度の効果を最大限に引き出すためにも、人事システムとの連携を視野に入れた運用をおすすめします。
コンピテンシー評価で組織の成長を加速させよう
本記事では、コンピテンシー評価の基本から具体的な導入ステップ、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。
コンピテンシー評価は、単なる成果だけでなく「高い業績につながる行動特性」を評価基準とするため、従業員の納得感を醸成し、企業のビジョンに基づいた戦略的な人材育成を可能にします。
導入にはモデル設計の手間や必要な側面もありますが、本記事で示した導入手順を参考に、自社の状況に合わせて設計・運用することが成功の鍵です。
また、効率的にコンピテンシー評価を導入する場合には、『HRBrain タレントマネジメントシステム』の利用がおすすめです。人材データの集約・一元管理で人事施策に役立てられるうえに、マネジメント課題の特定から管理職の育成計画までサポートしてくれます。
自社に最適なシステムを導入し、評価制度を整えたうえで、組織全体のパフォーマンス向上と持続的な成長を実現しましょう。