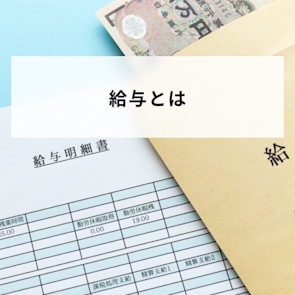バックオフィスDXとは?メリットや5つの導入手順、成功ポイントを解説
自社に最適な人事評価制度設計から運用まで、専門家が伴走支援
- バックオフィスDXとは
- バックオフィスDXが注目される理由
- 急激に変化する働き方に対応するため
- 「2025年の崖」問題に対応するため
- 頻繁な法改正に迅速に対応するため
- バックオフィスDXを実践するメリット5選
- 生産性向上につながる
- 多様な働き方に対応できる
- コスト削減につながる
- 業務の正確性が担保される
- 業務の属人化を防げる
- バックオフィスDXの導入手順5ステップ
- 1.DX推進の目的明確化と現状の業務を可視化する
- 2.DX化する業務を検討する
- 3.社内のDX推進体制を整える
- 4.目的に合うツール・サービスを導入する
- 5.導入後の効果測定とPDCAサイクルを回す
- バックオフィスDX推進にはツールやアウトソーシングの活用が効果的
- RPAツールを活用する
- クラウドシステムを導入する
- アウトソーシングを利用する
- バックオフィスDXを成功させるポイント3選
- スモールスタートではじめる
- 既存システムとの連携を検討する
- 「DX推進指標」を活用する
- 【企業別】バックオフィスDXの成功事例
- 情報の一元管理で作業効率が大幅アップ|株式会社カントウ流通
- 一元化されたデータ管理で効率的な人事配置が実現|みえなか農業協同組合
- バックオフィスDXの推進で企業の競争力を高めよう
「バックオフィスDXを進めたいが、何から着手すべきかわからない」「社内の協力が得られず、バックオフィスDXが思うように進まない」といった課題を抱えていませんか?
この記事を読めば、バックオフィスDXの具体的な進め方と、失敗しないためのポイントが明確になります。
本記事では、バックオフィスDX推進のメリットや基本的な導入手順、成功に導くポイントなどを解説します。成功事例も紹介するので、バックオフィスDXに興味がある場合には、ぜひ参考にしてみてください。
バックオフィスDXとは
バックオフィスDXとは、人事評価や労務管理などの間接部門の業務にデジタル技術を導入し、業務プロセスや組織、働き方を変革することです。
具体的には、これまで手作業で行なっていた請求書の発行や経費精算などを、クラウドサービスやRPAツールなどを活用して自動化・効率化することを指します。単にアナログな作業をデジタルに置き換えるだけでなく、データの活用や組織文化の変革を通じて、企業全体の競争力向上を目指すことが重要です。
たとえば、紙の書類で行っていた勤怠管理を、クラウドシステムに置き換えることで作業時間を大幅に削減できます。 このように、バックオフィスDXを進めることで、業務の効率化だけでなく、ミスの削減や情報の一元管理も実現できます。
企業が限られた人材と時間で成果を出すためには、業務のデジタル化が必要不可欠です。バックオフィスDXは、組織の根幹を支える重要な役割となります。
【関連コンテンツ】
バックオフィスDXが注目される理由
バックオフィスDXが注目される理由は、主に以下の3つが挙げられます。
急激に変化する働き方に対応するため
「2025年の崖」問題に対応するため
頻繁な法改正に迅速に対応するため
それぞれ詳しく解説します。
急激に変化する働き方に対応するため
バックオフィスDXは、現代の多様な働き方に対応するために必要不可欠です。近年、テレワークやリモートワークが普及し、オフィスに出社しなくても業務を遂行できる環境が求められるようになりました。しかし、紙の書類やハンコを必要とする業務が多く残っていると、従業員が出社せざるを得ず、柔軟な働き方が阻害されてしまいます。
そこで、クラウド型の労務管理ツールなどを導入すれば、従業員はどこからでも業務を滞りなく進められるようになります。
このように、バックオフィスDXは柔軟な働き方を支えるために欠かせない基盤となるでしょう。
「2025年の崖」問題に対応するため
「2025年の崖」とは、経済産業省が発表したレポートで示された、日本企業が直面するデジタル化の課題のことです。
具体的には、多くの企業が抱える老朽化したシステムがブラックボックス化し、維持管理費の高騰やDXへの対応が遅れるリスクを指します。このままでは、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が発生すると警告されています。
この崖を乗り越えるためには場当たり的なシステムの延命措置ではなく、業務プロセスそのものを見直し、クラウドサービスを活用して経営基盤を刷新する、計画的なバックオフィスDXへの取り組みが必要です。
頻繁な法改正に迅速に対応するため
頻繁に行われる法改正に、迅速かつ正確に対応するためにも、バックオフィスDXは重要です。法律の改正は、企業の業務に大きな影響を与えることが多く、人事や労務の業務プロセスを根本から見直す必要が出てくるケースも珍しくありません。
たとえば、2022年1月から電子帳簿保存法が改正され、電子取引の取引情報のデータ保存が義務化されました。これに対応するためには、紙の書類を電子データで管理する仕組みを整える必要があります。もし、手作業で書類を管理していると、改正に合わせた対応に手間と時間がかかってしまい、業務が滞る原因になりかねません。
バックオフィス業務をデジタル化しておけば、システムのアップデートによって迅速に法改正に対応でき、担当者の負担が大きく軽減されます。結果として、企業全体の法令順守体制も強化されるため、DXの推進は業務の安心・安全にもつながります。
バックオフィスDXを実践するメリット5選
バックオフィスDXを実践することで、業務の効率化だけでなく、組織全体の柔軟性や生産性も向上します。 とくに注目すべきメリットは以下の5つです。
生産性向上につながる
多様な働き方に対応できる
コスト削減につながる
業務の正確性が担保される
業務の属人化を防げる
それぞれのメリットについて、具体的な内容を解説します。
生産性向上につながる
バックオフィスDXの導入は、企業の生産性を大きく向上させます。なぜなら、これまで手作業で行っていた定型業務を自動化できるためです。従業員は時間のかかる単純作業から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。
たとえば、労務管理をクラウドシステムに置き換えることで、申請や承認などの手続きがオンライン上で完結し、処理にかかる時間の大幅な削減が可能です。 また、入力ミスや確認漏れなどの人為的なエラーも減り、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
このような改善の積み重ねが、結果として組織全体のパフォーマンス向上につながるのです。
多様な働き方に対応できる
バックオフィスDXは、テレワークやフレックスタイムなどの柔軟な働き方を実現するための基盤になります。なぜなら、クラウドベースの業務ツールを導入することで、場所や時間にとらわれずに業務を遂行できる環境が整うからです。
たとえば、電子契約システムを導入すると、契約書の作成から承認から締結までの一連の流れをオンライン上で完結できます。出社しなくても契約業務を進められるため、在宅勤務中の従業員もスムーズな業務遂行が可能です。
これは、育児や介護などのライフステージの変化に直面する従業員が働き続けやすい環境を整えることにもつながり、従業員満足度の向上と優秀な人材の定着に大きく貢献します。企業はDX化を通じて、多様な人材の活躍を支援できる組織へと成長させられます。
コスト削減につながる
バックオフィスDXの導入は、さまざまなコスト削減につながります。主な削減対象は、紙代や印刷代、郵送費、人件費などです。ペーパーレス化を進めることで、これらの直接的なコストを削減できるほか、業務の効率化によって間接的なコストの削減も期待できます。
具体的には、手作業によるデータ入力やダブルチェック、書類のファイリングなどの業務にかかっていた時間を自動化することで、その分の人件費を直接的に削減できます。
バックオフィスDXは、初期投資は必要ですが、長期的に見て確実なリターンが期待できる戦略的な取り組みです。
業務の正確性が担保される
バックオフィスDXの導入は、業務の正確性を向上させます。なぜなら、デジタル技術を活用することで、人為的なミスを大幅に減らせるためです。手作業でのデータ入力や計算は、ヒューマンエラーが発生しがちですが、システムの導入によってこれらのミスを防止できます。
たとえば、クラウド型の労務管理システムによっては、入退社手続きに必要な書類を従業員の入力情報から自動作成できる場合があり、手入力による転記ミスの防止が可能です。
また、情報が常に最新の状態で保存されるため、上長や経営層も正しい判断がしやすくなります。 結果として、社内全体の業務品質の向上が期待できます。
業務の属人化を防げる
バックオフィスDXは、業務の属人化を防ぐ効果もあります。属人化とは、特定の従業員しか知らない業務や、特定の従業員にしかできない業務が存在する状態です。このような状態は、担当者が不在の際に業務が滞ったり、引き継ぎに時間がかかったりする原因となります。
たとえば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用すれば、定型業務は誰でも同じように実行可能です。 これにより、社内で均一なクオリティを担保でき、組織全体の安定性が向上します。
また、業務のマニュアルをシステム上に保存しておくことで、新入社員の教育も効率的に行え、組織全体のスキルアップにもつながります。人に依存しない仕組みづくりが、持続可能な企業運営につながるのです。
バックオフィスDXの導入手順5ステップ
バックオフィスDXを成功させるには、適切な手順で進めることが重要です。導入手順は、以下の5つのステップで進めていきましょう。
- DX推進の目的明確化と現状の業務を可視化する
- DX化する業務を検討する
- 社内のDX推進体制を整える
- 目的に合うツール・サービスを導入する
- 導入後の効果測定とPDCAサイクルを回す
各ステップのポイントを順番に確認していきましょう。
1.DX推進の目的明確化と現状の業務を可視化する
バックオフィスDXをはじめるために、まずはDXを推進する目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままツールを導入しても、期待した効果は得られません。
目的を考える際には、「年末調整にかかる時間を50%削減する」「月末の残業時間をゼロにする」など、誰にでもわかり、達成度が測れる数値目標に落とし込むことが重要です。
目的を明確にしたら、現状の業務フローを可視化します。各業務がどのように行われているか、どのくらいの時間がかかっているか、どのような課題があるかを洗い出しましょう。このとき、現場の従業員にヒアリングを行い、リアルな声を聞くことが大切です。
2.DX化する業務を検討する
次に、どのバックオフィス業務をDX化するかを検討します。 すべての業務を一度に変えるのではなく、優先度の高い業務から取り組むことがポイントです。
検討の際には、「定型的な作業が多く、自動化しやすい業務」や「ミスが発生しやすい業務」などを優先するとよいでしょう。具体的には、「年末調整の効率化」や「各種申請のクラウド化」など、日常的に発生する定型業務を選ぶことで効果が早く実感できます。
また、人事や総務が行う入社・退職手続きなども、ペーパーレス化やオンライン化を進めることで、効率が大きく向上します。
この段階で改善すべき業務を絞り込むことで、ムダのないDX推進が実現できるでしょう。
3.社内のDX推進体制を整える
バックオフィスDXを成功させるには、社内全体の協力が必要です。そこで、DX推進の責任者や担当者を明確にし、プロジェクトチームを立ち上げましょう。このチームには、人事や総務など、DX化の対象となる各部門のメンバーを含めることが大切です。
チームが決定したら、DXの目的や具体的な進め方を社内全体に共有し、従業員の理解と協力を仰ぎましょう。
新しいシステムの導入は、従業員にとって負担になることもあります。そのため、DXのメリットを丁寧に説明し、積極的に意見を求めることで、現場の協力を得やすくなります。
4.目的に合うツール・サービスを導入する
DX推進体制が整ったら、設定した目的に合うツールやサービスを導入します。ツールを選ぶ際には、機能や費用、使いやすさ、サポート体制などを比較検討しましょう。
ここで陥りがちなのが、知名度や機能の多さ、価格の安さだけでツールを選んでしまい、「導入したものの自社の業務フローに合わなかった」「機能が複雑で現場が使いこなせない」という失敗です。闇雲に最新ツールを導入するのではなく、自社の課題を解決できるかどうかを基準に選ぶことが大切です。
また、導入前には無料トライアルやデモを利用して使い勝手を確認するのも有効です。焦らず、じっくりと自社に最適なパートナーを見極めることが、DX成功の鍵を握ります。
5.導入後の効果測定とPDCAサイクルを回す
最後に、導入した施策の効果を測定し、改善を重ねていくことが必要です。 なぜなら、DXは一度導入して終わりではなく、継続的な改善が求められる取り組みだからです。
たとえば、「処理時間がどれだけ短縮されたか」「入力ミスが何件減ったか」など、具体的な数値を指標として設定し、定期的に見直します。
結果を測定できたら、改善点を見つけ出し、PDCAサイクル(Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善))を回していくことが重要です。ツールを使いこなせていない従業員がいないか、より効率的な使い方はできないかなどを確認し、必要に応じて研修を実施するなど、継続的な改善を続けることで、バックオフィスDXの効果を最大限に引き出せます。
バックオフィスDX推進にはツールやアウトソーシングの活用が効果的
バックオフィスDXを推進するにあたり、自社の課題解決に役立つツールやサービスを導入することが効果的です。ここでは、バックオフィスDXの推進に効果的なツールやアウトソーシングの活用方法について、以下の3点で解説します。
RPAツールを活用する
クラウドシステムを導入する
アウトソーシングを利用する
ツールやアウトソーシングをうまく活用することで、業務効率化や生産性向上が期待できます。
RPAツールを活用する
RPA(Robotic Process Automation)は、人間がPC上で行うクリックやキーボード入力などの定型的な手作業を記憶し、自動で実行してくれるソフトウェアロボットです。人事や総務などの間接部門の業務に適しています。
具体的には、RPAツールは以下のような業務を自動化できます。
複数のシステムからデータを抽出し、集計する作業
Webサイトからの情報収集やデータ入力
特定のメールを受信した際、自動で返信する、あるいは指定の部署に転送する作業
請求書や領収書のデータ入力
繰り返し発生する単純作業をRPAツールに任せることで、ヒューマンエラーを防ぎながら、業務時間の大幅な短縮が可能です。
RPAはプログラミングの知識が不要なツールも多く、IT部門がない企業でも導入しやすいため、RPA化できる業務を選定するところからはじめてみましょう。
クラウドシステムを導入する
クラウドシステムも、バックオフィスDXに欠かせないツールです。クラウドシステムとは、インターネットを通じて提供されるサービスやソフトウェアのことで、PCにインストールする必要がなく、インターネット環境があればどこからでも利用できます。
バックオフィス業務でよく活用されるクラウドシステムには、以下のようなものがあります。
システム | 内容 |
|---|---|
会計システム | 経理業務を効率化し、経営状況をリアルタイムで把握 |
人事・給与システム | 従業員の入社から退職までの情報を一元管理し、給与計算や年末調整などの業務を自動化 |
経費精算システム | スマートフォンで領収書を撮影するだけで経費申請ができ、経理担当者の確認作業が効率化 |
ワークフローシステム | 申請・承認業務を電子化し、社内の意思決定を迅速化 |
たとえば、クラウドサービスである「HRBrain」では、人事・労務業務においてペーパーレス化やデータの一元管理で業務の効率化を図ります。
まずは無料トライアルを活用し、自社の課題を解決できるか試してみることをおすすめします。
アウトソーシングを利用する
アウトソーシングも、バックオフィスDXを推進する上で有効な手段のひとつです。アウトソーシングとは、自社の業務の一部を外部の専門業者に委託することです。とくに、専門知識や高度なスキルが求められる業務や、定型的な業務をアウトソーシングすることで、自社のリソースをコア業務に集中させられます。
自社で新たな人材を採用・育成したり、ツールの運用管理にリソースを割いたりすることなく、専門家の高いノウハウを活用して業務品質の向上とコスト削減を両立できる点がメリットです。
自社ですべてを抱え込まず、外部のプロフェッショナルの力を戦略的に活用するという視点も、DX推進においては重要になります。選定時には、サービス内容やサポート体制、実績などを比較し、自社のニーズに合った業者を選定しましょう。
バックオフィスDXを成功させるポイント3選
バックオフィスDXを成功させるためには、ただツールを導入するだけでなく、いくつか押さえておきたいポイントがあります。ここでは、DXを成功に導くための3つのポイントを紹介します。
スモールスタートではじめる
既存システムとの連携を検討する
「DX推進指標」を活用する
これらのポイントを押さえることで、失敗のリスクを減らし、スムーズにDXを推進できます。
スモールスタートではじめる
バックオフィスDXをはじめる際には、いきなり全社的な大規模導入を目指すのではなく、一部の業務や部署に絞ってスモールスタートで取り組むのが効果的です。
なぜなら、はじめから全業務を全社的に取り組もうとすると混乱や失敗のリスクが高くなってしまうためです。
たとえば、まず労務管理など、一部の定型業務から自動化を試してみることで、時間短縮やコスト削減の面において効果を実感しやすくなります。「こういう運用ルールが必要だ」という課題を洗い出せば、その学びをもとに全社展開の計画をより精度の高いものにできます。
小さな成功体験を積み重ねていけば、現場の理解や協力も得られやすくなり、スムーズなDXの社内浸透を期待できるでしょう。
既存システムとの連携を検討する
新しいツールを導入する際は、既存のシステムと連携できるかを検討することが重要です。なぜなら、連携ができない場合、新しいシステムに入力したデータを手作業で既存のシステムに転記する必要が出てくるためです。これでは、作業が二重になり、かえって業務効率が悪化してしまう可能性があります。
たとえば、新しい労務管理システムを導入するなら、社内のデータを各システムに結びつけるために、既存の給与計算システムとAPIで自動連携できるかは必須のチェック項目です。
ツール単体の機能だけでなく、常に全社的なデータの流れを意識し、システム間の壁をなくす設計を心がけることが組織全体の生産性を最大化させる鍵となります。
「DX推進指標」を活用する
「DX推進指標」は、企業がデジタル化の進捗状況を評価するために、国が提供する指標です。DXを進める際の道しるべとして、自社の現在地を客観的に把握し、次に取り組むべき課題の明確化に役立ちます。
たとえば、経済産業省が公表している「DX推進指標とそのガイダンス」では、経営ビジョンの浸透やデジタル人材の確保など、幅広い評価項目が示されています。
このようなフレームワークを活用すれば、感覚的ではなく戦略的なDX推進が可能です。はじめてDXに取り組む企業でも、方向性を誤るリスクを下げられるため、外部の客観的な指標を活用しながら進むべき方向が正しいかを確認しましょう。
【企業別】バックオフィスDXの成功事例
ここでは、実際にバックオフィスDXに取り組み、業務効率化や人的資源の最適化を実現した企業の事例を2つ紹介します。
情報の一元管理で作業効率が大幅アップ|株式会社カントウ流通
一元化されたデータ管理で効率的な人事配置が実現|みえなか農業協同組合
DX推進の具体的なイメージを掴みたい方は、ぜひ参考にしてください。
情報の一元管理で作業効率が大幅アップ|株式会社カントウ流通

食品を中心とした輸送事業を展開している株式会社カントウ流通は、従業員情報が社内に点在し、必要な情報へのアクセスに時間と労力がかかっていたため、人材情報管理の体制整備を課題とされていました。
そこで、HRBrainを導入し、タレントマネジメントシステムや労務管理システムによって、これまで散在していた従業員情報を一元化し、誰でも必要な情報へ迅速にアクセスできる環境を構築しました。
導入後は、情報検索の効率が大幅に向上し、業務の属人化という長年の課題も解消されています。特定の情報を探す際にも、保管場所に悩む時間が確実に削減されました。今後は、入社手続きなどもHRBrain上で完結させることで、労務関連業務の大幅な効率化が期待されています。
【関連コンテンツ】
一元化されたデータ管理で効率的な人事配置が実現|みえなか農業協同組合

従業員数860名を抱え、農業に関する各種事業を展開するみえなか農業協同組合は、合併に伴い、紙の書類が膨大に増加したことやデータ基盤が複数できたことで、業務効率が著しく低下したことが課題でした。
そこで、一元化されたデータ管理の導入が急務であると判断し、「HRBrain」を導入し、タレントマネジメントシステムで職員情報を一元管理することで、人員配置の可視化を図りました。
また、労務に関しては、紙ベースで行っていた雇用契約書の確認作業を電子化し、業務効率化を図る狙いもありました。そうすることで、組織全体の効率化を図り、働きやすい職場環境の構築を目指しています。
【関連コンテンツ】
バックオフィスDXの推進で企業の競争力を高めよう
バックオフィスDXは、単なる業務効率化に留まらず、企業の競争力を高めるための重要な経営戦略です。業務の可視化と改善を繰り返すことで、効率的にバックオフィスDXを推進できます。
その際には、RPAやクラウドツールを導入することが有効です。人手に頼らずとも、正確でスピーディーな業務運営を可能にします。クラウド型システム「HRBrain」であれば、従業員情報や評価データ、組織構成などを一元管理することで人事・労務業務の効率化をサポートします。
また、最適な人材配置を考える機能や人事関連の手続きを効率化する機能があることで、管理部門の負担が大幅に軽減され、戦略的人事への時間確保が可能です。
企業が持続的に成長していくためには、バックオフィスDXの推進が欠かせません。バックオフィスをDX化することで、人的資源をより有効に活用し、組織全体の成長スピードを高めていきましょう。