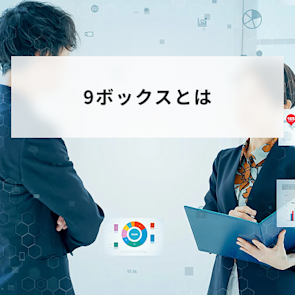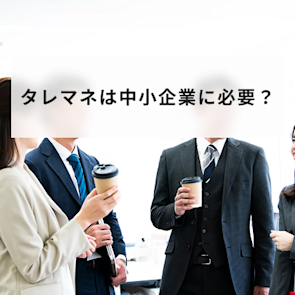納得度の高い評価とは?目指すべき状態やアクションについて
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- 評価の納得度について、⽬指すべき状態
- 評価基準が明確になっている
- 評価者自身が⾼いスキルを持っている
- 被評価者について十分な理解がある
- 評価の納得度が下がる原因
- 納得度改善のためのアクション
- ⼈事評価
- フィードバック⾯談
- ⼈事評価の納得度について、現状を正しく理解する
- 評価の納得度を向上させた具体的な成功例
- 紙の評価シートからシステムに切り替えて工数削減&評価項目も一新|イオンディライトセキュリティ株式会社
- HRBrainで人事評価の運用を効率化したその秘訣とは?|駒澤大学
- 20年ぶりの人事評価制度刷新とタレントマネジメントの活用|株式会社日比谷花壇
評価の納得度は、多くの企業の人事が抱えている問題のひとつです。しかし、具体的な解決策が見いだせず、従業員エンゲージメントの低下を招くケースも多いでしょう。
また、評価の納得度は人事が課題として認識していても、経営層は重視していないケースがあります。評価の納得度は企業全体の生産性にも関わるため、人事だけでなく経営層も着目すべき観点です。
今回は、評価制度の目指すべき状態や評価の納得度が下がる原因、そして、納得度改善のアクションについてご紹介します。
評価の納得度について、⽬指すべき状態
評価に対する従業員の納得度を向上・維持するために目指すべき状態とは、どのような状態でしょうか。以下で紹介する内容に当てはまる状態を参考に、自社の現状と理想に当てはめてみてはいかがでしょうか。
評価基準が明確になっている
評価に対する納得度が低い企業は、評価基準が曖昧である可能性があります。評価基準は従業員の育成はもちろん、エンゲージメント向上にも関連する重要な要素です。
そのため、まずは評価基準を明確にし、従業員に浸透させましょう。そのうえで、企業が目指す方向を従業員が理解できる体制を整える必要があります。また、企業の方向性と従業員のモチベーションを合致させるうえでも評価基準の明確化は重要です。
自社の評価基準が曖昧なものになっていないか、改めて見直すことで評価の納得度は向上するでしょう。
評価者自身が⾼いスキルを持っている
評価者のスキルが低い企業では、的確なフィードバックが実施できません。そのため従業員は、評価を上げるための行動が取りづらくなってしまいます。
従業員を適切に評価できるよう、評価者は以下を意識してください。
従業員に関する情報をメモし、把握する
従業員が目的を達成できるための環境を整備する
従業員の得手・不得手を把握する
過去の評価・目標を参照する
改善が必要な点・その改善方法を提示する
また、評価者自身のスキルを高い基準にするために、評価制度に関する説明会や研修を実施するのもおすすめです。
被評価者について十分な理解がある
被評価者である従業員の情報を事前に把握しておかないと、納得のいく評価にはつながりません。どのような人材なのか詳細に把握しておくことで、印象に左右される評価を避けられます。
評価者も人間である以上、どうしても印象点が評価に反映されがちです。しかし、印象に左右される評価点は納得度の高い評価体制の構築からは遠ざかってしまいます。
従業員についての情報収集を実施し、十分に従業員を理解したうえで評価しましょう。また、従業員と対面で話す機会になる「1on1」を定期的に開催するのもおすすめです。
評価の納得度が下がる原因
評価の納得度が上がらない原因に、人事評価自体が適切に実施されていない場合が挙げられます。評価に関するフィードバック面談などを実施していないために、なぜこの評価がされたのか?と疑問が出る従業員も多いでしょう。
適切な人事評価が実施されず、評価の納得度が下がることで、従業員のモチベーションが下がってしまいます。事態が悪化すれば、何のための人事評価なのか?という疑問を感じた従業員が離職することもあるでしょう。
納得度改善のためのアクション
評価の納得度に関する課題を解決するためには、人事評価・評価のフィードバック面談を適切に実施する必要があります。また、評価結果を次回に活かせる面談の実施や、納得度に関する現状の把握も大切です。
⼈事評価
人事評価にはいくつかの評価方法があり、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
成果評価
一定期間に定めた目標の達成度や過程を評価する方法。目標には、数字で表せる「定量的」な目標と、数字以外で表す「定性的」な目標の2種類がある。
能⼒評価
与えられた職務に対する遂行力を評価する方法。社内で定めた規定に則した評価が必要。
情意評価
勤務態度や企業ビジョンへの共感などを基準に評価する方法。主観が入りやすいため評価には注意しなければならない。
参考:人事評価の項目とは?評価の種類と、具体的な項目について解説
フィードバック⾯談
評価のフィードバック面談は、適切な評価はもちろん、従業員とのコミュニケーションの機会としても重要です。また、面談を通じて適切に評価することで、評価者・企業に対する従業員の印象もよいものになるでしょう。
フィードバック面談はただ実施するだけでなく、1on1のログなどを残しておくことも大切です。ログを残しておくことで、従業員が過去の自分を振り返ることも可能です。
過去のログを見て成長を実感できることもあるため、モチベーションアップにもつながります。
次回につながる⾯談をする
フィードバック面談を正しく行うことで、従業員自身が次回の評価面談までにどうなるべきかを把握しやすくなります。目標達成に向けたモチベーションの向上やパフォーマンスのアップが期待できるでしょう。
また、従業員が「自分を評価した上で評価面談をしてくれている」と感じることで、評価への納得度が向上します。また、次回の評価を想定し、従業員が自身のモチベーションを明確にする効果も期待できるでしょう。
参考:フィードバック面談とは?マイナス評価の部下への伝え方も解説!
社内で実施するのが難しい場合は、外部の評価者研修を受講するのもおすすめです。
⼈事評価の納得度について、現状を正しく理解する
人事評価への納得度を高めるためには、まずは企業が自社の置かれている現状を把握する必要があります。自社の現状を把握したうえで、⼈事評価の納得度をモニタリングしましょう。
評価の納得度が低ければ、なぜ低いのかを徹底的に調査する必要があります。また、これまでと比べて下がってしまっている場合は、なぜ下がっているか?その理由を調査しましょう。
評価の納得度を向上させた具体的な成功例
実際にどのような方法で評価の納得度を向上させるべきか、HRBrainを導入した企業の事例から見てみましょう。
紙の評価シートからシステムに切り替えて工数削減&評価項目も一新|イオンディライトセキュリティ株式会社
イオンディライトセキュリティ株式会社は、施設警備業務をメインに事業を展開しています。施設警備業務以外ではイベントに関わる警備業務の運営・企画のほか、近年は施設の快適性診断事業も手掛けています。アナログの紙で人事評価を行っていたことでの作業工数の多さや評価項目の内容に課題を感じていました。
課題
紙で人事評価を行っていたことで、膨大な作業工数がかかっていた
評価シートを回収したあと返却をしていなかったことで本人が設定した目標を忘れてしまっている
評価の運用だけでなく 、現場にそぐわない曖昧な評価項目など、内容にも多くの問題を抱えていた
課題解決のカギ
感覚的・直感的な操作性に優れているタレントマネジメントシステム「HRBrain」を導入
パソコン操作が苦手な方に向け、マニュアル動画を作成し全社的に案内
各拠点の幹部層に対して、HRBrain主催の評価者研修をZoomで実施
感覚的・直感的な操作性に優れているタレントマネジメントシステム「HRBrain」を導入。パソコン操作が苦手な方に向け、人事課長が出演するマニュアル動画を作成し社内に案内することで、全社的なシステム普及に繋がりました。また、各拠点の幹部層に対してHRBrain主催の評価者研修をZoomで実施することで、幹部層が評価を行う重要性の理解を促進することができました。
システム導入効果
人事評価に関して、幹部や現場から「圧倒的に作業が楽になった」という声を聞くことができた
自身の評価に対する従業員からの声を聞くことができた
導入システム
HRBrain 人事評価 | HRBrain
▼資料請求
HRBrain 人事評価 サービス資料
▼導入事例
紙の評価シートからシステムに切り替えて工数削減&評価項目も一新
イオンディライトセキュリティ株式会社 | 導入事例
HRBrainで人事評価の運用を効率化したその秘訣とは?|駒澤大学
駒澤大学は、「仏教」の教えと「禅」の精神を建学の理念とし、開校から130年以上、前身に遡れば420年以上の歴史を有している、約14,500人が7学部、9大学院研究科で学んでいる総合大学です。構築した人事制度をもとにエクセルで運用していましたが、シート回収などの作業に煩雑さなどの課題を感じていました。
課題
人事評価をエクセルで運用していたが、毎回回収する200枚以上の評価シートの管理に煩雑さを感じていた
課題解決のカギ
管理者も現場も使いやすいUIのタレントマネジメントシステム「HRBrain」を導入
勤怠管理や労務管理などの接続を行う他社システムの社員マスタと人事評価を行う「HRBrain」を効率的に連携
管理者も現場も使いやすいUIのタレントマネジメントシステム「HRBrain」を導入。勤怠管理や労務管理などの接続として他社システムの社員マスタを利用している一方で、人事評価のみエクセルで運用していたものを「HRBrain」に移行し、人事評価にかかっていた工数をスムーズに効率化できました。
システム導入効果
エクセルで行っていた人事評価にかかる業務の工数を8割削減でき、管理者と現場の作業負担が軽減された
人事評価の進捗を「HRBrain」から一目で確認できることで、制度がしっかり運用できていることの確認にもなった
導入システム
HRBrain 人事評価 | HRBrain
▼資料請求
HRBrain 人事評価 サービス資料
▼導入事例
評価の進捗管理・シート回収作業が8割減少! HRBrainで人事評価の運用を効率化したその秘訣とは?
駒澤大学 | 導入事例
20年ぶりの人事評価制度刷新とタレントマネジメントの活用|株式会社日比谷花壇
株式会社日比谷花壇は、フラワーショップの経営をはじめ、イベントプロデュース、ウエディングフラワー、EC、フラワーギフト・デザインの企画、制作、販売、フューネラル(葬儀)などの事業を展開しています。また、緑を活用した内装・造園事業も行っています。人事評価が20年前から抜本的な見直しがされないまま運用され続けていたことや人事システムの使いづらさに課題を感じていました。
課題
長期間見直しがされていなかった人事制度に「基準があいまい」「上長によって評価にバラつきがある」などの問題があった
各店舗に1台しかパソコンがないことやシステムの使いづらさから人事システムを「賞与のためだけに入力するもの」と認識されていた
課題解決のカギ
一目見たらわかる仕様・画面で操作できるタレントマネジメントシステム「HRBrain」を導入
「HRBrain」導入と同時に人事評価制度を20年ぶりに刷新
資格や独自の「今後やってみたいこと」など、社員の情報を「HRBrain」に一元管理して可視化
一目見たらわかる仕様・画面で操作できる、わかりやすいUIのタレントマネジメントシステム「HRBrain」を導入。それと同時に20年間見直しがされていなかった人事評価制度を革新しました。また、社員情報を「HRBrain」に一元管理することによって、人材データの可視化が実現されました。
システム導入効果
社員名簿から従業員の顔写真とパーソナルな情報が見られるため、人事評価しやすくなった
設立72年目にしてはじめて、対象の従業員全員が目標を入力できた
「HRBrain」上で社員が自ら情報を取得し、キャリアに活かす動きが出てきた
導入システム
HRBrain 人事評価 | HRBrain
▼資料請求
HRBrain 人事評価 サービス資料
▼導入事例
人事業務工数を7割削減。組織・人材改革を開始
株式会社日比谷花壇 | 導入事例