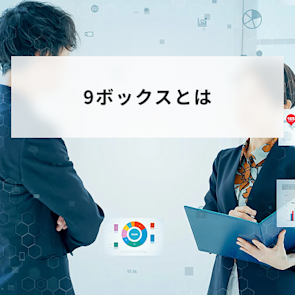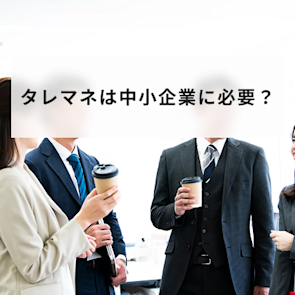評価制度の運用の形骸化を防ぐ!年間運用フローや成功させるコツ
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- なぜ評価制度の運用がうまくいかない?
- 制度の目的やビジョンが社内に浸透していない
- 評価基準が曖昧で評価結果に納得感がない
- 評価者のスキルや意識にばらつきがある
- 評価結果が処遇や育成に反映されていない
- 評価制度の運用を成功させるコツ
- 透明で明確な評価基準を設定する
- 評価者への研修を定期的に実施する
- 1on1面談を習慣化し進捗を確認する
- 評価調整会議で評価の公平性を担保する
- 評価結果を人材育成に活用する仕組みを作る
- 評価制度の運用支援するツールを使う
- 評価制度の年間運用フロー
- 期初:目標設定と共有面談を行う
- 期中:進捗確認とフィードバックを行う
- 期末:自己評価と上司評価を実施する
- 評価後:評価結果をもとに面談を行う
- 評価制度を適切に運用する4つのメリット
- 従業員の納得感とモチベーションが向上する
- 会社のビジョンや目標が現場に浸透する
- 個人の成長を促し人材育成が進む
- 公平な処遇決定の根拠が明確になる
- 評価制度を誤って運用した場合の4つのデメリット
- 優秀な人材の離職リスクが高まる
- 社員のモチベーションが大幅に低下する
- 管理職や会社への信頼感が失われる
- 評価にかけた時間や労力が無駄になる
- 評価制度の適切な運用で成長を加速させよう
評価制度は従業員の成果を可視化し、組織のパフォーマンスを最大化するための土台です。しかし、評価基準が曖昧で部下の納得感が得られず、育成にもつながらない課題を抱える組織は少なくありません。
この記事では、評価制度の運用について、形骸化を防ぐ仕組みづくりから、評価者間のズレをなくすルール設計、評価を育成と処遇に直結させるプロセスまで、実務に沿って解説します。
評価制度の運用を軌道に乗せ、組織の成長を加速させる確かな原動力にするために、ぜひ参考にしてみてください。
なぜ評価制度の運用がうまくいかない?
せっかく導入した評価制度が形骸化し、社員のモチベーション低下や不信感につながってしまう根本的な問題は、主に以下の4つに集約されます。
<評価制度の運用がうまくいかない原因>
制度の目的やビジョンが社内に浸透していない
評価基準が曖昧で評価結果に納得感がない
評価者のスキルや意識にばらつきがある
評価結果が処遇や育成に反映されていない
これらの原因を理解し改善策を講じることは、効果的な評価制度の運用へとつながります。
制度の目的やビジョンが社内に浸透していない
評価制度の目的が不明確では、評価者も被評価者も制度を管理のためのタスクとしか認識しないでしょう。結果、評価面談は形式的になり、社員の成長や組織目標達成といった本来の機能が失われてしまいます。
たとえば、「挑戦した姿勢そのものを評価する」と掲げていても、目的を共有せずに目標設定を運用すると、社員は失敗をおそれて無難な目標しか立てなくなるケースがあります。成長を支援するはずの制度が、かえって挑戦を阻害するかもしれません。
制度を機能させるには、目的を再定義し、経営層から現場まで一貫して伝え続けることが重要です。なぜこの制度が必要で、それにより社員と会社がどう成長できるのかというビジョンを共有し、制度を活性化させましょう。
評価基準が曖昧で評価結果に納得感がない
評価基準が曖昧だと、社員の不公平感や不信感につながる原因となります。たとえば、「主体性」のような抽象的な言葉では、評価者の主観で結果が左右されがちです。
社員は「何をどう頑張れば評価されるのか」が具体的にわからず、次の改善行動に移れません。たとえば、営業職では「顧客との良好な関係構築」といった項目にせず、「新規アポイント獲得数」や「アップセル契約額」など、客観的な指標に落とし込めば、評価への納得感は高まります。
効果的な評価制度には、評価基準の透明化が不可欠です。等級や職務ごとに期待される行動レベルを具体的に定義し、全社員に公開することが重要です。
評価者のスキルや意識にばらつきがある
評価制度を運用する際に、評価者にばらつきがあると、どれだけ機能する制度を設計しても、組織全体の信頼が損なわれます。多くの管理職は、一部の優れた点に引きずられて全体を高く評価してしまう「ハロー効果」や、中央値に評価を集中させる「中心化傾向」といった評価エラーに陥りがちです。
また、部下との対話を避け、一方的に評価を言い渡すだけの面談では、育成にはつながりません。結果として、部署間で評価の質に差が生まれ、社員の不公平感を招く可能性があります。
評価者研修を必須化し、全管理職のスキルと意識レベルを標準化しましょう。そのためには、評価エラーの防止策やSBIモデルなどのフィードバック手法を体系的に学び、評価者スキルを向上する必要があります。
評価結果が処遇や育成に反映されていない
社員が評価に時間と労力を費やしても、それが昇給、賞与、昇進などに結びつかない場合、評価制度の意味が薄れてしまいます。評価と結果の間に一貫性がないと、「頑張っても無駄だ」という学習性無力感が広がり、エンゲージメントは低下します。
たとえば、高評価の社員と低評価の社員の昇給率が同じだったり、面談で合意した研修が実施されなかったりするケースです。
効果的な評価制度を運用するには、評価が処遇や育成へ途切れることなく連動するサイクルを確立することが大切です。評価ランクと報酬の連動ルールを明確化し、評価面談で明らかになった強みや弱みを具体的な育成プランに落とし込み、次のサイクルへつなげる仕組みを徹底しましょう。
評価制度の運用を成功させるコツ
評価制度を形骸化させることなく、効果的に運用するコツを6つ紹介します。
<評価制度の運用を成功させるコツ>
透明で明確な評価基準を設定する
評価者への研修を定期的に実施する
1on1面談を習慣化し進捗を確認する
評価調整会議で評価の公平性を担保する
評価結果を人材育成に活用する仕組みを作る
評価制度の運用支援するツールを使う
先ほど解説した運用に失敗する原因を解決する、すぐ実践できる具体的なアクションプランです。評価制度を社員と組織の成長を加速させる制度として運用できるようにしていきましょう。
透明で明確な評価基準を設定する
評価制度を成功させるには、「何が評価されるのか」を社員が具体的に理解できる、透明で明確な評価基準を設け、全社に共有することが重要です。
これにより、主観や解釈のブレを抑え、評価のブラックボックス化を防げます。社員は評価結果に納得しやすくなり、目標達成に向けた具体的な行動を起こしやすくなるでしょう。
以下に、リーダーシップ評価基準の例をまとめます。
等級区分 | 期待される具体的な行動 |
|---|---|
メンバー | ・担当業務の進捗を自ら積極的に報告・相談する |
リーダー | ・メンバーに業務を的確に割り振り、進捗を管理する |
マネージャー | ・チーム全体の目標達成に向けて戦略を立案する |
完成した評価基準は、社員がいつでも閲覧できる場所に保管し、説明会などでその意図を全社に周知しましょう。
【関連記事】
評価者への研修を定期的に実施する
評価は人が人を評価する行為であり、評価者のスキル不足は、意図せずとも不公平な評価や部下のモチベーション低下を招きかねません。
評価エラーの防止や面談スキルは、個々の管理職の経験則だけに頼るのではなく、組織として体系的に以下のような学習の機会を提供する必要があります。
研修内容 | 実施方法のポイント |
|---|---|
評価エラーの防止 | ・具体的なケーススタディを用いた学習 |
フィードバックスキル | ・ロールプレイングを通じた実践的な対話スキルの習得 |
研修実施の仕組み | ・必須プログラムとして位置づける |
1on1面談を習慣化し進捗を確認する
期末の一方的な評価から脱却し、定期的な1on1面談で目標進捗の確認と支援をしましょう。目標とのギャップを早期に発見し、タイムリーな軌道修正が可能になります。評価時の認識のズレを防ぎ、納得感を高められるでしょう。
また、上司が「コーチ」として部下を支援することで信頼関係が深まります。たとえば、評価期間の中間地点で「チャレンジ面談」を設け、評価ではなく進捗や必要なサポートをヒアリングします。この中間面談を評価プロセスに組み込むことで、1on1面談が成功をサポートするための対話の場として定着するでしょう。
定期的な1on1面談で現在の課題や進捗などを把握し、適切なタイミングでサポートや働きかけを行うことで、評価と成長への取り組みを結びつけやすくなります。
【関連記事】
評価調整会議で評価の公平性を担保する
評価者である直属の上司だけで評価を完結させず、複数の部署の管理職が評価調整会議で目線を合わせて制度の公平性を保ちましょう。
会議では、各評価者が評価の根拠となる具体的な事実(部下の行動や成果)を持ち寄り、他の評価者の前で説明します。「Aさんのこの行動をS評価にしたのはなぜか?」といった問いに答えることを通じて、評価者は自らの評価を客観的に見直し、組織としての基準にすり合わせられます。
人事部門はファシリテーターとして参加し、評価分布データなどを提示しながら、建設的な議論を促す役割を担うことが期待されます。
評価結果を人材育成に活用する仕組みを作る
評価面談は、単に評価を伝える場にせず、面談結果を元に社員一人ひとりの強みを伸ばし、弱みを克服する育成プランを作りましょう。評価が過去の査定に終始すると、社員の意識も過去に向きがちです。しかし、評価を未来の成長につなげれば、制度は前向きに機能し、社員も次の行動へ進めます。
たとえば、評価面談の後半を将来に向けたディスカッションの時間にしてみましょう。評価でわかった課題に対し、「来期はこのプロジェクトに参加しよう」「あの先輩にメンターをお願いしよう」といった具体的なアクションプランを本人と合意します。育成プランの作成を面談のアジェンダに入れ、次期の目標設定に連動させましょう。
そうすると、評価制度は「評価→育成→目標設定」という継続的な成長支援サイクルとして機能しはじめます。
評価制度の運用支援するツールを使う
人事評価システムやテンプレートを活用し、煩雑な管理業務を効率化することで、人事や管理職が人と向き合う時間を増やしましょう。
Excelや紙での運用は、シートの配布・回収・集計といった非生産的な業務に時間を奪われがちです。ツールはこれらの課題を解決し、運用の負荷を下げ、データの可視化を促進することに役立ちます。
たとえば、人事評価システムを導入すれば、目標設定から評価、フィードバック記録までを一元管理できます。未提出者へのリマインドも自動化され、人事担当者は評価データの分析や評価者へのコンサルティングといった、より戦略的な業務に集中できるのがメリットです。
評価制度の運用課題として、マネジメントのリソース不足や負荷などがあれば、効率化を期待できる人事評価システムの導入を検討し、より評価に向き合える体制を構築しましょう。
評価制度の年間運用フロー
評価制度を形骸化させず、継続的に機能させるための年間運用フローの例を4つの期間に分けて解説します。
<評価制度の年間運用フロー>
期初:目標設定と共有面談を行う
期中:進捗確認とフィードバックを行う
期末:自己評価と上司評価を実施する
評価後:評価結果をもとに面談を行う
優れた評価制度の運用は、単発のイベントではなく、期初から期末、次期へとつながる一連のサイクルで成り立っています。各ステップで「何を」「なぜ」行うべきかを理解し、自社の運用プロセスを見直せば、評価制度を運用に乗せられるでしょう。
期初:目標設定と共有面談を行う
評価制度のサイクルは、評価期間の最初に上司と部下による1on1面談からはじまります。ここでは、組織目標に連動した具体的な目標を一緒に決め合意します。
ただ上司から指示されるのではなく、お互いに話し合って目標を決めれば、部下は目標への当事者意識が生まれ、モチベーションが向上するでしょう。
以下に目標設定と共有面談の進め方の例をまとめました。
ステップ | 実施内容 | 上司の役割 | 部下の役割 |
|---|---|---|---|
1. 背景説明 | ・部門目標や会社戦略とのつながりを説明する | ・会社全体の方向性を示す | ・説明を理解する |
2. 目標案の作成 | ・部下自身に目標案を考えてもらう | ・ヒントや方向性を示す | ・自身の役割や期待を踏まえ目標案を作成する |
3. 面談と目標の磨き込み | ・目標案を元に面談を実施する | ・具体的な目標になっているか確認・アドバイスする | ・目標案について説明・議論する |
ここで合意した内容は必ず文書化し、いつでも確認できるように共有することが大切です。
期中:進捗確認とフィードバックを行う
評価期間の中間地点で、目標の進捗確認と課題解決を支援する面談を実施します。問題点を早期に発見して軌道修正することで、部下の目標達成を支援できます。結果として、期末評価での「こんなはずではなかった」という認識のズレを防ぎ、評価への納得感を高めるでしょう。
たとえば、半期評価であれば3ヶ月後に面談を設定します。ここでは評価せず、部下から目標達成の現在地、課題、必要な支援などを話してもらいます。上司は評価者ではなく、部下の成功を支援するコーチとして、「どうすれば壁を乗り越えられるか一緒に考えよう」という姿勢で臨むことが大切です。
期末:自己評価と上司評価を実施する
評価期間の終わりには、まず部下自身が自己評価を行い、その後に上司が評価を実施します。自己評価は、部下が自身の成果と課題を客観的に振り返る機会になります。
上司は、部下の自己評価を理解し評価すれば、認識のズレを把握し、フィードバック面談をより効果的に進められるでしょう。
以下に、期末評価の実施プロセス例をまとめました。
担当者 | 実施内容 | ポイント |
|---|---|---|
部下 | ・評価シートに目標達成度を記入する | ・自身の成果と課題を客観的に振り返る機会となる |
上司 | ・部下の自己評価と行動記録メモを照らし合わせ、客観的事実に基づき評価する | ・期末の印象に左右される近接誤差を避ける |
共通 | ・期中の重要な出来事を記録しておく | ・客観的な事実に基づいた評価のために継続的な記録が重要 |
また、上司の評価はすぐに部下に開示せず、次の評価調整会議を経てから最終決定するフローを徹底し、公平性を保つことが重要です。
評価後:評価結果をもとに面談を行う
評価結果をもとにした面談の主な目的は、評価結果を元に次期の成長課題を明確にし、具体的な育成プランへつなげることです。
評価結果は過去の成果に対する共通認識であり、それをスタート地点として未来の成長に向けた対話をし、評価制度は育成の仕組みとして機能します。
以下に、評価後のフィードバック面談の進め方の例をまとめました。
- 自己評価の確認:部下から自身の評価に対する考えを聞く
- 上司からのフィードバック:上司は評価の根拠を、SBIモデル(状況、行動、影響)などを使い具体的に伝える
- 納得形成と未来志向の対話:評価理由を双方の合意した後に、強みを伸ばす、課題を克服するための行動をすり合わせる
ここで作成した育成プランが、次期の目標設定へとシームレスにつながれば、評価制度の運用は継続的な成長サイクルとなるでしょう。
評価制度を適切に運用する4つのメリット
評価制度の運用を改善すると、企業が得られる具体的なメリットを4つ解説します。
<評価制度を適切に運用する4つのメリット>
従業員の納得感とモチベーションが向上する
会社のビジョンや目標が現場に浸透する
個人の成長を促し人材育成が進む
公平な処遇決定の根拠が明確になる
これらのメリットを組織全体に浸透できるよう、詳細を見ていきましょう。
従業員の納得感とモチベーションが向上する
評価制度の運用が従業員にとって基準が明確でプロセスが公平と感じれば、率直なフィードバックでも受け入れやすくなるでしょう。「何をすれば評価されるか」が明確なため、目標に向かって努力しやすく、前向きにフィードバックを受け止める姿勢が生まれるからです。
自身のビジョンや課題にあった目標を立てられ、達成に向けて努力をしたことやあらわれた成果が正しく評価される制度の運用によって、日々のモチベーション向上を期待できます。
納得感のある評価制度がきっかけになり、モチベーションの高い従業員が増えれば、日々の生産性や効率が上がり、それぞれのスキルアップや企業の成長につながっていくでしょう。
会社のビジョンや目標が現場に浸透する
評価制度を適切に運用すると、経営層のビジョンや事業戦略が、現場社員一人ひとりの業務目標に結びつきやすくなります。
そのためには、期初の目標設定で、会社全体の目標、部門の目標、個人の目標を一貫して連動させることが重要です。社員は自分の仕事が組織全体にどう貢献しているかを常に意識するようになり、日々の業務に明確な意味と方向性を見出すでしょう。
たとえば、会社のビジョンが顧客満足度No. 1の場合、以下のように部門目標が立てられます。
部門 | 具体的な部門目標の例 | 評価制度での取り込み方 |
|---|---|---|
開発部門 | 製品のバグ発生率を10%低減する | 個人の評価項目に「バグ発生率低減貢献度」などとして設定 |
営業部門 | 顧客からの問い合わせに24時間以内に100%返信する | 個人の評価項目に「問い合わせ対応のスピード・完了率」などとして設定 |
カスタマーサポート部門 | 顧客アンケートの満足度を15点向上させる | 個人の評価項目に「顧客満足度向上貢献度」などとして設定 |
このように、評価制度の運用が、ビジョンを現場の具体的な行動に変換する役割を果たします。
個人の成長を促し人材育成が進む
適切に運用された評価制度は、単なる過去の評価を超え、未来の成長を創り出す人材育成の中心となります。評価結果から個々の強みや課題を特定し、具体的な育成プランに落とし込めば、評価と育成が直結します。社員は自身の成長を実感し、主体的に能力開発に取り組むようになるでしょう。
たとえば、評価面談で「交渉力」に課題があるとわかった社員がいるとします。上司と本人が「来期は小規模案件の主担当として顧客折衝を経験する」「交渉術に関する書籍の要約をチーム内で発表する」といった具体的な育成アクションを決めることで、交渉力に対して評価を得るためにするべきことが明確になります。
評価制度に個人のアクションプランや取り組むべきことを盛り込むことで、目指すべきゴールや取り組むべき課題を従業員自身が把握でき、評価面談が成長を実感できる瞬間になるでしょう。
公平な処遇決定の根拠が明確になる
客観的な事実と全社で統一された基準にもとづく評価は、評価者の個人的な感情や印象といった曖昧な要素が排除されます。誰もが納得できる事実とルールにもとづいて昇給や賞与、昇格といった処遇が決定されるため、社員は「成果を出せば正当に評価される」と会社を信頼し、安心して業務に集中できるでしょう。
たとえば、社員から「なぜ私の賞与はAランクなのですか?」と問われた際、上司は評価記録に基づき、「目標Xの達成度はすばらしかった一方、コンピテンシー評価の『チームへの貢献』項目において、チームミーティングでの発言が少なかった点や、他部署からの支援要請に対して自主的な協力を示せなかった点で期待値に届きませんでした。この点がSランクとの差になりました」と具体的に説明できるようになります。
このような対話は、社員の納得感を高め、次の行動への動機付けとなるでしょう。適切な評価制度の運用は、処遇に関する無用な憶測や不満を減らし、労務リスクを低減させる効果もあります。
【関連記事】
評価制度を誤って運用した場合の4つのデメリット
形骸化した評価制度を放置した場合に企業が被るデメリットを4つ解説します。
<評価制度を誤って運用した場合の4つのデメリット>
優秀な人材の離職リスクが高まる
社員のモチベーションが大幅に低下する
管理職や会社への信頼感が失われる
評価にかけた時間や労力が無駄になる
不適切な評価制度の運用は、効果がないどころか、組織に悪影響を及ぼすことがあるため、正しい運用をするために理解を深めましょう。
優秀な人材の離職リスクが高まる
優秀な社員ほど、自身の成果が正当に評価され、それが成長や報酬に結びつくことを望む傾向があります。評価が上司の主観で決まるような環境では、自身の市場価値を理解している優秀な人材は、より公正な評価と機会を求めて他社へと移ってしまうでしょう。
たとえば、高い成果を出しているのに、上司との相性だけで低い評価を受けたトップセールスが、適正な評価を提示した競合他社に転職してしまうケースも考えられます。この状況では、会社は売上と将来のリーダーとなるべき優秀な人材の両方を一度に失うことになります。
優秀な人材にかかわらず、従業員の成果や行動を正しく評価することが人材流出を防ぐために必要な対策です。
社員のモチベーションが大幅に低下する
評価が年に一度の形式的なイベントとなり、努力や成果が報われないと感じると、社員のモチベーションは著しく下がり、生産性が悪化します。評価に反映されない状態が続くと、最低限の仕事しかしなかったり、言われたことだけをこなしたりする姿勢が定着してしまうでしょう。
たとえば、評価面談がわずか15分で、上司からの具体的なフィードバックもなく「来期も頑張って」の一言で終わったケースがあるとします。社員は「この評価プロセスには意味がない」と感じ、次回の目標設定や自己評価への意欲を失うでしょう。
エンゲージメントの低下は、顧客満足度の低下やイノベーションの停滞にも直結するため、早急に納得感のある評価制度への改善が必要になります。
管理職や会社への信頼感が失われる
評価制度は、社員が会社の公平性を測る重要な基準です。評価は社員のキャリアや生活に直結する要素であり、評価基準の不透明さ、評価者の態度、評価結果と処遇の不一致といった矛盾は、社員に「この会社は社員を大切にしない」「言っていることとやっていることが違う」という強い不信感を抱かせます。
たとえば、普段は「君の貢献は大きい」と言ってくれる上司が、評価調整会議での指摘をおそれて無難な評価しかつけないといった事態が起これば、部下は「裏切られた」と感じるでしょう。
このような経験は、部下の上司や会社に対する信頼を完全に失わせ、チームワークを崩壊させます。従業員自身のパフォーマンスが落ちることはもちろん、組織の雰囲気や成果など多方面にネガティブな影響を与えてしまいます。
評価にかけた時間や労力が無駄になる
評価制度のために、目標設定、自己評価、面談、評価シートの集計などを準備するためには、膨大な時間が費やされます。しかし、そのプロセスが業績向上や人材育成に一切貢献しないのであれば、その時間はすべて、本来ならもっと価値のある業務に使えるはずだった機会損失となるでしょう。
たとえば、全社員が評価のために年間平均10時間を費やしていると仮定します。従業員1,000人の企業であれば、年間10,000時間もの労働時間が、リターンのない社内調整業務に消えている計算になります。
評価制度のプロセスを効率化し、その目的を人材育成と業績向上に再設定すれば、費やした時間と労力を何倍ものリターンとして回収が可能になるでしょう。
【関連記事】
評価制度の適切な運用で成長を加速させよう
適切に運用された評価制度は、企業のビジョンと個人の目標をつなぎ、日々の業務に意味を与えます。
公正なフィードバックを通じて信頼を築き、評価結果を具体的な成長機会につなげると、好循環を生み出すでしょう。このサイクルが回れば、社員は自律的に成長し、組織全体のパフォーマンスが向上します。
まずは、現在の評価制度が正しく運用できていない現状や課題を整理することが大切です。課題を把握した上で、従業員が納得し、それぞれのスキルアップや組織の成長につながる評価制度を運用できるように、評価基準の検討や研修の実施など、できることから改善に取り組みましょう。