社内アンケートとは?本音を引き出すコツを解説
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- 社内アンケートとは
- 社内アンケートを導入する目的
- 社内アンケートを導入するメリット
- 社内アンケートとサーベイの違い
- 社内アンケート(従業員満足度調査)
- 従業員サーベイ
- 組織サーベイ
- パルスサーベイ
- エンゲージメントサーベイ
- モラールサーベイ
- 社内アンケートが注目される背景
- 社内アンケートを実施するメリット
- 社内アンケートで本音を引き出すコツ
- 社内アンケートの目的を明確にする
- 社内アンケートの回答リスクを伝える
- 社内アンケートは課題抽出に役立つ質問を設定する
- 社内アンケートをWebで実施する
- 社内アンケートを匿名方式で実施する
- 社内アンケートの作り方のポイント
- アンケート回答者の「心理バイアス」と「正解バイアス」について
- アンケートの導入文の作り方
- アンケートの質問の作り方
- アンケートの回答項目の作り方
- アンケートの質問と回答の順番設定
- 社内アンケートの実施方法
- 社内アンケートの告知と依頼文の作り方
- 社内アンケートの集計と分析方法
- 社内アンケートの回答結果の活用方法
- 社内アンケートの活用例
- 社内アンケートの活用例:幸楽苑ホールディングス
- 社内アンケートの活用例:村田製作所
- 社内アンケートの活用例:大東建託
- 社内アンケートで経営や組織の課題を解決
社内アンケートは、年に1回〜数カ月に1度、従業員を対象として実施され、職場環境に対する従業員の満足度を把握するために実施されます。
社内アンケートを成功させるカギは「従業員の本音」を引き出すことです。
この記事では、社内アンケートのメリット、実施方法や実施の注意点、従業員の本音を引き出す上でカギとなる心理バイアスについて解説します。
▼社内アンケートで組織の課題を解決
社内アンケートとは
社内アンケートは、年に1回〜数カ月に1度、従業員を対象として実施され、職場環境に対する従業員の満足度を把握するために実施されます。
「従業員満足度調査」「ES調査」とも呼ばれ、人事部門が主導となって実施されますが、労働組合によって実施され、労使交渉の場で活用されることもあります。
▼「従業員満足度調査(ES調査)」についてさらに詳しく
【人事基礎】従業員満足度(ES)調査とは?サーベイの種類、生産性向上の要素
社内アンケートを導入する目的
社内アンケートの目的は、経営や組織の課題を把握し、対応策を検討することです。
社内アンケートの目的例
経営方針の従業員への浸透度を確認したい
人事制度、就業規則、福利厚生の内容に対して従業員の意見や考えを把握したい
管理職が職場で部下のマネジメントを適正に実施できているかを確認したい
いずれの場合も、従業員の意見や考えを把握することが目的で、従業員から本音の回答を引き出すことが求められています。
なお、社内アンケートのように人事領域のデータを集め、分析し、分析結果に基づいて、アクションを起こすことを「データドリブン人事(HR)」と言います。
▼「データドリブン人事(HR)」についてさらに詳しく
データドリブン人事(HR)とは?活用例・ツール・手法・本・資格を解説
社内アンケートを導入するメリット
社内アンケートを導入するメリットについて確認してみましょう。
生産性の向上
経営や組織の課題が解決されることにより、従業員の仕事に対するやりがいが大きくなり、生産性が高まります。
定着率の向上
従業員の仕事に対するやりがいが大きくなることにより、離職率が低下し、定着率が高まります。
業績の向上
従業員の生産性が高まることにより、組織力が高まります。組織力の向上は、企業業績に好影響を与えます。
▼「離職」についてさらに詳しく
若手の離職を防ぐには
早期離職の理由と問題とは?離職の原因と中途採用の定着率を上げる方法
社内アンケートとサーベイの違い
社内アンケート(従業員満足度調査)とサーベイの違いについて確認してみましょう。
サーベイは、社内アンケートを「目的別」により細かく分類し定義したもので、「従業員サーベイ」や「組織サーベイ」などがあります。
社内アンケート(従業員満足度調査)
調査の頻度は、年に1回〜数カ月に1度、実施されます。
主に職場環境の改善や、福利厚生の施策検討のために、社員の満足度を把握することがアンケートの目的です。
制度改定やマネジメント改善等、他サーベイの用途も広く包括した調査と位置づけられます。
従業員サーベイ
調査の頻度は、年に1回〜数カ月に1度、実施されます。
社内の人事制度や就業規則を改定する際、人事が仮説として立てた課題を検証するための事実情報を収集することがアンケートの目的です。
▼「従業員サーベイ」についてさらに詳しく
【基礎編】従業員サーベイとは?メリット・デメリットと実施時の注意点を解説
組織サーベイ
調査の頻度は、年に1回〜数カ月に1度、実施されます。
経営目標達成のため、各組織のチームマネジメントが機能しているか、事実情報を収集することがアンケートの目的です。
▼「組織サーベイ」についてさらに詳しく
組織サーベイとは?目的や従業員満足度調査・社内アンケートとの違いを解説
パルスサーベイ
調査の頻度は、1〜5分程度で回答できる簡単な質問を、毎日、週1、月1と定期的に実施されます。
社員満足度向上の施策を打つために、リアルタイムで従業員の意識や状態を把握することがアンケートの目的です。
▼「パルスサーベイ」についてさらに詳しく
パルスサーベイとは?意味や目的と質問項目を解説
エンゲージメントサーベイ
調査の頻度は、年に1回〜数カ月に1度、実施されます。
従業員の仕事に対するモチベーションを向上させるために、現状を把握することがアンケートの目的です。
▼「エンゲージメントサーベイ」についてさらに詳しく
エンゲージメントサーベイとは?質問項目や実施する目的と必要性
モラールサーベイ
調査の頻度は、年に1回〜数カ月に1度、社員のモラールを測定するために実施されます。モラールとは、フランス語で「士気」「意欲」と訳され、組織として目的を達成しようとする意欲、態度を意味します。
社員のパフォーマンスに、どのような要素が影響しているか、事実情報を集めることがアンケートの目的です。
▼「モラールサーベイ」についてさらに詳しく
【基礎編】モラールサーベイとは?メリット、活用方法を解説
社内アンケートが注目される背景
企業の業績向上の鍵となる「従業員エクスペリエンス」を測定するツールとして、社内アンケートが注目を集めています。
従業員エクスペリエンスとは、従業員がその企業で働く上で得られる体験のことです。
従業員エクスペリエンスが高まれば、仕事に対するやりがいが高まります。
仕事に対するやりがいが高まれば、組織力が高まり、業績の向上につながります。
「従業員エクスペリエンス」の向上を目的としたアンケートとして、顧客体験の向上で活用される「eNPS」を活用することができます。
eNPSは親しい友人や身近な人、知人にどの程度おすすめできるかを数値化したものです。0〜10の11段階でスコア化し、企業の推奨者(9〜10)中立者(7〜9)批判者(0〜6)で分類します。
eNPSのスコアは、推奨者の割合から批判者の割合を引いたものになります。
eNPSが高いほうが、より良い従業員エクスペリエンスを提供できているといえます。
▼「従業員エクスペリエンス(EX)」についてさらに詳しく
従業員エクスペリエンス(EX)とは?注目の理由や改善の方法、メリット
社内アンケートを実施するメリット
従業員の満足度を把握するためには、社内アンケートを実施し、従業員の生の声を聞くことが効果的です。
社内アンケートを実施するメリットについて、具体的に確認してみましょう。
立場が異なる従業員の声を収集できる
社内アンケートを実施することで、年齢、役職、職種、雇用形態といった従業員の属性別に、意見や考えを集めることができ、アンケート結果を整理、分析し、課題抽出につなげることができます。
社内コミュニケーションが活性化する
社内アンケートの結果を整理、分析することによって、経営や組織の課題が明確になります。そして、結果を社内で共有することにより、課題解決に向けた、組織内のコミュニケーションの活性化につながります。
社内アンケートで本音を引き出すコツ
社内アンケートを通して、従業員の意見や考えを正確に把握するためには、従業員に本音で社内アンケートに回答してもらう必要があります。
従業員の本音を引き出すコツ
社内アンケートの目的を明確にする
社内アンケートの回答リスクを伝える
社内アンケートは課題抽出に役立つ質問を設定する
社内アンケートをWebで実施する
社内アンケートを匿名方式で実施する
社内アンケートの目的を明確にする
従業員に対して、本音で回答する姿勢を作ってもらうには、実施の目的を明確にした上で、事前に従業員に説明することが重要です。
例えば、従業員の離職が増加傾向にあり、定着率を向上させたいという目的があった場合、「現在の社内での働きがいを確認したい」と社内に明言した上で、社内アンケートを実施すると、従業員から本音の回答を集めることができます。
また、社内アンケートは、事業年度の切り替わりや、年間計画の修正が行われる月に実施するのが望ましいです。事業の節目となる時期をアンケートの実施時期に選ぶことで、従業員に社内アンケートが経営計画達成のための重要なアンケートであると認識させることもできます。
さらに、社内アンケートを実施する際の説明は、社長やアンケート実施部署の管掌役員から従業員に直接、説明することが望ましいです。
役員が従業員に直接訴えかけることによって、社内アンケートの実施に対しての会社の本気度を示すことができ、従業員に本音で回答しなければという義務感を持たせることができます。
社内アンケートの回答リスクを伝える
従業員はアンケート回答のリスクを確認したうえで、回答する姿勢を決めます。
具体的には、匿名の場合でも個人が特定される可能性があるのか、回答内容は人事評価に影響するのかといったことがあげられます。
事前に回答する上で、リスクとなる項目を洗い出し、従業員にどう伝えるのかを検討する必要があります。
社内アンケートは課題抽出に役立つ質問を設定する
従業員の回答から課題を抽出するためには、質問の設計方法が肝になります。
質問の設計には心理学、統計学の学術的な知識が要求されるため、自社内で作成することは難しく、外部の「アンケート」サービスを利用することをおすすめします。
社内アンケートをWebで実施する
社内アンケートの実施方法には、Word等の文書ファイルで実施する方法と、Web上に質問項目を設定し実施する方法、の2種類があります。
Webアンケートは、回答者がストレスなく短時間で回答し、提出まで完了できます。
本音の回答を集めるためには効率的に回答できる「Webアンケート」が望ましい方法です。
社内アンケートを匿名方式で実施する
社内アンケートの実施方式には、回答者の氏名を明らかにして回答する「記名方式」と、氏名を明らかにせず回答する「匿名方式」があります。
従業員は、アンケートに回答する際に、プライバシーが保護されるかを気にすることが多いため、従業員本音の回答を引き出すためにも匿名方式で、アンケートを実施する必要があります。
匿名方式にする場合、社内アンケートの管理方法を事前に従業員に説明することも重要です。
例えば、Webアンケートを採用する場合、回答の閲覧者を限定し、事前に従業員に説明するなど、厳重な管理体制が整備されていることを示す必要があります。
社内アンケートの作り方のポイント
社内アンケートで従業員の本音を引き出すためには、質問の設計方法がポイントになります。特に、回答者の心理バイアスに配慮する必要があります。
心理学、統計学の観点を交え、例文を用いて質問と回答作成のポイントや、注意点について確認してみましょう。
アンケート回答者の「心理バイアス」と「正解バイアス」について
アンケートに回答する際に、起こってしまう恐れのある「心理バイアス」と「正解バイアス」について確認してみましょう。
アンケートが選択式である場合や、回答者が質問への回答に迷った場合、質問文が特定の回答を誘導する内容だった場合に、本音とは異なる回答が発生しやすくなってしまいます。
これを「心理バイアス」と呼びます。
また、回答者が、自分に求められている回答を見越して、本音とは異なる回答をしてしまうことを「正解バイアス」と呼びます。
社内アンケートの場合、例えば回答者である社員が、役職等の自分が社内で置かれている立場から、自分が選ぶべき回答を本音とは別に、無意識に選択してしまうことが考えられます。
本音の回答を集めるためには、「心理バイアス」や「正解バイアス」を発生させないような質問を設計する必要があります。
アンケートの導入文の作り方
アンケートの導入文で、従業員に対して「本音の回答を求めている」ことを明記しましょう。具体的には、アンケートの「目的」と「回答の注意点」についての記載をするようにしましょう。
そうすることで、従業員が役職などの立場から、自分が選ぶべき回答を、無意識に選択する可能性を排除できます。
アンケートの目的(例文テンプレ)
本アンケートは、マネジメントの課題を抽出し、社員にとって働きがいのある職場を作りたい、との思いから作成しています。皆さんの意見を率直に受け止め、有効な改善策につなげたいと考えているので、本音で回答頂きますようお願い申し上げます。
アンケート回答の注意点(例文テンプレ)
全ての質問項目に回答してください。
本アンケートは、回答集計時に回答に一貫性があるか、チェックをかけています。質問を読まずに回答したり、意図的に正解を狙った回答をした場合、全ての回答が無効になります。回答が無効の場合、再回答して頂きますので、本心から回答して頂きますよう、お願いします。
心理バイアスは、回答者の無意識に入り込んでくるものです。
導入文を工夫し、意識的にアンケートに回答するよう従業員を促すことで、バイアスを取り除くことができます。
アンケートの質問の作り方
経営や組織の課題を解決するためには、従業員の働きがいが鍵になります。
従業員の働きがいを決める要因は2つあると言われています。
衛生要因:不満を抑制する要因(給与水準、福利厚生、対人関係、職場環境、就労条件などの労働条件)
動機づけ要因:満足を強化する要因(社内の評価、仕事を通じた成長実感、昇進など)
質問設計は、この2つの要因を軸にして項目を洗い出し、組み立てることで、課題抽出に役立つ回答が得られます。
衛生要因「給与に対する満足度」(例文テンプレ)
質問:あなたは、自分の現在の給与水準に対してどう思いますか?
動機づけ要因「今後の社内でのキャリア」(例文テンプレ)
質問:あなたは、5年後に社内でどのような仕事をしていたいですか?
質問文については、回答を誘導してしまう表現は避けた方がよいでしょう。
例えば、「動機づけ要因」の質問例で「あなたは、現在の職場で5年後も働いていたいですか」という質問を設定します。
この場合、「働いていたい」という前提で質問されていますので、無意識に肯定的な回答をする従業員が増えてしまいます。
なお、社内アンケートで予め解決すべき課題が特定できている場合は、回答対象者を限定し、質問の内容を課題に特化したものに設計する工夫が必要です。
アンケートの回答項目の作り方
アンケートの選択式で「全く満足していない」から「非常に満足している」のように、回答に程度の強弱がある設問形式を「リッカートスケール」と呼びます。
リッカートスケールで、従業員の本音の回答を集めるためには、「選択肢の数」が重要です。
リカットスケールの選択肢は「5つ」が一般的で、これより多すぎても、少なすぎても回答結果の信頼性が担保されません。
質問内容にもよりますが、5つから7つ前後の数で設定するとよいでしょう。
また、選択肢の数は偶数ではなく、奇数にすることが望ましいです。
奇数にすると、質問に対して肯定と否定のどちらでもない「中央値」が生まれ、回答者の心理的負担を減らすことができます。
ですが、中央値の選択肢の表現を工夫しないと、中央値が安易に選択する逃げ道になり、本音の回答が得られない場合があります。
▼「アンケートの設計方法」についてさらに詳しく
社内アンケート調査の進め方!実施目的や、注意点、項目例を紹介
アンケートの質問と回答の順番設定
アンケートの順番が、前の方の質問の回答を前提とした情報が入っていると、回答者はその質問に行った回答を前提に、以降の質問に臨みます。
例えば「現在の給与水準に対してどう思いますか?」という質問が前にあり、「上司のあなたの仕事に対する評価をどう思いますか?」という質問が、その後にあったとしましょう。
この場合、回答者が前の質問に対して、給与水準が「低いと思う」と回答すると、それが前提となって、続く後の質問に評価が「低いと思う」と無意識に回答してしまう可能性が高くなります。
全ての質問と回答に対して、順番設定の影響が出ないよう、アンケートを設計することは難しいですが、前提なく回答してほしい質問がある場合は、順番設定に注意しましょう。
アンケートの質問と回答は、専門知識が要求されるため、いちから作成することは難しいです。
外部のアンケートサービスのテンプレートを元に、自社用にカスタマイズすることをおすすめします。
どうしても自社で対応せざるを得ない場合、パイロット版を作成して、従業員の意見を正しく引き出せるか、本番前のテストを実施するようにしましょう。
社内アンケートの実施方法
社内アンケートの告知と依頼文の作り方から、アンケート結果の集計と分析、活用までの全体の流れについて確認してみましょう。
従業員の本音を引き出すためには、随所で工夫が必要です。
社内アンケートの告知と依頼文の作り方
社内アンケートの従業員への告知と依頼文のポイントについて確認してみましょう。
アンケートの告知
告知はメールで行う
添付ファイル:アンケートがWord等の文書ファイルの場合は添付する
回答フォーム:Webアンケートの場合は回答フォームのURLを文中に記載する
アンケートの依頼文
アンケート実施の目的、活用方法、開示有無、実施方式(匿名・記名)、回答に要する目安時間を明記する
回答期限を強調する
社内アンケートの集計と分析方法
集計については、経営や組織の課題を抽出し、現状を正確に把握するために、対象者の「8割以上の回答率」を目指す必要があります。
アンケートの回答期限までに未回答者へ、リマインド通知を複数回実施することにより、回答率向上につながります。
分析については、過去アンケートの結果と比較してどうだったかの定点観測を行わなければ、正確に読み解くことは難しいです。
また、分析結果の検証のために、職場への回答結果に基づくヒアリングを実施することが重要です。
正確な分析を行う為にも、アンケートの回答結果は従業員に開示し、協力してもらうことが望ましいでしょう。
社内アンケートの回答結果の活用方法
アンケートの分析結果が出たら、課題を抽出し、経営陣と共有します。
課題が経営方針や人事施策などの、全社に関わるものであれば、経営陣と対応の方向性を議論し、分析結果とともにその内容を従業員に伝えます。
一方、課題が管理職のマネジメントなどの、部署固有のものであれば、従業員への通知は分析結果までにとどめ、対応策については各部署で検討してもらいます。
また、アンケートの実施から課題の抽出、対応策の検討までに時間が空いてしまうと、従業員のアンケートに対する姿勢が消極的なものになり、継続的な実施が難しくなってしまいます。
スピード感をもって対応策までつなげるために、アンケート実施部門が全てを抱え込むのではなく、職場も巻き込みながら、最適な役割分担を検討して進めるようにしましょう。
社内アンケートの活用例
社内アンケートの企業での活用例について確認してみましょう。
社内アンケートの活用例:幸楽苑ホールディングス
株式会社幸楽苑ホールディングス(業種:飲食 / 社員数:1,200名)では、社内アンケートを全社で実施し、従業員の今後のキャリアや、店舗運営に関する意見を集約し、結果を「人事異動施策」や「事業の業務改善」に役立てています。
社内アンケートの活用例:村田製作所
株式会社村田製作所(業種:電気機器 / 社員数:9,500名)では、社内アンケートをデジタルマーケティングやサービスに取り組む部署において、「1on1ミーティングの改善プロジェクトの一環」として実施しています。
1on1ミーティングでの、上司と部下との対話の仕方と部下の満足度の相関を検証し、検証結果をミーティングの品質改善に役立てています。
▼「1on1ミーティング」についてさらに詳しく
1on1とは? 従来の面談との違いや効果を高めるコツ
1on1ミーティング入門書
社内アンケートの活用例:大東建託
株式会社大東建託(業種:不動産 / 社員数:8,700名)では、社内アンケートを全社で実施し、従業員の「働きがい」と「仕事のやりがい」について意見を集約し、結果を「将来の人事施策の検討」に役立てています。
毎年、回答結果を経営陣に報告した後、従業員に開示しています。
また、回答結果を受けて、各職場が来期の「改善策と行動計画を策定」し、1年のスパンでPDCAを回しています。
社内アンケートで経営や組織の課題を解決
社内アンケートは「従業員満足度調査」「ES調査」とも呼ばれ、年に1回〜数カ月に1回、従業員を対象として実施される調査です。
職場環境に対する従業員の現状の満足度を把握するために実施され、経営や組織の課題を把握し、対応策を検討することに活用されます。
社内アンケートを効果的に活用し、経営や組織の課題を解決できれば、従業員の生産性、定着率が向上し、企業の業績向上につながるでしょう。
「HRBrain 組織診断サーベイ」では、独自の設問設計によって、組織改善を素早く、的確に実現します。
サーベイの3つの壁を突破する方法
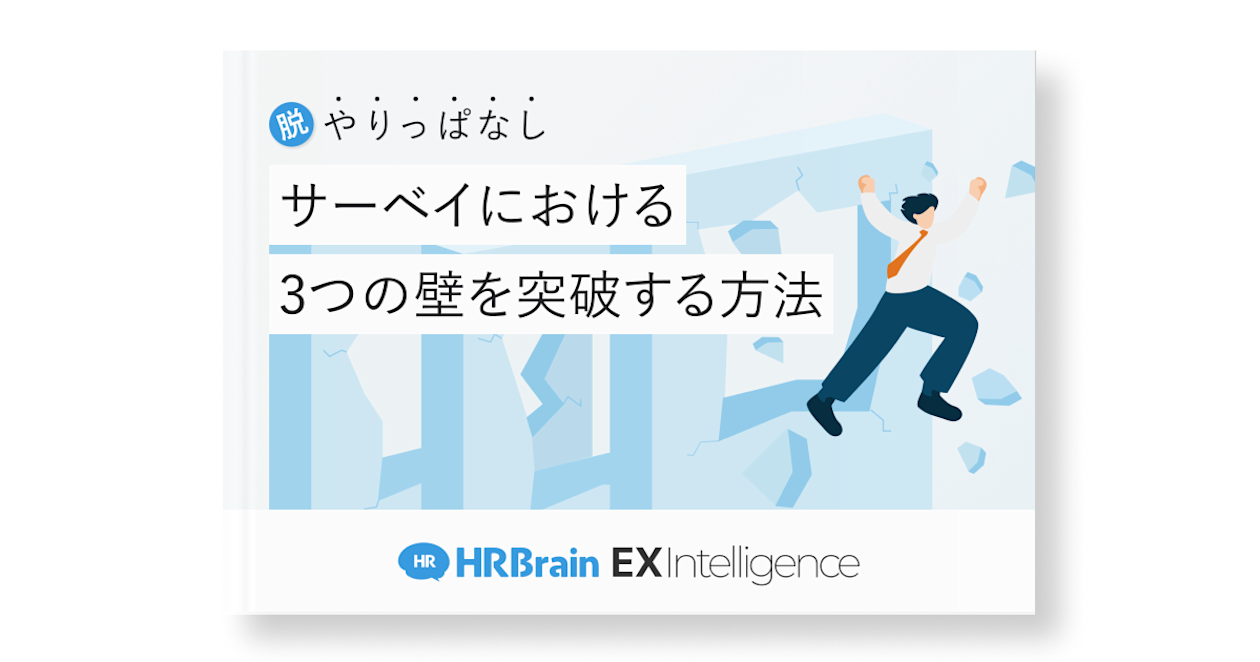
従業員の離職防止やエンゲージメント向上に取り組む多くの企業で、組織診断サーベイやエンゲージメントサーベイが導入されています。
一方で、組織改善のための施策検討や実行までできている企業は、まだ少ないのではないでしょうか。
サーベイにおける3つの壁や成功の秘訣などについて解説します。
この資料で分かること
サーベイの3大あるある病
組織改善を阻む3つの壁
サーベイの成功の秘訣とは?
組織診断サーベイ「EX Intelligence」とは







