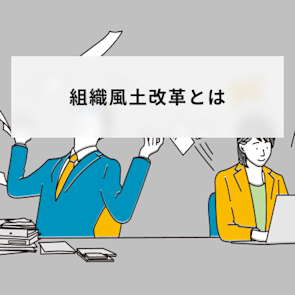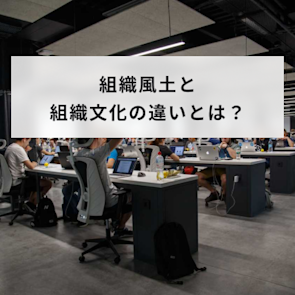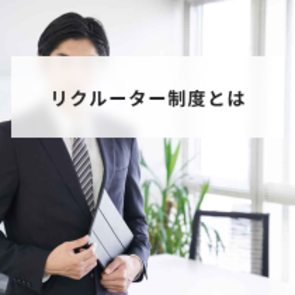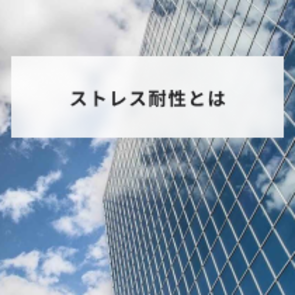ジョブディスクリプション(職務記述書)とは?書き方や必要性と注意点について解説
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- ジョブディスクリプション(職務記述書)とは
- ジョブディスクリプションの目的
- ジョブディスクリプションでの日本企業と海外企業との違い
- ジョブディスクリプションの活用シーン
- ジョブ型雇用制度の導入時の参考資料
- ジョブ型雇用での求人票の作成
- 社内の職務整理や人材管理
- ジョブディスクリプションの作成方法
- 職務分析の実施
- ジョブサイズとジョブグレードの決定
- ジョブディスクリプションをデータベースに登録する
- ジョブディスクリプションを更新する
- ジョブディスクリプションの注意点
- 業務実態をヒアリングする
- ジョブディスクリプションに基づいた評価を実施する
- ジョブディスクリプションと人材育成
- ターゲットジョブに対する能力開発
- ジョブディスクリプションの作成と運用は人事管理システムで
ジョブディスクリプションとは、日本語で「職務記述書」と呼ばれ、その職務に対する仕事内容、役割、期待される成果、直属の上司など「職務を定義したもの」を指します。
また、ジョブディスクリプションは「ジョブ型雇用」において必須のツールです。
この記事では、ジョブディスクリプションについて、書き方や必要性、ジョブディスクリプションの注意点や人材育成との関係性などについて解説します。
ジョブディスクリプションの作成に役立つ「タレントマネジメントシステム」
ジョブディスクリプション(職務記述書)とは
ジョブディスクリプションとは、日本語で「職務記述書」と呼ばれ、その職務に対する仕事内容、役割、期待される成果、直属の上司などが書かれています。
一言で言えば、職務を定義したものがジョブディスクリプションです。
また、ジョブディスクリプションは「ジョブ型雇用」において必須のツールです。
▼「ジョブ型雇用」についてさらに詳しく
ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型雇用との違いやメリットとデメリットを解説
ジョブディスクリプションの目的
ジョブディスクリプションの目的は、その仕事(職務)の責任範囲を明確化するとともに、仕事内容に応じた報酬を支払う根拠を提示することです
職務を定義し仕事内容にマッチした人材を採用するという考え方は、会社にマッチする人材を採用するというメンバーシップ型雇用を採用する企業が多い日本では、あまり馴染みがないかも知れません。
しかしジョブ型雇用制度が主流の海外では、仕事内容と報酬が厳密に連動しているため、職務を定義することは報酬を支払う根拠として重要な取り組みなのです。
ジョブディスクリプションでの日本企業と海外企業との違い
日本企業でも株式会社日立製作所や富士通株式会社を始め、ジョブ型雇用制度を導入する会社が増えています。
ジョブ型雇用制度は、従来の人を起点としたメンバーシップ型雇用制度と異なり、業務を起点に人材を雇用する制度です。
業務を起点に雇用するということは、会社の中にどのような業務があり、その業務を遂行するためにはどのような能力を持った人材が必要かを定義することです。
では、日本企業と海外企業での、ジョブディスクリプションがどのように異なるのか確認してみましょう。
海外の企業では業務に対して報酬が決まります。
報酬には仕事の難易度、業務量が加味されるため、ジョブディスクリプションには細かい業務内容が記載されています。
また、従業員はジョブディスクリプションに書かれていない仕事はやらなくていいことになっています。
例えば、従業員に書類をコピーすることを頼んだ際に、「ジョブディスクリプションに書かれていない」という理由で仕事を断られるくらい、ジョブディスクリプションは従業員にとって厳密なものです。
一方で、日本企業でジョブディスクリプションを運用した場合、仕事の属人化が進み日本企業の良さである助け合いの文化が失われる可能性があります。
日本企業でジョブ型雇用制度を導入する際は、海外のように厳密な運用ではなく、ある程度の自由度と柔軟性を持たせたジョブディスクリプションを設定すると良いでしょう。
ジョブディスクリプションの活用シーン
ジョブディスクリプションの活用シーンについて確認してみましょう。
ジョブディスクリプションの活用シーン
ジョブ型雇用制度の導入時の参考資料
ジョブ型雇用での求人票の作成
社内の職務整理や人材管理
ジョブ型雇用制度の導入時の参考資料
ジョブ型雇用制度を導入する企業にとってジョブディスクリプションは必要不可欠なツールです。
しかし、ジョブ型雇用を導入するにしても何から検討すればよいかわからないという場合も多いです。
一度社内で自社におけるジョブディスクリプションやジョブ型雇用はどのようなものかをまとめ、議論すると良いでしょう。
ジョブ型雇用での求人票の作成
ジョブディスクリプションの作成が必要になるのはジョブ型雇用制度を導入する時だけではありません。
特に、中途採用において求人票の作成を行う際にも必要です。
中途採用では、仕事内容に合致する人材を採用する必要があります。
よくある中途採用の失敗事例に、仕事内容を曖昧に定義したことで、採用のミスマッチが起きてしまうということです。
ジョブディスクリプションを使用して、採用する職種の仕事内容を整理すれば、求人票の内容をより具体的に記載することができます。
社内の職務整理や人材管理
社内にどんな仕事が存在しているのか、業務の棚卸をする際にもジョブディスクリプションは有効です。
従業員に各自の仕事内容を記入してもらえば、社内の仕事が把握できます。
その上で不要な業務を整理することもできるでしょう。
また、社内の人材管理ツールとしてもジョブディスクリプションは活用できます。
▼「人材管理」についてさらに詳しく
【人材管理:完全版】人事が押さえておきたいマネジメントとは?システム導入まで
ジョブディスクリプションの作成方法
ジョブディスクリプションの作成方法について確認してみましょう。
ジョブディスクリプションの作成方法
職務分析の実施
ジョブサイズとジョブグレードの決定
ジョブディスクリプションをデータベースに登録する
ジョブディスクリプションを更新する
職務分析の実施
ジョブディスクリプションはひとつひとつの仕事内容を定義したものです。
つまり、ジョブディスクリプションの作成には、ひとつひとつの職務がどのような業務内容なのかを分析する必要があります。
職務分析の方法には「面接法」「観察法」「記述法」の3つの分析方法があります。
職務分析の方法「面接法」
面接法とは、人事担当者が従業員全員と面談を行って全ての仕事を記述する方法で、客観的に職務定義ができるメリットがある一方で、担当者の負担が大きいというデメリットがあります。
職務分析の方法「観察法」
観察法とは、職場で上司や人事担当者が実際の仕事を観察して職務定義を行う方法で、観察法は客観的かつ正確で詳細な職務定義ができるメリットがある一方で、面接法よりも担当者の負担がさらに大きくなるというデメリットがあります。
職務分析の方法「記述法」
記述法とは、その職務を担当する従業員自身が自分の業務内容をジョブディスクリプションに入力する方法で、従業員に入力を依頼するため、人事担当者はジョブディスクリプション作成の手間が省けるメリットがある一方で、客観的な情報ではないため、業務内容の抜け漏れや他の職務との重複が発生する可能性があるというデメリットがあります。
記述法では、予め入力内容のガイドラインやテンプレートを用意し、記述内容を揃えると良いでしょう。
ジョブサイズとジョブグレードの決定
職務分析が完了したら、「報酬水準」を決定するために、その職務の「ジョブサイズ」と「ジョブグレード」を決めます。
ジョブサイズとは、その職務の仕事内容の難易度、業務量、会社への貢献度から総合的に判定した仕事の「レベル」を指し、一般的にジョブサイズが大きいほど報酬が高くなります。
ジョブグレードとは、ジョブサイズを基準に、さらに役職や職位を加えて報酬レンジを定めたもので、企業によって制度が異なりますが、例えば、ジョブサイズ「1」でジョブグレード「3」の場合の年俸が「〇〇〇万円」というように定められます。
具体的には、同じ「部長」でも事業部門の部長と総務部長では会社への貢献度や仕事の難易度が異なります。
この場合、「部長」というジョブグレードに対して、「ジョブサイズ」によって報酬が決定されます。
このように、自社の状況に合わせながらジョブサイズ、ジョブグレードの両方またはいずれかを導入するようにしましょう。
ジョブディスクリプションをデータベースに登録する
ジョブディスクリプションを作成したら、どの部門にどの仕事が存在するのかを明確に整理しておく必要があります。
万が一、欠員が出た場合はどの職務に補充が必要なのか、すぐに分かるようにしておきましょう。
また、職務と報酬を連動させる必要もあります。
こうしたジョブディスクリプションの整理と報酬との連動は、人事管理システムを活用すると良いでしょう。
▼「人事管理システム」についてさらに詳しく
人事情報管理システムとは?業務効率化の方法、ポイントやメリットを紹介
ジョブディスクリプションを更新する
ジョブディスクリプションは一度作成したら終わりではありません。
仕事内容は経営環境の変化によって変わります。
そのため、少なくとも年単位でジョブディスクリプションの見直しと更新を行いましょう。
ジョブディスクリプションの更新方法として、「記述法」が最も簡単です。
従業員に既存のジョブディスクリプションを確認し、更新する部分がないかを申告してもらいます。
もしくは上司による年次目標設定の面談の際に、更新内容を上司から確認してもらうのも良いでしょう。
適正に報酬を支払うためには、常に最新のジョブディスクリプションがあることが欠かせないため、必ず更新作業を行うようにしましょう。
ジョブディスクリプションの注意点
ジョブディスクリプションの注意点について確認してみましょう。
ジョブディスクリプションの注意点を理解していないと、最悪の場合、従業員のモチベーションの低下や離職につながってしまう場合があります。
ジョブディスクリプションの注意点
業務実態をヒアリングする
ジョブディスクリプションに基づいた評価を実施する
業務実態をヒアリングする
業務を取り巻く環境は変化し続けるため、気づけばジョブディスクリプションと業務内容が乖離してしまっているという場合もあります。
また、仕事内容が同じでも、会社の方針変更によりジョブサイズが変更になることもあります。
今までは貢献度が低かった仕事が、新しい市場を開拓することになったことで重要な仕事になることもあり得ます。
ジョブディスクリプションと実際の業務が乖離してしまうと、報酬と業務内容との乖離が発生し、従業員のモチベーションが低下する可能性があり、最悪の場合、離職につながってしまいます。
離職防止のためにも、常に業務実態をヒアリングしてジョブディスクリプションを最新の状態に維持するようにしましょう。
▼「モチベーション」につていさらに詳しく
仕事のモチベーションを上げる方法とは?元人事が実体験をもとに解説
▼「離職」につていさらに詳しく
離職の原因TOP3!特に気をつけたい若者・新卒の離職理由も詳しく解説
原因と対策を考える若手の離職を防ぐためには
▼「離職防止」についてさらに詳しく
離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説
ジョブディスクリプションに基づいた評価を実施する
ジョブ型雇用制度は、ジョブディスクリプションに基づいて評価を行います。
そのためジョブディスクリプションには、その仕事に対して期待される成果を明記する必要があります。
複数の業務内容がある場合は、「Aの仕事に対しては報酬の30%、Bの仕事に対しては報酬の70%」といったように、それぞれの業務の比重を決めて報酬を決定します。
もし業務内容が変更になり、期待される成果の比重が変わった際はすぐにジョブディスクリプションを更新しなければなりません。
更新を怠ってしまった場合、適切な評価ができなくなってしまいます。
優秀人材の離職を防止するためにも、ジョブディスクリプションは常に最新の状態にしておくようにしましょう。
ジョブディスクリプションと人材育成
ジョブディスクリプションとジョブ型雇用では、人材育成が重要です。
日本企業ではこれまで、メンバーシップ型雇用制度を背景に「職能等級制度」が運用されてきました。
まず人を採用して、育成したうえで最適な仕事へ配置する人材活用の考え方です。
そのため、日本企業では人材育成が人材マネジメントの中心的な取り組みであることが少なくありません。
また、日本銀行副総裁の中曽氏のレポートによれば、日本は欧米と比べ人材の流動性が低いため、社外から人材を調達することはまだまだ有効な手段ではありません。
そのため、当面は人材育成を重視した日本ならではのジョブ型雇用制度が運用されると考えられます。
(参考)日本銀行副総裁 中曽宏「日本経済の底力と構造改革」
▼「人材育成」についてさらに詳しく
人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説
失敗しない人材育成ハンドブック
▼「人材マネジメント」についてさらに詳しく
【人材管理:実践・事例編】人材マネジメントとは?メリット・課題・導入のポイント
ターゲットジョブに対する能力開発
日本型ジョブ型雇用制度では、社内での能力開発が重視されます。
まず対象となる職務として「ターゲットジョブ」を決め、ターゲットジョブに対して不足しているスキルや知識を従業員に習得させていきます。
こうすることで、雇用の流動性が低い日本企業でジョブ型雇用制度を導入しても、社内で人材を補充できるようになります。
特に、ジョブ型雇用制度の導入初期には、設定されたジョブに対して人材が不足する可能性が高くなります。
そのため初期から不足するジョブをターゲットジョブとして、一定数の人材を育成する取り組みを行っておくことが必要になります。
ジョブディスクリプションの作成と運用は人事管理システムで
ジョブディスクリプションはジョブ型雇用において必須のツールであるだけでなく、「従業員の業務の棚卸」や「中途採用での求人票の作成」「自社に不足している人事の把握」「従業員の人材育成」などにも役立ちます。
また、ジョブディスクリプションはジョブ型雇用制度を導入している企業にとって、「報酬の決定」のベースとなるもののため、常に更新を行い最新の状態を保っておく必要があります。
ジョブディスクリプションは、作成する側の手間は非常に掛かることと、常に最新の情報を保っておかないと、ジョブディスクリプションに記載されている業務内容と報酬とのとの乖離が発生してしまい、従業員のモチベーションの低下うや離職につながってしまう恐れがあります。
そのため、ジョブディスクリプションの作成や運用には「人事管理システム」を使用することをおすすめします。
「HRBrain タレントマネジメント」は、ジョブディスクリプションに必要な従業員ひとりひとりの業務内容をはじめ、あらゆるデータを一元管理し可視化します。
従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、研修などの育成履歴や、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、1on1やフィードバックなどの面談履歴、OKRなどの目標設定と進捗管理などを一元管理します。
従業員データをもとに、適材適所の人材配置や、自社に不足しているスキルや人材のピックアップも可能です。
HRBrain タレントマネジメントの特徴
検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現
運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。
柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を
従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。
人材データの見える化も柔軟で簡単に
データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。
▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく
【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説
タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで
▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ
【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ