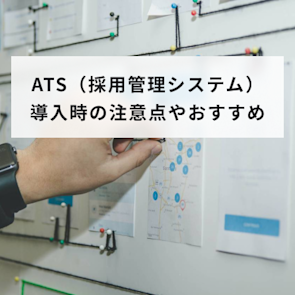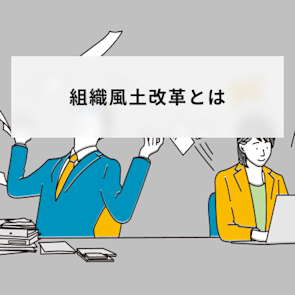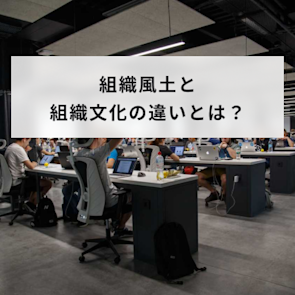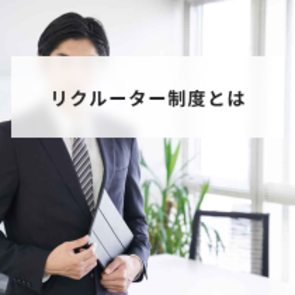ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型雇用との違いやメリットとデメリットを解説
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- ジョブ型雇用とは
- ジョブ型雇用が広まった背景
- ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い
- ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用のメリットとデメリット
- ジョブ型雇用のメリット
- ジョブ型雇用のデメリット
- メンバーシップ型雇用のメリット
- メンバーシップ型雇用のデメリット
- ジョブ型雇用と中途採用
- ジョブ型雇用で働き方はどう変わるのか
- 成果主義型の働き方の浸透
- 仕事の専門化が進む
- ジョブ型雇用の取り入れ方のポイント
- 管理職から取り入れていく
- 必ずしも全従業員に適用しない
- 業種や業界特性にあわせる
- ジョブ型雇用の導入は自社の状況を考えてからに
ジョブ型雇用は、「仕事に対して人材をあてはめる」考え方で、大企業を中心に日本でも導入する企業が増えてきています。
この記事では、ジョブ型雇用の意味やメンバーシップ型雇用との違い、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用それぞれの持つメリットとデメリットの比較、ジョブ型雇用を取り入れる際のポイントについてわかりやすく解説します。
ジョブ型雇用に必須のジョブディスクリプションの作成に役立つ「タレントマネジメントシステム」
ジョブ型雇用とは
ジョブ型雇用とは、簡単に言えば会社が定義した仕事内容に合致する人材を雇用することです。
ジョブ型雇用では、仕事内容の1つ1つが「職務記述書(ジョブディスクリプション)」によって規定されます。
ジョブ型雇用は、主に欧米企業を中心に、海外で最も普及している雇用形態です。
▼「ジョブディスクリプション」についてさらに詳しく
【人事監修テンプレ】ジョブ型雇用時代のジョブディスクリプションの作成法
ジョブ型雇用が広まった背景
新型コロナウィルスの影響により、急速にテレワークが普及しました。
テレワークでは、物理的に仕事のプロセスの管理が難しいという特徴があり、成果を基準とした評価方法へ変更する企業が増えてきました。
成果を評価基準にする場合、仕事内容とその仕事の達成基準が明確である方が評価しやすいと言えるでしょう。
そのため、新たな働き方に対応する組織運営方法の一環としてジョブ型雇用制度へシフトする企業が増えています。
▼「テレワーク」についてさらに詳しく
テレワークとリモートワークと在宅勤務って何が違う?言葉の意味と違いを解説!
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い
ジョブ型雇用に対して、これまでの日本企業での雇用制度は「メンバーシップ型雇用」と呼ばれる雇用制度が主流でした。
メンバーシップ型雇用とは、日本企業で戦後から取り入れられてきた雇用制度です。
メンバーシップ型雇用では、会社が市場からまず人材を採用し、入社後に能力開発を行ったうえで職場に配置します。
戦後の高度経済成長期に人材を確保するために発達した制度のひとつです。
メンバーシップ型雇用は、「人材を仕事にあてはめる」考え方です。
それに対して、ジョブ型雇用は、「仕事に人をあてはめる」考え方です。
メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用は正反対の考え方といえるでしょう。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用のメリットとデメリット
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用、それぞれのメリットとデメリットについて確認してみましょう。
ジョブ型雇用のメリット
ジョブ型雇用のメリットは、仕事内容と人材のスキルが合致することで、「採用のミスマッチを防げる」ことです。
また、仕事の範囲が決まっているので企業は「報酬設計が容易」であり、雇用される側も「報酬に納得感が生まれやすい」というメリットがあります。
さらに、必要な仕事に対して人材を採用するため、「人員数を適正化」することができ、仕事が減ればリストラをし、仕事が増えれば人員を増やすというコントロールがしやすくなります。
ジョブ型雇用のデメリット
ジョブ型雇用のデメリットは、「新たな人材の採用が難しくなる」ことです。
ジョブ型雇用は前提として、企業が求める人材が市場に存在していることが必要です。
欧米では専門人材の労働市場が発達しているため、必要な人材を採用することが容易です。
しかし日本ではまだまだ労働市場が発達しておらず、特定の仕事に特化した専門性のある人材が少ないのが実情です。
また、ジョブ型雇用には原則「すべての仕事に職務記述書が必要」になります。
職務記述書はジョブディスクリプションとも言われ、仕事内容と役割を詳細に定義した書類です。
当然、仕事内容が変われば職務記述書も変更しなければならず、「職務記述書の管理工数の手間が増える」こともデメリットの1つです。
メンバーシップ型雇用のメリット
メンバーシップ型雇用のメリットは、「人材を安定的に確保できる」ことです。
メンバーシップ型雇用では、人材を採用してから育成するため、長期的な雇用に適しています。
また、長期的に人材を雇用することで、人材を安定的に確保することができます。
従業員に企業理念や仕事の進め方を教え込むことで、その企業特有のスキルが身につき、離職防止にも役立つでしょう。
雇用される側も会社に所属することで賃金がもらえるため、安心して働くことができます。
▼「企業理念」についてさらに詳しく
企業理念と経営理念の違いは?それらを社内に浸透させる方法について
▼「離職防止」についてさらに詳しく
離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説
原因と対策を考える若手の離職を防ぐためには
メンバーシップ型雇用のデメリット
メンバーシップ型雇用のデメリットは、「仕事が人員の数だけ増える」ことです。
メンバーシップ型雇用は、人材に対して仕事をアサインするため、管理しなければ仕事が人員の数だけ増えることになります。
仕事が急増している成長期は適していますが、経済や会社の成長が鈍化している時には不向きです。
また、人材育成を行ってから人材配置をするため、ジョブ型雇用よりも人材が能力を発揮するまでの時間的コストが発生します。
さらに、人材を採用することから始まるため、採用した人材が業務に適していないことが後から判明するリスクが高くなります。
▼「人材育成」についてさらに詳しく
人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説
▼「人材配置」についてさらに詳しく
適材適所を実現する「人材配置」とは?実践的な方法とポイントを人事目線で解説
ジョブ型雇用と中途採用
日本企業では、以前から中途採用に関しては「特定の仕事内容に対しての人材募集」を行ってきました。
中にはジョブ型雇用に近い形式での採用も多いでしょう。
しかしその場合でも、通常の雇用制度とは別枠で契約社員といった形式をとったり、最初はジョブ型で採用しても後から「ジョブローテーション」を行うメンバーシップ型の運用を行ったりしていました。
つまり、メンバーシップ型雇用の運用に例外を設けることで、中途採用で即戦力を採用していたケースが多いのです。
▼「ジョブローテーション」についてさらに詳しく
ジョブローテーションの基本!効果や仕組みを現役人事が解説
ジョブ型雇用で働き方はどう変わるのか
大企業を中心にジョブ型雇用を導入する流れが広がっています。
ジョブ型雇用が普及すると、私たちの働き方はどのように変わるのか確認してみましょう。
成果主義型の働き方の浸透
ジョブ型雇用が普及すると、「成果主義型の働き方の浸透」が実際に進むでしょう。
「実際に」という理由は、現在でも表向きは成果主義を取り入れている企業が多いためです。
大企業では成果主義と言いながら実質的には「年功序列型」の人事制度を続けてきました。
なぜなら、これまでは企業の中で仕事内容が明確に定義されておらず、成果に対する評価が難しかったからです。
しかし、ジョブ型雇用が導入されることで仕事内容に対する成果と報酬が実際に連動するようになります。
そのため、成果主義の働き方が日本でも広がっていくと考えられます。
▼「成果主義」についてさらに詳しく
成果主義と能力主義の相違点を知る。概要や導入のポイントを解説
▼「人事制度」についてさらに詳しく
人事制度設計のポイントとは!設計方法を3つの人事制度を交えて解説
仕事の専門化が進む
ジョブ型雇用が普及すると、大企業では「仕事の専門化が進む」でしょう。
これまで日本企業ではジョブローテーションを中心としたOJTによって、ジェネラリストを育成してきました。
しかし、ジョブ型雇用を導入することで、仕事が専門化することになります。
企業では一定数の人材が今後スペシャリストになっていくと考えられます。
▼「OJT」についてさらに詳しく
OJTとは?OFF-JTとの違いや意味と教育方法をわかりやすく解説
ジョブ型雇用の取り入れ方のポイント
実際にジョブ型雇用を取り入れる際の、取り入れ方のポイントについて確認してみましょう。
ジョブ型雇用の取り入れ方のポイント
管理職から取り入れていく
必ずしも全従業員に適用しない
業種や業界特性にあわせる
管理職から取り入れていく
ジョブ型雇用は管理職から取り入れていくのがよいでしょう。
労働組合に守られている一般従業員と比べ、比較的容易にジョブ型雇用を導入することができます。
また、管理職は一定の専門知識が求められるため、ジョブ型雇用に適していると考えられます。
必ずしも全従業員に適用しない
ジョブ型雇用は仕事を職務記述書で定義するため、職務記述書に書かれていない仕事はやらないことになるため、本当はやるべき仕事が漏れる可能性があるでしょう。
一定数の従業員を「万能選手」として、メンバーシップ型雇用を継続すれば、仕事の漏れを防ぐことができます。
全従業員にジョブ型雇用を適用するべきかどうかは、自社の業務事情にあわせて検討するようにしましょう。
業種や業界特性にあわせる
業種や業界によっては、ジョブ型雇用が適さない場合があります。
長期的に育成が必要なものづくりの仕事や、ベンチャー企業や新設部署などで幅広い業務に対応する必要がある場合です。
こうした業務や部署では、引き続きメンバーシップ型雇用を続ける方が企業側にとって人材活用の柔軟性が高まるでしょう。
ジョブ型雇用の導入は自社の状況を考えてからに
ジョブ型雇用は、「仕事に対して人材をあてはめる」考え方で、「人材を仕事にあてはめる」考え方のメンバーシップ型雇用とは正反対のものになります。
ジョブ型雇用では、仕事に対して採用を行うため、採用後のミスマッチを防ぐことができるというメリットがあります。
ジョブ型雇用は時代の変化に合わせた新たな「人事制度改革」として日本で避けては通れない変化のひとつです。
一方で、メンバーシップ型雇用もデメリットばかりではありません。
長期的に育成が必要なものづくりの仕事や、ベンチャー企業や新設部署などで幅広い業務に対応する必要がある場合には、メンバーシップ型雇用の方が向いています。
ジョブ型雇用を導入する際は、自社の状況を考えながら取り入れていきましょう。
「HRBrain タレントマネジメント」は従業員ひとりひとりのあらゆるデータを一元管理し可視化します。
従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、研修などの育成履歴や、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、1on1やフィードバックなどの面談履歴、OKRなどの目標設定と進捗管理などを一元管理します。
従業員データをもとに、適材適所の人材配置や、自社に不足しているスキルや人材のピックアップも可能です。
HRBrain タレントマネジメントの特徴
検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現
運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。
柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を
従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。
人材データの見える化も柔軟で簡単に
データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。
▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく
【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説
タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで
▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ
【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ