サーベイとは?意味や種類、2つの実施方法、4つの成功事例を解説
組織状態の把握から分析・課題抽出までワンストップで実現
- サーベイとは
- サーベイとアンケートの違い
- サーベイとリサーチの違い
- サーベイとアセスメントの違い
- サーベイの7つの種類
- エンゲージメントサーベイ
- モラールサーベイ(従業員満足度調査)
- 組織診断サーベイ
- ストレスチェック
- コンプライアンス意識調査
- アセスメントサーベイ
- 360度サーベイ(360度評価サーベイ)
- 組織サーベイの2つの実施方法
- センサス
- パルスサーベイ
- サーベイを実施する3つのメリット
- 従業員エンゲージメントの向上につながる
- 優先的に改善すべき課題がわかる
- 経営層と現場のギャップが明らかになる
- サーベイを実施する4つのデメリット
- サーベイの実施コストがかかる
- 本音を引き出せない場合もある
- 従業員の不満につながる可能性がある
- 改善策につなげる力が必要になる
- 効果的なサーベイ実施の9ステップのやり方
- 1. 実施目的を明確にし、「何を知りたいか」を設計に落とし込む
- 2. 設問数はシンプルかつ要点を絞り、回答負荷を最小限にする
- 3. 回答データの守秘性を担保し、安心して意見を表明できる環境をつくる
- 4. 回答しやすいタイミングで実施し、全社的な参加を促す
- 5. 集計・分析の体制を整え、スピーディにフィードバックを行う
- 6. 結果を公開し、組織として「聴く姿勢」を示す
- 7. 結果をもとに優先課題を設定し、具体的な改善策に落とし込む
- 8. アクションの進捗を定期的に共有し、信頼と納得感を醸成する
- 9. 継続実施を前提にし、経年比較や効果検証に活かす
- サーベイ実施時の9つの注意点
- 設問の目的と意図を明確にしないまま設計しない
- 設問数が多すぎたり抽象的すぎると回答率が下がる
- 回答者の保護や守秘性が不十分だと、本音を引き出せない
- 回答の自由度が低すぎると重要な声を見落とす
- 個々の回答の取り扱いで信頼を損なわない
- 結果を放置すると「形だけのサーベイ」と捉えられる
- 分析・改善に活かす体制がないまま実施しない
- サーベイの目的や結果を社内に共有しないと不信感が残る
- 単発で終わらせず、継続的な改善サイクルに組み込む必要がある
- サーベイ導入の4つの成功事例・ツール活用事例
- タレントマネジメント×サーベイで実現。個人の強みを組織の強みに転換させていく方法とは
- 全社を巻き込むサーベイ運用。各部門が主体となって進める組織改善の仕組みとは
- 「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善
- おすすめの組織診断サーベイツール「HRBrain」
- サーベイを「やるだけ」で終わらせない。組織を動かす仕組みに変えよう
従業員満足度の向上や組織の健康を測るために、企業はさまざまな手段を講じています。その中でも「サーベイ」は、従業員の意見や感情を直接反映させる有力な手法です。
本記事では、サーベイの種類や実施方法、成功事例を詳しく紹介し、企業がどのようにして効果的にサーベイを活用できるかを解説します。
サーベイとは
サーベイとは、組織や個人の意識、状況、課題を把握するために実施される調査のことです。企業においては、従業員満足度やエンゲージメント、組織風土などを数値化・可視化する手法として活用され、組織の現状把握や改善の第一歩として重要な役割を担います。
サーベイを通じて得られたデータは、人事施策やマネジメントの見直し、経営戦略の立案などに活かされ、より良い職場環境の実現に寄与します。
ここからは、サーベイと似た調査として、アンケート・リサーチ・アセスメントとの違いを解説します。
サーベイとアンケートの違い
サーベイとアンケートは目的と範囲が異なります。サーベイは、特定のテーマについて全体像を把握するための「調査活動全体」を指します。
これには計画立案、情報収集、集計・分析、そして結果に基づく評価や改善策の検討までが含まれます。企業では、従業員のエンゲージメントや満足度を測り、組織課題を明らかにするために実施されます。
一方で、アンケートはサーベイというプロセスの中で使われる「情報収集の具体的な手法のひとつ」です。多数の人に同じ質問を投げかけて回答を集める質問票調査を指します。
たとえば、従業員エンゲージメントサーベイを実施する場合、その中で配布・回収される質問票がアンケートにあたります。
サーベイとアンケートの違いを理解することは、調査の全体像を設計し、単なる情報収集に留まらず結果を具体的な行動につなげるために重要です。
サーベイとリサーチの違い
サーベイとリサーチは、調査の範囲と深掘りの度合いに違いが見られます。
リサーチは特定の課題や仮説に対して、より焦点を絞り、深く掘り下げて行われる調査を意味します。特にマーケティング分野で多用され、特定の商品やサービスに対するターゲット顧客層の反応やニーズを詳細に分析する場合などが該当します。
リサーチでは、対象者を特定の条件で絞り込んだり、より詳細なデータを収集したりすることが特徴です。どちらの手法を用いるかは、調査によって「全体像を広く把握したい」のか、「特定の事柄を深く知りたい」のかという目的によって使い分けることが肝心です。
目的に応じてサーベイとリサーチから適切な手法を選択することが、有益な情報を得るための鍵となります。
サーベイとアセスメントの違い
サーベイとアセスメントは、主に人事分野において、調査対象と目的に違いがあります。
アセスメントは、個々の従業員の「能力、スキル、適性」などを客観的な基準で測定・評価することを目的とします。評価結果は、人材配置、育成計画、昇進・昇格の判断材料として活用されます。たとえば、特定の職務に対する適性検査や、管理職候補者のリーダーシップ能力評価などがアセスメントにあたります。
サーベイが組織という「環境」に対する従業員の認識を問うのに対し、アセスメントは従業員「個人」の特性や能力を評価する点に大きな違いがあります。
両者は補完的な関係にあり、組織と個人の両側面から課題を把握し、改善を進めるうえでは、サーベイとアセスメントの使い分けが重要です。
サーベイの7つの種類
企業が従業員や組織の状態を把握するために用いる、代表的なサーベイを7つ解説します。
<サーベイの7つの種類>
エンゲージメントサーベイ
モラールサーベイ(従業員満足度調査)
組織診断サーベイ
ストレスチェック
コンプライアンス意識調査
アセスメントサーベイ
360度サーベイ(360度評価サーベイ)
それぞれのサーベイは目的や測定対象が異なり、自社の状況や課題に応じて適切な種類を選ぶことが重要です。効果的なサーベイ活用は、組織改善や従業員の働きがい向上につながります。
エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、従業員が自社や仕事に対してどれだけ熱意や愛着、貢献意欲を持っているかを測定するための調査です。
単なる満足度だけでなく、従業員が自発的に組織の成功のために貢献しようとする意欲を可視化し、組織の現状、特にエンゲージメントを促進または阻害している要因を特定し、分析します。エンゲージメントが高い状態は、生産性の向上、離職率の低下、イノベーションの促進などにつながると考えられています。
調査は年1回程度実施されることが多く、「会社のビジョンに共感する」「仕事に誇りを感じる」といった質問項目を通じてエンゲージメントスコアを算出するのが特徴です。ただ実施するだけではなく、結果を分析し、改善施策へつなげることが重要となります。
【関連コンテンツ】
モラールサーベイ(従業員満足度調査)
モラールサーベイは、「従業員満足度調査」とも呼ばれ、従業員の勤労意欲や士気(モラール)、仕事内容、給与、福利厚生、職場環境、人間関係といった労働条件や環境に対する満足度を測定する調査です。
従業員が日々の業務や会社に対して、具体的にどのような点に満足し、あるいは不満を感じているかを把握することが主な目的です。これにより、従業員のモチベーション低下や離職につながる可能性のある問題点を早期に発見し、改善策を講じることが可能になります。
たとえば、「現在の業務量に満足していますか」「上司とのコミュニケーションは円滑ですか」「提供されている福利厚生に満足していますか」といった質問が考えられます。調査結果をもとに、労働環境の改善や、処遇の見直し、コミュニケーションの活性化などを図り、従業員の定着率向上や生産性の改善を目指します。
【関連コンテンツ】
組織診断サーベイ
組織診断サーベイは、組織全体の健全性や機能度合いを多角的に把握し、課題を特定するための調査です。
企業の健康診断といわれることもあり、個々の従業員の満足度やエンゲージメントだけではなく、組織構造、部門間の連携、コミュニケーションの流れ、意思決定プロセス、リーダーシップのあり方、組織風土といった、組織システム全体の機能不全や改善点を明らかにすることを目的とします。
組織が目指す姿と現状とのギャップを認識し、より効果的な組織運営や組織変革を進めるための基礎データを得るために実施されます。質問項目は、「部署間の情報共有は円滑に行われていますか」「経営層からの情報は適切に伝達されていますか」「自社の理念は浸透していると感じますか」など、組織運営のさまざまな側面を網羅しているのが特徴です。分析結果は、組織構造の見直しや新たな制度導入の検討にも活用されています。
【関連コンテンツ】
ストレスチェック
ストレスチェックは、従業員自身のストレス状態への気づきを促し、メンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的とする調査です。
日本では、労働安全衛生法の改正により、2015年12月から従業員数50人以上の事業場において、年1回の実施が義務化されました。この制度は、従業員が質問票に回答することで自らのストレスレベルを把握し、必要に応じてセルフケアを行うきっかけを提供します。
また、高ストレス者と判定された従業員には、本人の申し出に基づき医師による面接指導が行われ、専門的な助言やサポートを受ける機会が与えられます。
さらに、個人の結果とは別に、部署や職場単位で結果を集計・分析(集団分析)し、職場環境におけるストレス要因を特定することも重要な目的です。この集団分析結果をもとに、職場環境の改善策を検討・実施することで、働きやすい環境づくりを進めます。
【関連コンテンツ】
コンプライアンス意識調査
コンプライアンス意識調査は、組織内の従業員が法令、社内規程、企業倫理などをどの程度理解し、遵守する意識を持っているかを測定するためのサーベイです。
企業の信頼失墜や法的責任につながりかねないコンプライアンス違反のリスクを事前に把握し、予防策を講じることを主な目的とします。
また、定期的に実施することで、コンプライアンス研修の効果測定や、従業員の意識の変化を把握し、今後の教育・啓発活動の方向性を定めるうえでの重要な情報源となります。
「自社のコンプライアンスに関する方針を理解しているか」「業務上、倫理的に問題があると感じた場合に相談できる窓口を知っているか」「個人情報の取り扱いについて正しく理解しているか」などが主な質問内容です。
調査結果は、リスクの高い領域や対象者を特定し、重点的な対策を講じるために活用されます。
アセスメントサーベイ
アセスメントサーベイは、従業員一人ひとりが持つ能力、スキル、知識、性格特性、職務適性などを客観的な基準にもとづいて測定・評価するための調査手法です。
採用選考や、人材配置、異動、昇進・昇格、人材育成計画の策定といった人事関連の意思決定において、客観的で信頼性の高い情報を提供することを目的として実施します。
個人のポテンシャルや強み・弱みを正確に把握することで、適材適所の人材配置を実現したり、個々の従業員に最適化された能力開発プログラムを提供したりすることが可能です。
具体的な手法としては、職務知識や専門スキルを問うテスト、論理的思考力や問題解決能力を測る適性検査、リーダーシップや協調性といった行動特性(コンピテンシー)を評価する質問紙、個人の価値観や性格を分析する性格検査など、多岐にわたります。
組織全体の課題を見る他のサーベイとは異なり、「個人」の評価に特化している点が特徴です。
360度サーベイ(360度評価サーベイ)
360度サーベイは、「360度評価」や「多面評価」とも呼ばれ、評価対象者本人による自己評価に加え、その上司、同僚、部下といった複数の関係者から、対象者の行動や能力についてフィードバックを収集する評価手法です。
場合によっては、顧客や取引先など社外の関係者が評価に参加することもあります。ひとりの評価者(通常は直属の上司)だけでは捉えきれない、対象者の多面的な姿を明らかにすることが目的です。
さまざまな立場からの視点を取り入れることで、より客観的で公平性の高い評価情報が得られると同時に、自己認識と他者からの認識のギャップに気づきを与え、対象者の自己成長や能力開発を促す効果が期待されます。
評価項目には、リーダーシップ、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力など、具体的な行動特性に関するものが多く含まれます。
結果のフィードバックは慎重に行う必要があり、育成目的での活用が推奨されているサーベイです。
【関連コンテンツ】
組織サーベイの2つの実施方法
組織サーベイを実施する際の主な2つのアプローチ、「センサスサーベイ」と「パルスサーベイ」について解説します。
これらは実施頻度や設問数、目的に違いがあり、それぞれの特徴を理解して使い分けることが効果的な組織改善につながります。
センサスサーベイ | パルスサーベイ | |
|---|---|---|
実施頻度 | 低い(年1~2回) | 高い(週1回~四半期に1回など) |
設問数 | 多い(数十問~) | 少ない(数問~15問程度) |
目的 | 組織全体の包括的な状況把握、根本課題特定、長期トレンド分析 | リアルタイムな状態観測、特定課題の追跡、迅速な問題発見・改善 |
メリット | 詳細な分析が可能、網羅的、ベンチマークに適する | タイムリーな情報収集、問題の早期発見、回答負担が少ない、変化を捉えやすい |
デメリット | 結果が古くなりやすい、分析・改善に時間がかかる、回答負担が大きい | 包括的な分析は難しい、サーベイ疲れのリスク、深い課題を見逃す可能性 |
センサス
センサスサーベイは、年に1回または半年に1回といった比較的低い頻度で実施される、大規模かつ包括的な組織調査を指します。
多くの場合、全従業員を対象とすることから「センサス(国勢調査)」の名が付けられています。このアプローチの主な目的は、組織全体のエンゲージメント、従業員満足度、組織文化、リーダーシップ、キャリア開発、職場環境など、幅広いテーマについて深く掘り下げて現状を把握することです。
設問数が多く、詳細な分析が可能であるため、組織全体の根本的な課題を特定したり、長期的な傾向を把握したり、他社比較を行ったりするのに適しています。
一方で、実施頻度が低いため、調査時点から時間が経過すると情報が古くなる可能性や、結果の分析・改善策の実行までに時間がかかる点がデメリットとして挙げられます。また、設問数が多いため、従業員の回答負担が大きくなりやすいことにも注意が必要です。
パルスサーベイ
パルスサーベイは、「脈拍(Pulse)」のように、短期間かつ高頻度(毎週、毎月、四半期ごとなど)で従業員の意識や状態を定点観測する調査手法です。
センサスサーベイが年に1回程度の「精密検査」だとすれば、パルスサーベイは日常的な「健康チェック」に例えられます。設問数を少なく、回答時間を短くすることで、従業員の負担を軽減しつつ、リアルタイムに近い形で現場の状況や従業員の感情の変化を捉えることを目的とします。
新しい人事制度導入後の反応、特定のプロジェクトの進捗に伴うチームの状態変化など特定のテーマに焦点を当てたり、エンゲージメント、ウェルビーイングなどの重要な指標の変化を継続的に追跡したりするのに有効です。問題の早期発見と迅速な改善アクション、継続的なフィードバック文化の醸成といったメリットがあります。
ただし、頻度が高すぎると従業員の「サーベイ疲れ」を引き起こしたり、毎回結果に対するフィードバックや改善が行われないと不信感につながったりする可能性があるため、適切な運用が求められます。
【関連コンテンツ】
サーベイを実施する3つのメリット
企業が組織サーベイを実施することによって得られる主な3つのメリットについて解説します。
<サーベイを実施する3つのメリット>
従業員エンゲージメントの向上につながる
優先的に改善すべき課題がわかる
経営層と現場のギャップが明らかになる
サーベイは、組織の現状を客観的に把握するだけでなく、従業員のエンゲージメント向上や効果的な課題解決に繋がる重要な手段です。適切に活用することで、組織の持続的な成長を促進できます。
従業員エンゲージメントの向上につながる
組織サーベイの実施と、その結果に基づいた適切なアクションは、従業員のエンゲージメント向上に大きく貢献します。
エンゲージメントとは、従業員が自社や自身の仕事に対して抱く、自発的な貢献意欲や深い愛着のことです。サーベイを通じて、企業が従業員一人ひとりの声に耳を傾け、その意見を真摯に受け止める姿勢を示すことは、従業員にとって「自分は組織から大切にされている」「自分の意見は尊重されている」という実感につながります。
このような肯定的な経験は、従業員の組織に対する信頼感を醸成します。さらに重要なのは、サーベイで明らかになった課題に対して具体的な改善策が実行され、職場環境がよりよくなっていくプロセスです。
従業員は、自分たちの声が実際に組織を動かし、変化を生み出していると感じることで、働きがいや組織への貢献意欲が一層高まります。
【関連コンテンツ】
優先的に改善すべき課題がわかる
組織サーベイは、社内に存在するさまざまな課題の中から、特に優先して取り組むべき重要なものは何かを客観的なデータに基づいて見極める効果的な手段です。
多くの組織では、常に複数の課題が存在しますが、リソースには限りがあるため、すべての課題に同時に着手することは現実的ではありません。
サーベイを活用することで、従業員がどの項目に強い不満を感じているのか、どの要素がエンゲージメントや満足度に最も大きな影響を与えているのかといった点を定量的に把握することが可能です。
これにより、経営層や人事担当者の主観や感覚だけに頼るのではなく、データに基づいた論理的な根拠を持って、改善策の優先順位を決定できます。たとえば、サーベイ結果の分析から、特定の部署におけるコミュニケーション不足が他の問題よりもエンゲージメント低下に強く関連していることがわかれば、その対策に優先的にリソースを投入するといった判断ができるでしょう。
このように、サーベイは組織改善の方向性を定め、限られた資源を最も効果的に活用するために役立ちます。
経営層と現場のギャップが明らかになる
組織サーベイは、経営層や管理職が考えている組織の状況と、実際に現場で働いている従業員が肌で感じている状況との間に存在する認識のギャップを具体的に浮き彫りにします。
組織運営においては、経営層が打ち出した方針やビジョンが現場の従業員に正確に伝わっていなかったり、現場が抱える問題点や日々の業務における困難さが経営層に十分に届いていなかったりするケースが少なくありません。
サーベイは、多くの場合、守秘性が確保された状態で実施されるため、従業員は普段、立場上言いづらいと感じている本音や、率直な意見、現場の実態などを比較的表明しやすくなります。これにより、経営層が良かれと思って導入した新しい人事制度が、現場では意図通りに機能しておらず、むしろ混乱や不満を生んでいるといった実態が、データとして可視化されることがあるでしょう。
このような認識のギャップを把握することは、経営層が的確な意思決定を行い、実効性のある施策を打つうえで不可欠なプロセスです。
サーベイを実施する4つのデメリット
組織サーベイを実施する際に注意すべき4つのデメリットや課題を解説します。
<サーベイを実施する4つデメリット>
サーベイの実施コストがかかる
本音を引き出せない場合もある
従業員の不満につながる可能性がある
改善策につなげる力が必要になる
サーベイは組織改善に有効な手段ですが、これらのデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じなければ、期待した効果が得られない可能性があります。ポイントを押さえて、サーベイの失敗リスクを低減しましょう。
サーベイの実施コストがかかる
組織サーベイの実施には、さまざまなコストが発生する点を認識しておく必要があります。
まず、外部のサーベイツールやプラットフォームを利用する場合には、そのシステム利用料がかかります。また、設問の設計、データ分析、結果報告などを外部のコンサルティング会社に委託する場合は、専門的なサービスに対する費用が発生します。
社内で実施する場合でも、人事担当者などが設問作成から分析、報告、改善策の検討といった一連の業務に時間を費やすため、人的コストも無視できません。さらに、従業員がサーベイに回答する時間もコストとして考慮すべきです。
たとえば、全従業員が業務時間内に回答する場合、その時間は本来の業務に充てられるはずの時間であり、実質的な人件費といえます。これらのコストを考慮せずに安易にサーベイを導入すると、費用対効果が見合わない結果になりかねません。
対策としては、まずサーベイの目的を明確にし、本当に必要な調査範囲や頻度を見極めることが重要です。Googleフォームなどの無料ツールを活用したり、内製化できる範囲を増やしたりすることもコスト抑制につながります。
本音を引き出せない場合もある
サーベイを実施しても、従業員が自身の本音を回答せず、表面的な回答や当たり障りのない意見に留まってしまう可能性があります。
その主な理由として、従業員が抱く不安感が挙げられます。「正直に回答したら、自分の評価に不利になるのではないか」といった懸念があると、率直な意見を表明することをためらってしまいます。
特に、上司や人事評価に関する質問、あるいはネガティブな内容を含む質問に対しては、自己保身の心理が働きやすくなるでしょう。
また、質問の仕方自体に問題がある場合もあります。回答を特定の方向に誘導するような質問や、言葉遣いが曖昧で意図が正確に伝わらない質問は、従業員の真意とは異なる回答を引き出してしまう原因となります。
このような状況を避けるためには、収集された情報の守秘性を徹底し、そのデータが公正に取り扱われることを明確に約束することが大前提です。サーベイの回答が、従業員にとって不利益な人事評価や処遇に直接結びつくことはないことを伝え、安心感を醸成する必要があります。
加えて、サーベイの目的や結果の活用方法を具体的に説明し、協力をお願いする姿勢を示すこと、誰にでも理解できる中立的で分かりやすい質問を作成することが重要です。
従業員の不満につながる可能性がある
サーベイは従業員の声を聞くための有効な手段ですが、その実施方法や結果の取り扱い方を誤ると、かえって従業員の不満や会社に対する不信感を招いてしまうリスクがあります。
たとえば、サーベイを実施する目的や意義が従業員に十分に共有されないまま、一方的に回答を求められるようなケースでは、従業員は何のために協力するのか理解できず、やらされている印象を抱きがちです。また、実施頻度が高すぎたり、設問数が多すぎたりして、従業員の負担が大きい場合も不満の原因となります。
さらに重要なのは、サーベイ実施後の対応です。従業員が時間を使って真剣に回答したにも関わらず、調査結果が全くフィードバックされなかったり、具体的な改善アクションにつながらないことが繰り返されると、「どうせ答えても何も変わらない」「意見を聞くだけで行動しない」という諦めや不信感が組織内に蔓延し、次回以降のサーベイへの協力意欲も著しく低下してしまいます。
こうした事態を防ぐためには、実施前に目的と意義を丁寧に説明し、従業員の負担に配慮した設計を心がけるとともに、結果を迅速かつ誠実にフィードバックし、具体的な改善行動につなげ、その進捗状況を継続的に共有していく姿勢が不可欠です。
改善策につなげる力が必要になる
サーベイを実施し、組織の課題や従業員の意見を収集することは重要ですが、それだけで組織が良くなるわけではありません。
サーベイで得られた結果を分析し、具体的な改善策を立案し、それを実行に移していくための能力や体制が組織に備わっていなければ、サーベイは単なる「調査のための調査」に終わり、時間とコストを浪費しただけになってしまう可能性があります。サーベイ結果の分析には、データを正しく読み解き、傾向や課題の根本原因を特定するためのスキルが必要です。
分析結果にもとづいて実効性のある改善策を企画し、関連部署や担当者を巻き込みながら計画的に実行し、その効果を測定してさらなる改善につなげるという一連の活動には、強いリーダーシップと推進力、継続的な努力が求められます。
サーベイを成功させるためには、調査を計画する段階から、結果をどのように分析し、誰が責任を持って改善を進めるのか、具体的なプロセスと体制を明確にしておくことが重要です。
もし社内に十分なスキルやリソースがない場合は、外部の専門家の支援を仰いだり、分析機能やアクションプランニング機能を持つサーベイツールを導入したりすることも有効な解決策となります。
効果的なサーベイ実施の9ステップのやり方
組織サーベイを効果的に実施し、組織改善につなげるための具体的な9つのステップを紹介します。
<効果的なサーベイ実施の9ステップのやり方>
- 実施目的を明確にし、「何を知りたいか」を設計に落とし込む
- 設問数はシンプルかつ要点を絞り、回答負荷を最小限にする
- 回答データの守秘性を担保し、安心して意見を表明できる環境をつくる
- 回答しやすいタイミングで実施し、全社的な参加を促す
- 集計・分析の体制を整え、スピーディにフィードバックを行う
- 結果を公開し、組織として「聴く姿勢」を示す
- 結果をもとに優先課題を設定し、具体的な改善策に落とし込む
- アクションの進捗を定期的に共有し、信頼と納得感を醸成する
- 継続実施を前提にし、経年比較や効果検証に活かす
サーベイは計画から実行、そして結果の活用まで、一連のプロセスを丁寧に進めることが成功の鍵となります。各ステップのポイントを押さえ、意義のあるサーベイ実施を目指しましょう。
1. 実施目的を明確にし、「何を知りたいか」を設計に落とし込む
効果的なサーベイを実施するための最初のステップは、調査の目的を明確に定義することです。
「なぜサーベイを実施するのか」「この調査を通じて何を知りたいのか」「結果をどのように活用したいのか」を具体的に定めます。たとえば、「若手従業員の離職率が高い原因を特定し、定着率を向上させる」「新しい人事制度に対する従業員の理解度と満足度を把握する」「組織全体のエンゲージメントレベルを測定し、改善のための重点課題を見つける」といった目的が考えられます。目的が明確になることで、調査すべき対象者、質問すべき項目、適切な調査手法などが自ずと定まります。
また、事前に「組織には〇〇のような課題があるのではないか」という仮説を立てておくと、その仮説を検証するための設問設計ができ、後の分析や改善策の立案がスムーズに進みます。目的が曖昧なままサーベイを実施しても、有用なデータが得られず、時間とコストが無駄になる可能性があるため、まず目的を明確にしましょう。
2. 設問数はシンプルかつ要点を絞り、回答負荷を最小限にする
サーベイの設問内容と数は、回答率や回答の質に直接影響します。従業員の負担を最小限に抑え、質の高い回答を得るためには、設問をできるだけシンプルにし、本当に知りたい情報に絞り込むことが重要です。質問文は、専門用語や曖昧な表現を避け、誰にでも理解できる平易な言葉で、短く具体的に作成します。
ひとつの質問で複数の論点を問う「二重質問」は避け、ひとつの質問ではひとつのことだけを尋ねるようにしましょう。
また、設問数が多すぎると回答者は疲労し、途中で離脱したり、後半の回答が不誠実になったりする可能性が高まります。一般的なエンゲージメントサーベイであれば10~15分程度、パルスサーベイであれば数分で完了できる長さを目安に、設問数を調整しましょう。
回答形式も、直感的に答えやすい選択式を中心にするなど、回答しやすい工夫を取り入れることが推奨されます。回答者の時間を尊重する姿勢が、協力的な回答を引き出す鍵となります。
3. 回答データの守秘性を担保し、安心して意見を表明できる環境をつくる
従業員から正直な意見を引き出すためには、回答データの守秘性を徹底し、安心して意見を表明できる環境を整えることが重要です。
サーベイを実施する場合、従業員は「回答内容が人事評価にどう影響するのか」「率直な意見を述べることで不利益を被らないか」といった不安を感じやすくなります。
そのため、サーベイを実施する際には、収集した個人情報と回答内容は厳重に管理され、権限のない者には開示されないこと、回答内容は本来の目的以外には使用されないこと、そして回答内容で個人が不利益な評価や扱いを受けないことを明確に従業員に伝え、安心感を醸成することが不可欠です。
4. 回答しやすいタイミングで実施し、全社的な参加を促す
サーベイの回答率を高め、より多くの従業員から意見を集めるためには、実施するタイミングと参加促進の工夫が重要です。
まず、実施時期は、繁忙期や大きな社内イベントの直後などを避け、従業員が比較的落ち着いて回答に取り組める時期を選定します。回答期間も、短すぎると回答できない従業員が出てくる可能性があるため、1~2週間程度の適切な期間を設定しましょう。
次に、参加を促すためには、事前の告知が不可欠です。サーベイを実施する目的、重要性、回答にかかる時間の目安などを明確に伝え、従業員の理解と協力を求めます。経営層からサーベイ実施への期待や協力を呼びかけるメッセージを発信することも、従業員の意識を高める上で効果的です。回答期間中には、未回答者に対してリマインダーを送ることも有効ですが、過度な催促は逆効果になる可能性もあるため注意が必要です。
また、回答時間を業務時間として認めるなど、従業員が回答しやすい環境を整える配慮も、参加率向上につながります。
5. 集計・分析の体制を整え、スピーディにフィードバックを行う
サーベイを実施したら、収集したデータを迅速に集計・分析し、その結果を従業員にフィードバックする体制を整えておくことが重要です。
回答期間が終了してから結果のフィードバックまでに時間がかかりすぎると、従業員の関心が薄れてしまうだけでなく、「結果はどうなったのか」「意見は無視されたのか」といった不信感にもつながりかねません。スムーズな集計・分析のためには、事前に担当者を決め、役割分担を明確にしておく必要があります。
また、近年では多くのサーベイツールに自動集計や分析機能が搭載されているため、こうしたツールを活用することで、効率的に作業を進められます。分析においては、単に全体の平均点を出すだけでなく、部署別、役職別、勤続年数別などの属性ごとにクロス集計を行ったり、前回調査結果との比較(経年比較)を行ったりすることで、より詳細な傾向や課題を把握できます。
分析結果が出たら、なるべく早いタイミングで、概要だけでも従業員にフィードバックすることが、信頼関係の維持と改善への機運を高める上で重要です。
6. 結果を公開し、組織として「聴く姿勢」を示す
サーベイの集計・分析が終わったら、その結果を隠すことなく、従業員に対して透明性を持って公開することが重要です。
結果をオープンに共有する姿勢は、企業が従業員の声を真摯に受け止め、組織をよりよくしていこうと考えていることの証となります。これにより、従業員は自分の意見が軽視されていないと感じ、組織への信頼感を深めます。結果の公開にあたっては、よかった点だけでなく、課題として明らかになった点についても正直に伝えることが大切です。
課題を認識していることを示すことで、改善への本気度を伝えられます。全体の傾向や、属性別の分析結果、特に重要な発見事項などを、全社集会や社内報などを通じてわかりやすく伝えましょう。
結果の公開は、従業員との対話のはじまりであり、組織全体で課題に向き合う意識を醸成するための第一歩です。
7. 結果をもとに優先課題を設定し、具体的な改善策に落とし込む
サーベイ結果を分析し、課題を特定した後は、それらの課題に優先順位をつけ、具体的な改善策(アクションプラン)に落とし込むステップが不可欠です。
サーベイによって複数の課題が明らかになることが多いですが、すべて同時に取り組むことは現実的ではありません。そのため、分析結果にもとづき、「どの課題が最も組織全体や従業員のエンゲージメントに影響を与えているか」「どの課題から着手するのが最も効果的か」といった観点から、優先的に取り組むべき課題を決定します。
優先課題が決まったら、その原因をさらに深掘りし、「何を」「誰が」「いつまでに」「どのように」改善していくのか、具体的な行動計画を策定します。改善策は、測定可能で達成可能な目標を設定し、担当者と期限を明確にすることが重要です。
また、改善策の立案に従業員を巻き込むことで、より現場の実態に即した実効性の高いプランとなり、実行段階での従業員の協力も得やすくなります。サーベイの結果を具体的な行動へと転換するこのステップが、調査を意味あるものにするための要となります。
8. アクションの進捗を定期的に共有し、信頼と納得感を醸成する
具体的な改善策(アクションプラン)を策定し、実行に移した後は、その進捗状況を定期的に従業員へ共有することが非常に重要です。
サーベイを実施し、課題が明らかになり、改善策が示されたとしても、その後の進捗が見えなければ、従業員は「結局何も変わらないのではないか」「あの計画はどうなったのだろうか」と不安や不信感を抱きかねません。進捗状況を透明性をもって共有することで、会社が本気で改善に取り組んでいる姿勢を示し、従業員の信頼と納得感を得られます。
共有の方法としては、社内報やイントラネットでの定期的な報告、全社集会や部門会議での説明、関係者へのメール配信などが考えられます。単に進捗を報告するだけではなく、取り組みの中で見えてきた新たな課題や、計画の変更点なども含めて正直に伝えることが、信頼関係の維持につながります。
また、改善の成果が見えはじめた際には、それを積極的に共有し、関係者の努力を称えることも、従業員のモチベーションを高める上で効果的です。
継続的なコミュニケーションを通じて、組織全体で改善を進めている一体感を醸成しましょう。
9. 継続実施を前提にし、経年比較や効果検証に活かす
組織サーベイは、一度実施して終わりではなく、継続的に実施していくことを前提として計画することが重要です。
定期的にサーベイを実施することで、組織の状態の変化や従業員の意識の推移を時系列で把握できます。これにより、過去に実施した改善策が実際に効果を発揮しているのかどうか客観的な検証が可能です。
また、時間の経過とともに新たな課題が発生したり、以前は問題でなかった点の重要度が増したりすることもあるため、継続的な観測を通じて組織の状態を常に最新の状態にアップデートしておく必要があります。前回のサーベイ結果や、それに基づいて実施したアクションの効果を踏まえて、次回のサーベイの設問内容を見直したり、分析の観点を変更したりすることも有効です。
継続的なサーベイの実施と効果検証のサイクルを回していくことで、組織はデータにもとづいた持続的な改善活動を行うことができ、よりよい組織へと進化していくことが期待できます。
サーベイ実施時の9つの注意点
組織サーベイを実施する際に陥りやすい失敗や注意すべき9つのポイントについて解説します。
<サーベイ実施時の9つの注意点>
設問の目的と意図を明確にしないまま設計しない
設問数が多すぎたり抽象的すぎると回答率が下がる
回答者の保護や守秘性が不十分だと、本音を引き出せない
回答の自由度が低すぎると重要な声を見落とす
結果を放置すると「形だけのサーベイ」と捉えられる
分析・改善に活かす体制がないまま実施しない
個々の回答の取り扱いで信頼を損なわない
サーベイの目的や結果を社内に共有しないと不信感が残る
単発で終わらせず、継続的な改善サイクルに組み込む必要がある
これらの点に留意し、適切な計画と配慮をもって実施することで、サーベイの効果を最大限に引き出し、従業員の不満や不信感を防ぐことができます。
設問の目的と意図を明確にしないまま設計しない
サーベイを効果的なものにするためには、設問設計の段階で「なぜこの質問をするのか」「この質問で何を知りたいのか」という目的と意図を明確にすることが不可欠です。
目的が曖昧なまま設問を作成してしまうと、調査全体の方向性が定まらず、結果的に知りたい情報が得られない、収集したデータが分析や具体的なアクションにつながらないといった事態を招きかねません。サーベイに費やした時間やコストが無駄になるだけでなく、回答してくれた従業員の協力をも無意味にしてしまう可能性があります。
たとえば、「組織風土を改善したい」という漠然とした目的ではなく、「部署間のコミュニケーション不足という課題仮説を検証し、改善策のヒントを得たい」といったレベルまで具体化することが望ましいです。
各設問が調査目的達成のためにどのような役割を果たすのかを常に意識し、一貫性のある設問設計を心がけましょう。
設問数が多すぎたり抽象的すぎると回答率が下がる
サーベイの設問数が多すぎたり、質問内容が抽象的で回答しにくかったりすると、従業員の回答意欲を著しく低下させ、結果として回答率の低下や回答の質の劣化を招く大きな原因となります。
回答に長時間要するサーベイは、回答者の集中力を削ぎ、途中で回答を諦めてしまいやすくなります。最後まで回答してもらえたとしても、後半になるにつれて疲労から回答が適当になったり、一貫性がなくなったりする可能性があるでしょう。
さらに、「会社の満足度」や「働きがい」といった抽象的な質問は、回答者によって解釈が異なり、具体的な状況や意見を引き出しにくいため、分析に役立つ精度の高いデータを得ることが困難です。
これを防ぐためには、調査目的の達成に必要な質問項目を厳選し、設問数を適切な範囲(例えば、回答時間10~15分以内が目安)に絞り込むことが重要です。
質問文は誰にでも理解できるよう具体的かつ平易な言葉を選び、回答者の負担を最小限に抑える配慮が求められます。
回答者の保護や守秘性が不十分だと、本音を引き出せない
従業員の本音を引き出すには、回答内容の守秘性を徹底し、回答者が不利益な扱いを受けないことを明確に伝える必要があります。回答内容が不適切に扱われる懸念があれば、従業員から本音を引き出すことは難しくなります。
個人情報の取り扱いルールを明確にして、従業員が不利益な扱いを受けないことを約束することで、安心して本音を回答できる環境を整えましょう。
回答の自由度が低すぎると重要な声を見落とす
サーベイの設問が、主に選択肢から回答を選ぶ形式に偏り、従業員が自身の言葉で自由に意見や感想を記述できる形式が少ない場合、注意が必要です。
選択式の質問は集計や分析がしやすいというメリットがありますが、一方で回答者は用意された選択肢の範囲内でしか意見を表現できません。そのため、選択肢だけでは捉えきれない個々の具体的な状況、その回答に至った背景や理由、従業員が抱える独自の視点や改善提案といった、貴重な「生の声」を見落としてしまう可能性があります。
特に、新たな問題の発見や、既存の課題に対する深い洞察を得るためには、自由記述欄が重要な役割を果たします。効果的なサーベイのためには、定量的な質問で全体の傾向を把握しつつ、要所に自由記述式の質問を設け、定性的な情報もバランスよく収集する設計を心がけることが望ましいです。
個々の回答の取り扱いで信頼を損なわない
個々の回答の取り扱いには細心の注意が必要です。本人の許可なく不必要に共有したり、目的外利用したりすれば従業員からの信頼を失い、回答してもらうことが難しくなります。
閲覧権限を限定・厳格に管理し、結果報告は全体の傾向に焦点を当てるなど配慮しましょう。
結果を放置すると「形だけのサーベイ」と捉えられる
サーベイを実施した後に、その結果を分析せず放置したり、従業員へのフィードバックや具体的な改善アクションにつなげなかったりすることは、絶対に避けなければなりません。
このような「やりっぱなし」の状態は、サーベイを単なる「形だけのイベント」にしてしまい、従業員の会社に対する信頼を著しく損ねる結果を招きます。従業員は、サーベイに回答する際に、自分の意見が組織をより良くするために役立つことを期待しています。
時間と労力をかけて協力したにも関わらず、その後何の音沙汰もなく、職場も何も変わらなければ、「意見を言っても意味がない」「会社は従業員の声を聞く気がない」と感じ、深い失望感や不満を抱くでしょう。一度このような経験をすると、従業員は今後のサーベイに対して非協力的な態度をとるようになり、組織改善の貴重な機会が失われてしまいます。
サーベイの価値は、結果を次の行動につなげてこそ生まれるということを強く認識し、必ずフィードバックと改善アクションを実行する責任があります。
分析・改善に活かす体制がないまま実施しない
サーベイを実施する前に、収集したデータを適切に分析し、その結果に基づいて具体的な改善策を立案・実行するための社内体制が整っているかを確認することが重要です。
分析や改善活動を実行するための担当者、必要なスキル、時間的リソース、そして推進していくための権限などが不明確なままサーベイに踏み切ると、せっかく集めた貴重なデータが活用されずに終わってしまうリスクが高まります。
サーベイデータの分析には、統計的な知識やデータハンドリングのスキルが求められる場合があり、分析結果から実効性のある改善策を導き出し、関係者を巻き込んで実行に移すには、企画力やプロジェクトマネジメント能力、そして何より改善を推進するリーダーシップが必要です。
これらの体制や能力が不足している状態でサーベイを実施しても、「結果を放置する」のと同じく、従業員の期待を裏切り、不信感を招くだけの結果になりかねません。
実施計画と同時に、結果を誰がどのように分析し、改善活動を推進していくのか、具体的な体制とプロセスを設計しておくことが、サーベイを成功させるための前提条件です。
サーベイの目的や結果を社内に共有しないと不信感が残る
サーベイの実施にあたっては、その目的や背景、そして調査結果とそれに基づく改善計画について、従業員に対して透明性を持って情報を共有することが、不信感や疑念を防ぎ、円滑な協力を得るために重要です。
従業員は、自分がなぜこの調査に協力する必要があるのか、自分の回答がどのように活用されるのかを知りたいと考えています。
目的が不明確なまま一方的に回答を求められたり、調査結果が一部の役職者だけで共有され、一般の従業員には何も知らされなかったりすると、「会社は何を隠しているのだろうか」「自分たちの意見は軽視されているのではないか」といった疑念や不満を抱く原因となります。情報共有が不足すると、サーベイに対する従業員のエンゲージメントは低下し、回答の質にも影響が出かねません。
サーベイを実施する前には目的と意義を丁寧に説明し、調査後には結果の概要と今後のアクションプランをわかりやすく共有し、さらに改善活動の進捗についても継続的に報告するなど、プロセス全体を通じてオープンなコミュニケーションを心がけることが、従業員の理解と納得感、そして組織への信頼を育む上で不可欠です。
単発で終わらせず、継続的な改善サイクルに組み込む必要がある
組織サーベイは、一度実施したら終わりという単発のイベントとして捉えるべきではありません。組織の状態や従業員の意識は常に変化するため、その効果を最大限に引き出すためには、定期的に継続して実施し、組織の継続的な改善プロセス(PDCAサイクルなど)の一部として明確に位置づけることが重要です。
継続的にサーベイを実施することで、組織の変化のトレンドを経年で比較・分析できるようになります。過去に実施した改善策が実際に効果を発揮したのかどうかを客観的に評価したり、社会情勢や事業環境の変化に伴って新たに発生した課題を早期に発見したりできるでしょう。
単発の調査では、その時点での状況しかわからず、変化の方向性や施策の効果を正しく捉えることは困難です。
サーベイを「組織の健康診断」と位置づけ、年に1回、半年に1回といった計画的なサイクルで実施し、その結果を分析して次のアクションにつなげ、さらにその効果を次回のサーベイで検証するという継続的な改善サイクルを回していくことが、データにもとづいた持続可能な組織運営を実現する鍵となります。
サーベイ導入の4つの成功事例・ツール活用事例
組織サーベイを導入し、その結果を活用して組織改善に成功した企業の事例や、サーベイツールの効果的な活用事例を紹介します。
<サーベイ導入の4つの成功事例・ツール活用事例>
従業員に寄り添うサーベイ運用。 2,000名規模の組織改善の取り組みとは
タレントマネジメント×サーベイで実現。個人の強みを組織の強みに転換させていく方法とは
全社を巻き込むサーベイ運用。各部門が主体となって進める組織改善の仕組みとは
「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善
具体的な企業の取り組みを知ることは、自社でのサーベイ活用のヒントとなります。サーベイの導入を検討している方は、ぜひ導入の背景や成果などに注目してみてください。
タレントマネジメント×サーベイで実現。個人の強みを組織の強みに転換させていく方法とは
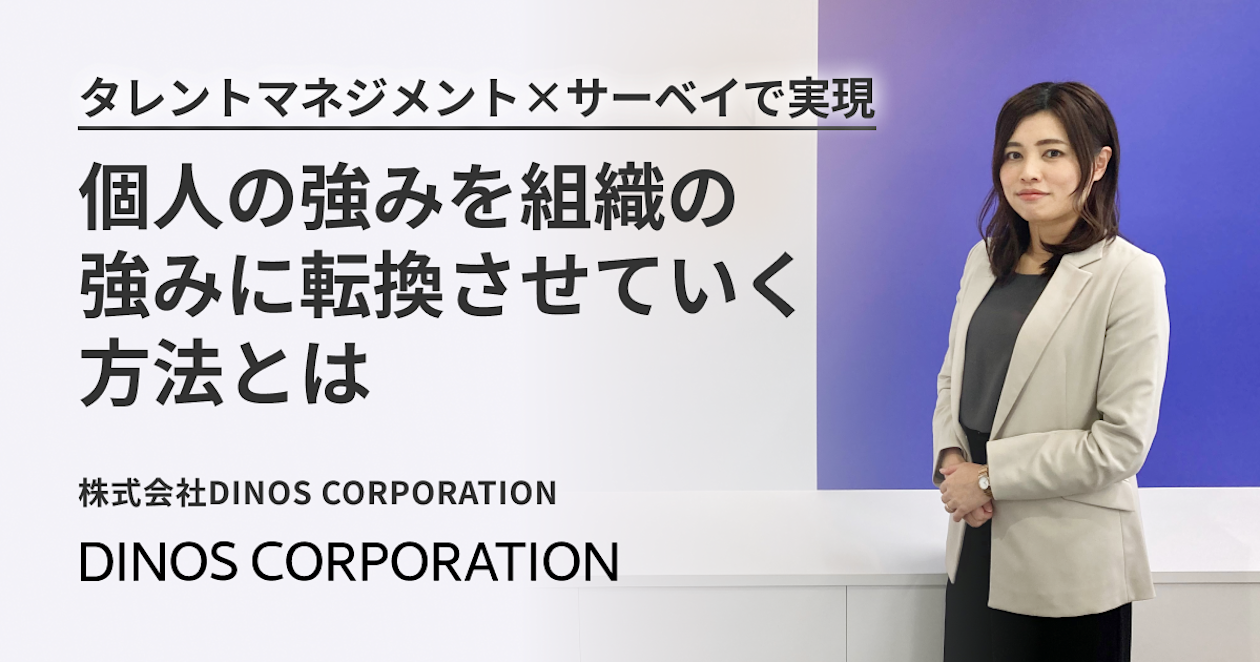
株式会社DINOS CORPORATIONでは、従業員情報や目標・評価の管理をエクセルで行っていたため、情報呼び出しや目標更新に多大な手間と時間がかかっていました。また、スポットでのサーベイ実施はあったものの、定期的な観測ができず、長期的な人事施策に活用しきれていない課題もありました。
そこでタレントマネジメントシステム「HRBrain」を導入し、従業員情報・目標・評価の一元管理を実施。組織診断サーベイ「EX Intelligence」により、定期的な組織診断を行い、数値データに基づいた課題把握と分析を進めました。
エクセル管理時に数日かかっていた評価集計時間がゼロになり、分析やフィードバックに注力できるようになっただけではなく、経営層と課題認識を共有できるようになったことで、従業員の期待に即した課題解決への取り組みが推進されています。
【関連コンテンツ】
全社を巻き込むサーベイ運用。各部門が主体となって進める組織改善の仕組みとは
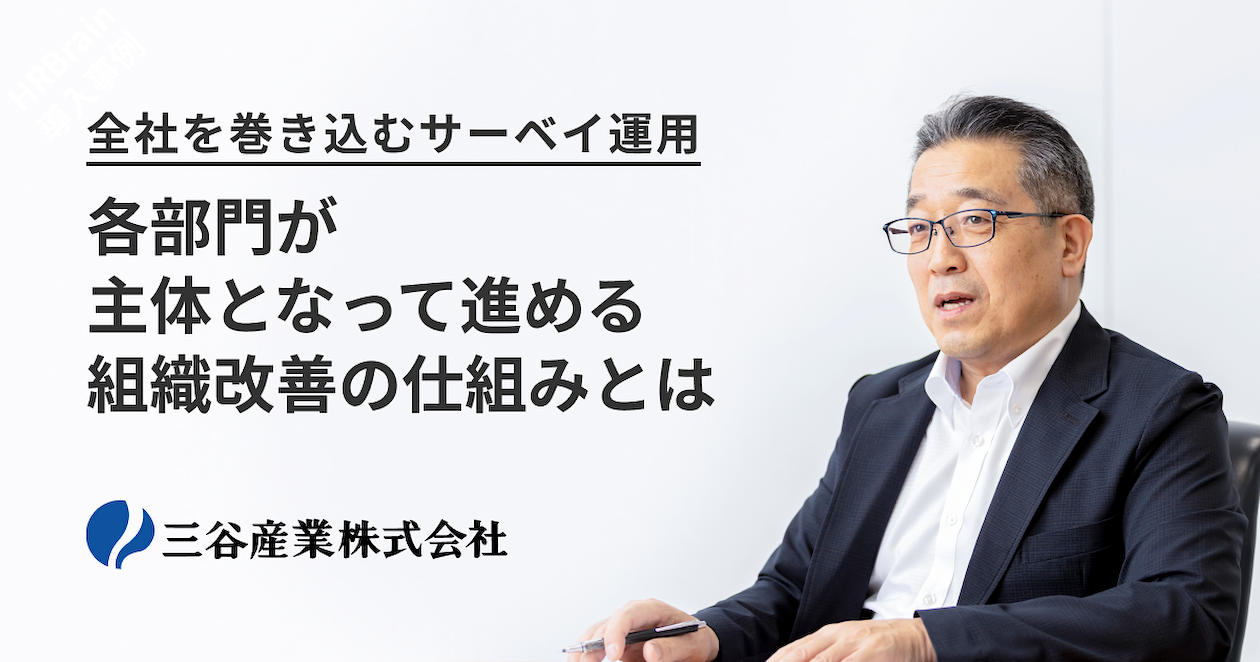
三谷産業株式会社では、過去に実施していたサーベイのスパンが長く、リアルタイム集計ができないことに課題を感じていました。また、「良い会社であり続けるための非財務的経営目標」を設定する新プロジェクトの始動に伴い、より効果的な組織診断手法が求められていたなかで、HRBrainの「EX Intelligence」を導入に踏み切っています。
組織の「実態」と「ありたい姿」のギャップを数値化し、サーベイの分析を各部門が主体的に実施することで、人事がリズムを刻む形で全社の改善活動をサポートする仕組みを整備しました。
リアルタイムで状況把握と改善活動が可能となり、各部門が主体的・自律的に組織改善を推進した結果、従業員エンゲージメント指標(EXスコア®)も向上し、より豊かなコミュニケーション文化の醸成に成功しています。
【関連コンテンツ】
「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善
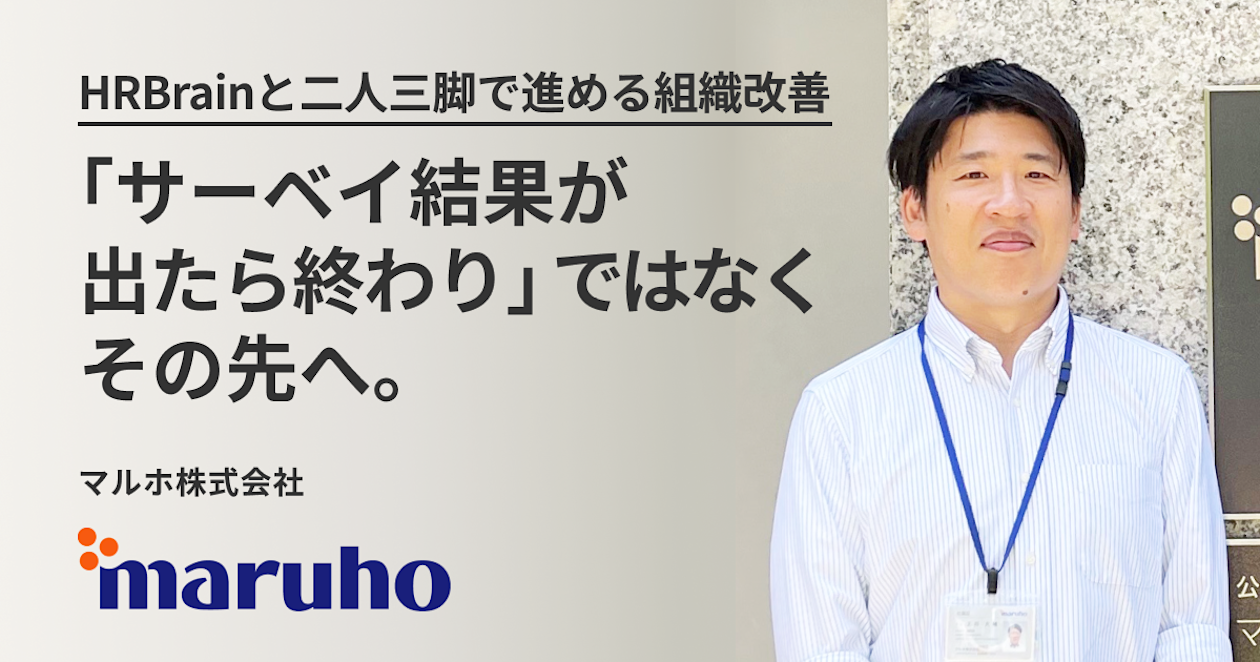
マルホ株式会社では、離職率が多い印象があったものの、発生している事象に対する課題や要因がつかみきれず、具体的な対応ができていないという危機意識を持っていました。
経営理念を刷新するタイミングと重なったこともあり、従業員エンゲージメントを定点的に計測するために、サーベイの導入を決断しています。
「経営理念の浸透度・実践度を把握すること」「従業員が日常的に感じている課題を把握し、改善に繋げること」を実施目的として取り組んだ結果、組織課題の可視化に効果を実感しています。改善に向けたディスカッションが進んでおり、執行役員や従業員が一体となって解決に取り組める体制づくりのきっかけにもなっているそうです。
【関連コンテンツ】
おすすめの組織診断サーベイツール「HRBrain」

組織が持続的に成長するためには、現状を正確に把握し、課題を明確にした上で、適切な対策を講じることが不可欠です。しかし、従業員の意見を効率よく収集し、分析することは決して簡単ではありません。そこで、注目したいのが組織診断サーベイツールの活用です。
数あるサーベイツールの中でも、特におすすめしたいのが「HRBrain」です。HRBrainは、設問設計から配信、集計、分析まで、組織診断サーベイに必要な一連のプロセスを効率化できるため、人事担当者はより本質的な課題解決や施策実行に集中することができるようになります。
サーベイを「やるだけ」で終わらせない。組織を動かす仕組みに変えよう
サーベイは、実施すること自体が目的ではありません。得られたデータを組織改善に結びつけて初めて、本当の価値が生まれます。サーベイ結果を放置していては、従業員の信頼を失い、組織改革の機会を逃してしまうでしょう。まずは、調査後すぐに結果を可視化し、課題を特定しましょう。
そして、アクションプランを立案し、改善施策をスピーディーに実行しましょう。サーベイを「やるだけ」で終わらせず、組織を動かす仕組みに変革していきましょう。







