複線型人事制度とは?メリットとデメリットや導入方法と事例を解説
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- 複線型人事制度とは
- 複線型人事制度のキャリアコース設定
- キャリア志向
- 適性
- 職群
- 複線型人事制度のメリット
- 複線型人事制度で企業が得られるメリット
- 複線型人事制度で従業員が得られるメリット
- 複線型人事制度のデメリット
- 複線型人事制度の企業でのデメリット
- 複線型人事制度の従業員でのデメリット
- 複線型人事制度の導入方法
- 必要な人材やスキルを定義する
- キャリアコースを作成する
- 制度を見直しスキルと評価や報酬を紐づける
- 被評価者と評価者向けに説明会や研修を行う
- コースごとに従業員を配置する
- 採用方法を変更する
- 複線型人事制度の導入事例
- 株式会社りそなホールディングス
- 中野区(自治体)
- 東日本旅客鉄道株式会社
- 複線型人事制度の導入には人事制度の抜本的な見直しが必要
複線型人事制度とは、1つの企業に複数のキャリアコースが設けられている人事制度のことで、多くのキャリアパスを設けることで、自社内で多様な人材を育成することが可能です。
この記事では、複線型人事制度とはどのような制度なのか、メリットとデメリット、複線型人事制度の導入方法や企業での導入事例について解説します。
ゼロから作る人事制度設計マニュアル
複線型人事制度とは
複線型人事制度とは、1つの企業に複数のキャリアコースが設けられている人事制度のことです。
複数のキャリアパスを用意することで、自社内で多様な人材を育成することができます。
また、複線型人事制度に対応する制度として「単線型人事制度」があります。
単線型人事制度は、その名の通り、キャリアコースが単線(ひとつ)しかない人事制度のことです。
▼「人事制度」についてさらに詳しく
人事制度設計のポイントとは!設計方法を3つの人事制度を交えて解説
複線型人事制度のキャリアコース設定
複線型人事制度のキャリアコース設定は、「キャリア志向」「適性」「職群」の3つの核となる考え方をもとに設定されます。
それぞれの、複線型人事制度でのキャリアコース設定について確認してみましょう。
複線型人事制度のキャリアコース設定
キャリア志向
適正
職群
キャリア志向
キャリア志向に重点を置いた複線型人事制度について確認してみましょう。
従業員のキャリア志向によって、「総合職」「一般職」などから選べるコースが設定されています。
総合職は、社内の中核を担う業務を担当し、一般職は総合職のサポートを担当します。
そのため、総合職の方が責任が重く、ジョブローテーションの観点から転勤が多いという特徴があります。
一般職は内勤のため、基本的に異動や転勤がありませんが、サポート業務がメインのため、総合職に比べて、給与が低く設定されている場合があります。
▼「ジョブローテーション」についてさらに詳しく
ジョブローテーションとは?意味や人事異動との違いや制度の仕組みを解説
適性
適性に重点を置いた複線型人事制度について確認してみましょう。
従業員の適性や希望によって、「マネジメント業務を担当する」「職種の専門性を高める」のいずれかのコースを選ぶことができます。
特に、エンジニアはプロジェクトマネジメントよりも「技術に携わりたい」という傾向が強いため、マネジメント以外のコースを用意することで、技術力のある人材の流出を防ぐことができます。
「マネジメント」以外のコースには「スペシャリスト」「エキスパート」など、企業によって異なる名称がついています。
▼「業務適性」についてさらに詳しく
業務適性とは?意味と見極める方法やメリット職種別の必要スキルを解説
職群
職群に重点を置いた複線型人事制度について確認してみましょう。
職群とは、企業や団体で働く従業員を、職務上の「一定の基準」で分類したグループのことを指します。
具体的な職群の名称は企業によって異なり、「営業職」「技術職」のように、従事する業務に由来する場合があります。
従業員を職群に分けるだけではなく、分類ごとに「等級」や「報酬」を設定するなど、企業独自の職群に応じて複線型人事制度を構築する場合もあります。
▼「職群」についてさらに詳しく
職群とは?職群の定義や実際の企業での事例を解説
キャリアコースの設定に役立つ従業員データの管理
⇒「人材データベース管理入門」資料ダウンロード
複線型人事制度のメリット
複線型人事制度を設定することで得られるメリットについて、企業と従業員それぞれのメリットについて確認してみましょう。
複線型人事制度で企業が得られるメリット
複線型人事制度で企業が得られるメリットについて確認してみましょう。
企業に必要なスペシャリストの育成ができる
複線型人事制度を導入することで、企業が展開する事業に応じて、専門知識を持つ人材を育成することができます。
近年、「マネジメントではなく、自身のスキルを磨いていきたい」と専門性を高めるキャリアを選択する人材が増えています。
複線型人事制度は、そうした従業員のニーズにもマッチしていると言えるでしょう。
複線型人事制度を導入することで、企業は技術の高い人材の流出を防ぐだけでなく、ノウハウの蓄積や、技術の高度化も期待できます。
▼「人材育成」についてさらに詳しく
人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説
企業の経営戦略と連動した人材育成を実現する方法
⇒「失敗しない人材育成ハンドブック」資料ダウンロード
職位のポスト不足の解消
複線型人事制度を導入することで、職位のポスト不足の解消をすることができます。
ピラミッド型組織で、1つしかキャリアコースがない場合、職位のポストが不足する恐れがあります。
その場合、事業の貢献度が高い人材を昇進させたくても、すでにそのポストはほかの従業員に占められている状態になっている可能性があります。
また、日本企業の場合、よほどのミスや不祥事がない限り、一度昇進させたポストから降ろすことがないという傾向があることも、企業のポスト不足に拍車をかけていると言えます。
しかし、複線型人事制度の場合、それぞれにキャリアコースが定められているため、主任や課長といった「職位(ポスト)」に「昇進」させるのではなく、職群に設定された「等級」に対して「昇格」させることができます。
ポスト不足を補うことは、従業員のモチベーションアップにも繋がります。
▼「モチベーション」についてさらに詳しく
仕事のモチベーションを上げる方法とは?元人事が実体験をもとに解説
複線型人事制度で従業員が得られるメリット
複線型人事制度で従業員が得られるメリットについて確認してみましょう。
希望のライフスタイルに応じてキャリアを選べる
複線型人事制度を導入することで、「ワークライフバランスを充実させたい」「出産や妊娠を見越して転勤のないキャリアコースを選択したい」など、希望のライフスタイルに応じてキャリアコースを選択することが可能です。
また、企業が複線型人事制度を導入することによって、ライフスタイルによって業務の継続が難しくなった場合、従業員は退職ではなく「総合職から一般職へ」とコースを変更をすることもできます。
また、近年の働き方の多様化を受けて、総合職よりも一般職の方が倍率が高いといった現象も起きています。
モチベーションが向上する
複線型人事制度を導入することで、従業員のモチベーションが向上するでしょう。
「マネジメントが苦手でも、専門性を高めることによって会社から評価される」「社内にロールモデルとなる先輩社員がいる」ということは、従業員のモチベーションアップに繋がります。
「キャリアや専門性を高めるために、具体的に何をすれば良いのか」という情報が企業から提供されているため、成長の機会も多いと言えるでしょう。
▼「ロールモデル」についてさらに詳しく
ロールモデルとは?意味やメリットと女性リーダーの例を解説
効果的な人材育成につながる人事評価の方法
⇒「人材を成長させる人事評価のポイント」資料ダウンロード
報酬を与えられる機会が増える
複線型人事制度を導入することで、より細やかな成長機会や評価を得ることができます。
そのため、1つしかキャリアコースがない場合に比べて、報酬を与えられる機会が多いと言えるでしょう。
複線型人事制度のデメリット
複線型人事制度のデメリットについて、企業と従業員それぞれでのデメリットについて確認してみましょう。
複線型人事制度の企業でのデメリット
複線型人事制度の企業でのデメリットについて確認してみましょう。
給与体系の抜本的な見直しや評価システムの構築と運用が必要
複線型人事制度を導入するためには、複数のキャリアコースを用意する必要があります。
そのためには、コースごとに給与体系を見直し、給与体系に連動した評価システムの構築が必要になります。
また、新たに評価システムを導入する場合は、継続的な運用コストがかかるでしょう。
複線型人事制度の導入には、抜本的な人事制度の改革や見直しが必要なため、時間と手間がかかります。
▼「人事評価」についてさらに詳しく
人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介
人事評価システムの導入方法を解説
⇒「ゼロから始める人事評価」資料ダウンロード
評価や運用のルールが複雑化する
複線型人事制度は、複数のキャリアコースを同時に展開する必要があります。
「公平さ」を意識しながら、それぞれの評価制度のルールを把握する必要があるため、1つのキャリアコースしかない場合に比べて、運用が複雑化すると言えるでしょう。
報酬を与える機会が多くなり人件費が増加する傾向がある
複線型人事制度(適性・職群)の場合、会社に対する貢献度に応じて報酬を与える機会が増えます。
そのため、1つしかキャリアコースがない場合に比べて、人件費が増加する傾向にあります。
複線型人事制度の導入前に、綿密な試算を行う必要があると言えます。
人事制度の設計や見直しに
⇒「ゼロから作る人事制度設計マニュアル」資料ダウンロード
従業員へ周知する機会を設ける必要がある
新たに複線型人事制度を導入する場合、従業員に周知を行う必要があります。
複線型人事制度の導入には、従業員の同意と理解が必要不可欠です。
人事制度が変化する場合、従業員は「今までと何がどう変わるのだろうか」と不安を抱きます。
新しい人事制度を導入する際は、導入の背景や目的、従業員自身のメリットなどを説明して、安心させましょう。
また、評価者と被評価者のための複線型人事制度の資料などを用意して、スムーズな運用のための準備を行う必要があります。
複線型人事制度が定着するまで時間がかかる
複線型人事制度の定着には時間がかかります。
また、従業員の説明会などの周知のほかに、採用方法を変える必要があります。
いきなり全てを変更するのではなく、まずは1つの職群からテスト的に導入を開始するなど、複線型人事制度を「どのように実施するのか」を慎重に検討するようにしましょう。
複線型人事制度の定着には時間とともに手間がかかることを頭に入れて、余裕を持ったスケジュールを策定するようにしましょう。
複線型人事制度の従業員でのデメリット
複線型人事制度の従業員でのデメリットについて確認してみましょう。
他のキャリアコースに移ることが難しい
従業員にとって、1度キャリアコースを選択した後に、他のキャリアコースに移行するのが難しい場合があります。
例えば、一般職から総合職にキャリアチェンジする場合、同一の企業であっても、試験や面接を行うことが一般的です。
評価制度が複雑化して理解しにくい
複数のキャリアコースがある場合、複雑化した評価制度の把握は、会社側だけでなく従業員の負担にもなります。
特に、入社後に評価制度が大きく変わった場合、評価者研修などの受講や、評価者や被評価者として1から覚えることが多く、戸惑うこともあるでしょう。
▼「評価者研修」についてさらに詳しく
評価者研修とは?人事評価の必要性と期待されることやメリットを解説
評価者の育成に欠かせない「評価者研修」
⇒「評価者研修に盛り込むべき必須コンテンツ」資料ダウンロード
待遇に関して不平等を感じる場合もある
もし、会社が定めたキャリアコースと、職務の実態に乖離がある場合、「結局、同じような仕事をしているのに、こんなにも給与が違う」と従業員が不満を感じてしまう場合があります。
そうした不満を従業員が持たないためにも、複線型人事制度を導入する場合は、それぞれの職務の範囲や責任のあり方などを明確に定める必要があります。
複線型人事制度の導入方法
複線型人事制度の導入方法について確認してみましょう。
複線型人事制度の導入方法
- 必要な人材やスキルを定義する
- キャリアコースを作成する
- 制度を見直しスキルと評価や報酬を紐づける
- 被評価者と評価者向けに説明会や研修を行う
- コースごとに従業員を配置する
- 採用方法を変更する
必要な人材やスキルを定義する
事業成長のために「必要な人材やスキルはなにか」を定義しましょう。
事業計画に基づき、どの事業領域に人員を配置するのかを決定し、各ポジションに求められる役割やスキルを割り出します。
キャリアコースを作成する
求められる役割やスキルに対して、適切なキャリアコースを作成しましょう。
スキルの項目の洗い出しに関しては、現場の従業員の協力が欠かせません。
また、複線型人事制度のメリットを理解してもらうためにも、複線型人事制度導入の前段階から従業員を巻き込むことが重要です。
従業員の意見を反映する制度になるよう、従業員と積極的に意見を交換をするようにしましょう。
制度を見直しスキルと評価や報酬を紐づける
従来の人事制度を見直し、新たに設定したスキルと、複線型人事制度の「評価ランク」や「報酬」を紐づけましょう。
キャリアコースごとに、求められるスキルの項目を追加し、柔軟に評価のランクや報酬を設定しましょう。
キャリアコースごとの特色が、企業自体の魅力となります。
また、自社の基準だけではなく、「人材の市場価値」といった外部からの視点も持ち込むことで、複線型人事制度導入の失敗を回避することができます。
被評価者と評価者向けに説明会や研修を行う
複線型人事制度の概要が整ったら、従業員向けに「複線型人事制度を導入したことによって何が変わるのか」「何をしなければならないのか」などを説明しましょう。
また、被評価者と評価者向けに研修を行うことも重要です。
評価制度の運用に欠かせない「評価者研修」のポイント
⇒「評価者研修に盛り込むべき必須コンテンツ」資料ダウンロード
コースごとに従業員を配置する
複線型人事制度が整った後、キャリアコースごとに従業員の配置を行います。
配置の際には、本人の希望だけでなく、適性を考慮するようにしましょう。
また、一方的に配置の通知を行うのではなく、従業員との面談を通じて、納得を促すことも重要です。
複線型人事制度の導入が、従業員のモチベーション低下に結びつかないよう、配慮を行いましょう。
また、キャリアコースの基準を満たさない従業員は、そのコースの選択ができない旨の通知や判断を徹底するようにしましょう。
採用方法を変更する
複線型人事制度の導入後は、採用を制度に即したものに変更する必要があります。
総合職と一般職では、異なった応募条件を設けている企業もあります。
人事制度設計のポイントを解説
⇒「ゼロから作る人事制度設計マニュアル」資料ダウンロード
複線型人事制度の導入事例
複線型人事制度を導入している企業の導入事例について確認してみましょう。
株式会社りそなホールディングス
株式会社りそなホールディングスは、2021年4月に人事制度を改定しました。
その目的は、「従業員ひとりひとりがビジネス環境の変化に対応しプロフェッショナルとして成長すること」です。
そして、従業員が多様な分野でプロフェッショナルを目指せるように、「渉外・融資外為」「サービス」「事業再生」など、業務分野別の全19コース(2023年4月より全20コース)からなる「コース制」を導入しました。
また、社員、スマート社員(社員と比較して勤務時間や勤務範囲を限定できる正社員)、パートナー社員(パートタイマーなど)に共通の人事評価制度を適用し、それぞれが柔軟に登用や転換を経て職種を変更できる制度を整えています。※2024年3月時点の情報です
(参考)りそなホールディングス「人事制度」
中野区(自治体)
中野区は、2022年3月に「区の目指す将来像」の実現を担う職員の総合的な人材マネジメントのため「中野区人材育成基本方針」を策定しました。
「ゼネラリスト職員」「エキスパート職員」「特定部門エキスパート職員」を設定し、「新規採用から10年目までの職員について、本人の適性判断やキャリア形成期間として3~5年を基本に異なる部門(①企画・計画、②内部管理、③窓口・相談、④事業執行の分類で2つ以上)の職務を経験させ、育成を図る」としています。
ゼネラリスト職員…行政全般に精通。3年〜5年程度で様々な部署に異動。
エキスパート職員…特定の業務(福祉・生活支援、まちづくり等)に精通。異動は限定的に行う。
特定部門エキスパート職員…特定の部門(①企画・計画、②内部管理、③窓口・相談、④事業執行)に精通。異動は原則部門内において、3年〜5年程度で他の部や課に異動。
※2023年8月時点の情報です
(参考)中野区「【全体版】中野区人材育成基本方針(令和4年3月策定)」
東日本旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社は、2012年に人事と賃金制度の抜本的な見直しを実施しました。
等級試験を廃止し、管理者の補佐役としての「主務職」、人材育成のプロとしての「技術専任職」を新設するなどの複線型人事制度を導入しました。
あわせて、昇進資格の短縮や飛び級制度の新設なども実施し、社員のバックグラウンドに関わらず公平なチャンスの付与を実現しました。※2015年3月時点の情報です
(参考)経済産業省「ダイバーシティ経営企業100選」
複線型人事制度の導入には人事制度の抜本的な見直しが必要
複線型人事制度とは、複数のキャリアコースを選べる人事制度です。
複線型人事制度では、「キャリア志向」「適性」「職群」の3つのタイプがキャリアコースの基本となっています。
複線型人事制度のメリットは、事業に必要なスペシャリストを育成できること、ポスト不足が解消できることで、従業員にとっても、成長の機会が多く、モチベーションが上がりやすいという利点があります。
複線型人事制度のデメリットは、複数のキャリアコースを運用するため、評価制度やルールが複雑化しやすいという点で、制度を整えるために手間と時間がかかるだけでなく、従業員の同意と理解が必要になります。
また、複線型人事制度の導入には、今ある人事制度の抜本的な見直しが欠かせません。
「HRBrain コンサルティング」では人事制度の課題を人事のプロと解決、納得度の高い人事評価制度の構築を実現します。
原稿の人事制度の見直しをし自社に最適な人事制度の構築をしたい、新しく人事制度を導入したものの制度の運用が上手くいかない…人事制度に関するあらゆる課題を解決します。
HRBrainコンサルティングの特徴
業種・規模・目的に応じた100社100通りの柔軟な人事評価制度構築
評価制度は経営層と従業員が対話するための共通言語であると捉え、お客様の「今」と「未来」に最適な制度設計を実現します。
制度構築だけでなく、制度定着まで中長期的に運用サポート
評価制度の構築だけで終わらず、制度の移行スケジュールの作成や制度説明会、評価者・被評価者研修に加え、制度の定着までをサポートし、組織の成長を生み出します。
“シリーズ累計2,500社以上”※ 業界トップクラスのサービス運用実績!
創業以来、累計導入社数2,500社以上※であるHRBrainシリーズ(タレントマネジメントシステム、組織診断サーベイ、労務管理クラウドなど)の運用支援をしています。あらゆる業種業態の成功事例・失敗事例を共有しながら、お客様とともに各社の特徴・ご要望に合わせた評価制度構築を提供します。※2023年9月時点
ゼロから作る人事制度設計マニュアル
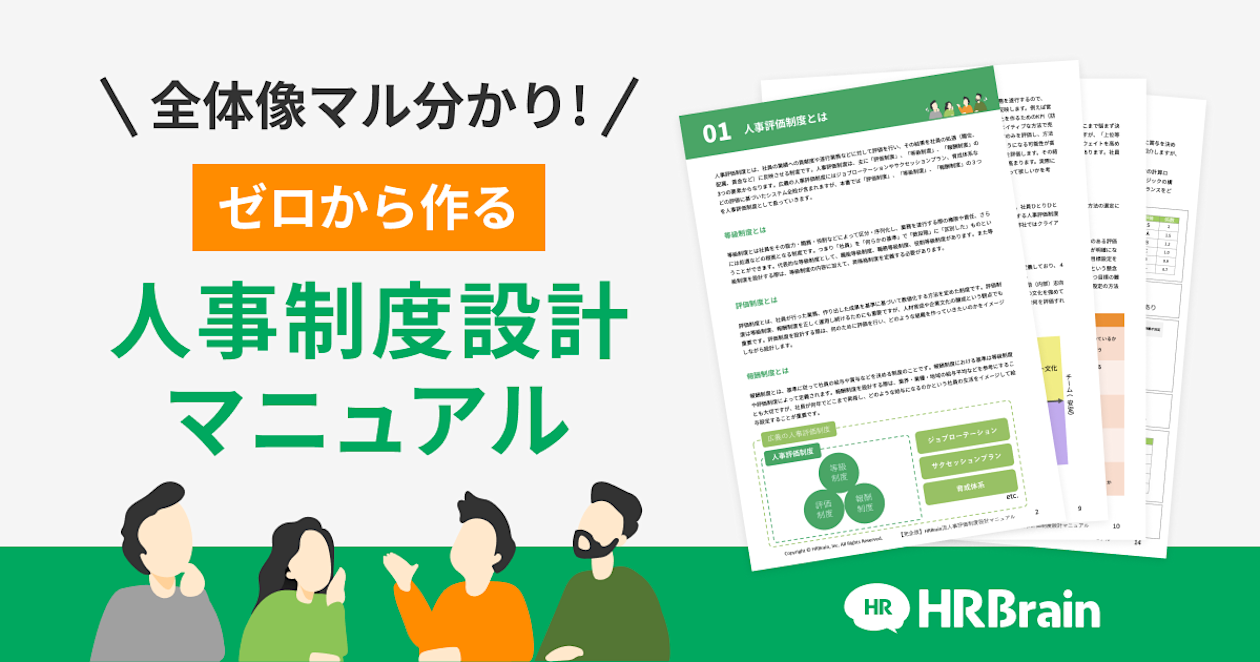
▼「HRコンサルタント」についてさらに詳しく
HRコンサルタントとは?選定のポイントや依頼するメリットについて
▼「HRビジネスパートナー(HRBP)」についてさらに詳しく
HRビジネスパートナー(HRBP)とは?人事のトランスフォーメーションを実現する方法を解説






