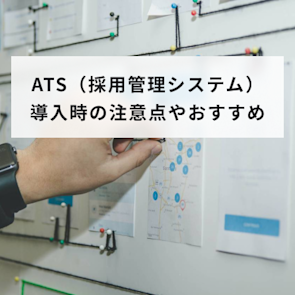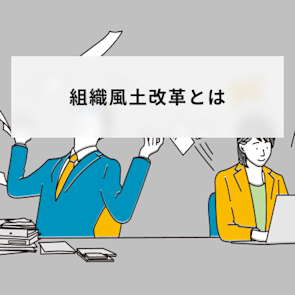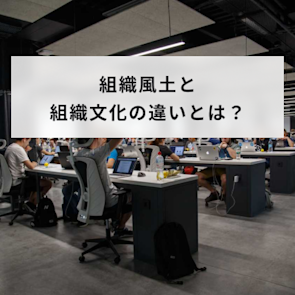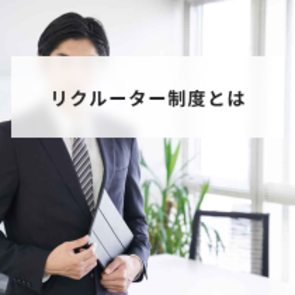ジョブ型人事制度とは?メンバーシップ型とどう違う?メリット・デメリットや導入背景を紹介
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- ジョブ型人事制度とは
- 日本企業の従来の雇用制度は「メンバーシップ型」
- ジョブ型とメンバーシップ型との違い
- ジョブ型人事制度が注目される背景
- キャリアの多様化による終身雇用制の崩壊
- リモートワーク普及による成果主義の働き方の浸透
- グローバルスタンダードへの対応と人材獲得競争
- ジョブ型人事制度のメリット
- 賃金の適正化が可能になる
- 無駄な人員を削減し組織を効率化できる
- ジョブ型人事制度のデメリット
- 日本企業の「強み」が失われる
- 誰も対応しない仕事が発生する
- ジョブ型人事制度が採用や人材育成に与える影響
- ジョブ型人事制度が採用に与える影響
- ジョブ型人事制度が人材育成に与える影響
- ジョブ型人事制度の導入方法
- 職務と職務要件を定義する
- 職務に対する報酬を設計する
- 管理職から導入する
- ジョブ型人事制度の導入事例
- ジョブ型人事制度の導入事:株式会社日立製作所
- ジョブ型人事制度の導入事:富士通株式会社
- ジョブ型人事制度の導入は慎重に
ジョブ型人事制度では、その職務に対する、会社の中での仕事内容、責任範囲、役割、期待される成果などが「ジョブディスクリプション(職務記述書)」によって、ひとつひとつ定義され、そうした仕事内容と責任、役割によって報酬が定められ、責任の重さや仕事量によって報酬が上下することが特徴です。
ジョブ型人事制度は、多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。
特に、雇用の流動性がまだまだ低い日本では、従来のメンバーシップ型の方が企業の強みを発揮できる場合もあるため、慎重に検討してジョブ型人事制度を導入するかどうかを決める必要があります。
この記事では、ジョブ型人事制度とは、メリットとデメリット、注目される背景、ジョブ型人事制度の導入方法、日本企業での導入事例について解説します。
「ジョブ型人事制度」導入の検討など人事制度の課題を人事のプロと解決
ジョブ型人事制度とは
ジョブ型人事制度とは、職務(ジョブ)に合う人材を採用する人事制度のことです。
職務とは担当する仕事と役割を意味します。
ジョブ型人事制度では、その職務に対する、会社の中での仕事内容、責任範囲、役割、期待される成果などがひとつひとつ定義されています。
この職務を定義したものを、「ジョブディスクリプション(職務記述書)」と言います。
また、ジョブ型人事制度では、そうした仕事内容と責任、役割によって報酬が定められ、責任の重さや仕事量によって報酬が上下することが特徴です。
ジョブ型人事制度では、「ジョブ型雇用」で職務を担える人材を採用する、または配置することで組織を運用します。
▼「ジョブディスクリプション(職務記述書)」についてさらに詳しく
ジョブディスクリプション(職務記述書)とは?書き方や必要性と注意点について解説
▼「ジョブ型雇用」についてさらに詳しく
ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型雇用との違いやメリットとデメリットを解説
日本企業の従来の雇用制度は「メンバーシップ型」
日本企業では、昔から「メンバーシップ型」での採用を進めてきました。
メンバーシップ型とは、人をまず採用し、さまざまな仕事を経験させたうえで、業務適性を見極め、最終的にその人に適した仕事に人材配置をします。
世界的にはジョブ型が中心的であるのに対し、日本はいわゆる「察する」文化であるハイコンテクストカルチャーや単一民族であることを背景に、メンバーシップ型という独自の雇用制度が発達してきたのです。
▼「業務適性」についてさらに詳しく
業務適性とは?意味と見極める方法やメリット職種別の必要スキルを解説
▼「人材配置」についてさらに詳しく
適材適所を実現する「人材配置」とは?実践的な方法とポイントを人事目線で解説
▼「コンテクスト」についてさらに詳しく
コンテクストとは?意味と使い方や実例を解説
人材の「最適配置」のポイントを5分で解説
⇒「人事異動の業務効率化と『最適配置』実現のキーポイント」資料ダウンロード
ジョブ型とメンバーシップ型との違い
メンバーシップ型雇用は、「業務適性」の考えに基づく人事制度です。
一方でジョブ型雇用は、職務に対して適切な人を配置する「適所適材」の考え方と言えます。
ジョブ型とメンバーシップ型は正反対の制度と言えるでしょう。
ジョブ型人事制度が注目される背景
日本では2020年頃からジョブ型人事制度が注目されるようになりました。
ジョブ型人事制度が注目されるようになった背景について確認してみましょう。
ジョブ型人事制度が注目される背景
キャリアの多様化による終身雇用制の崩壊
リモートワーク普及による成果主義の働き方の浸透
グローバルスタンダードへの対応と人材獲得競争
キャリアの多様化による終身雇用制の崩壊
日本のジョブ型人事制度の背景を知るためには、まず世界的な「ダイバーシティ(多様化)」への取り組みの歴史を知る必要があります。
1960年代にアメリカで公民権運動が起こり、世界的に人種や宗教、思想の違いを認める素地ができあがりました。
その後、それまで男性中心社会だったアメリカで女性の社会進出がはじまり、1980年代から90年代にかけてアメリカではダイバーシティを尊重する風土が生まれました。
それに遅れて日本でも、1990年代から女性の社会進出が始まり、2010年代に政府が「女性活躍推進法」を施行しました。
それにより日本でもダイバーシティと働き方の多様化が推進され、転職や副業など多様な働き方が認められるようになりました。
もはや同じ会社で長く勤め続ける終身雇用制は当たり前でなくなり、企業も時代に合わない従来のメンバーシップ型を維持することが難しくなり、ジョブ型人事制度が注目されるようになりました。
(参考)厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
リモートワーク普及による成果主義の働き方の浸透
また2019年に新型コロナウイルス感染症が発生し、日本でも感染拡大防止のために2020年からリモートワークが急速に普及しました。
リモートワークでは、これまで日本企業が得意としてきた「すり合わせ」を中心とした対面での人材マネジメントが難しくなりました。
また、働き方も時間や場所にとらわれなくなるため、成果を重視した成果主義の働き方が広まったのです。
これまでは「会社に行けば仕事をしている」と思われていましたが、会社に行かないことで成果を出す人と出さない人が明確になりました。
そのため、従来の人をまず採用してから仕事に配置するメンバーシップ型よりも、その仕事ができる人を職務にアサインするジョブ型人事制度が注目されるようになりました。
▼「リモートワーク」についてさらに詳しく
テレワークとリモートワークと在宅勤務って何が違う?言葉の意味と違いを解説!
▼「成果主義」についてさらに詳しく
成果主義とは?メリットとデメリットや能力主義との違いをわかりやすく解説
リモートワークでのメンバー育成に
⇒「1on1ミーティング入門書」資料ダウンロード
グローバルスタンダードへの対応と人材獲得競争
2000年代から急速にITが進歩し、世界中の優秀な人材をLinkedinのようなSNSやインターネットから見つけられるようになりました。
また、リモートワークの普及によって優秀な人材を場所に関係なく採用できる環境が調いました。
それによって、グローバル企業が世界中から優秀なエンジニアなどの人材を集めるようになり、世界的な人材獲得競争が起きています。
例えば、特に優秀なエンジニア人材のいるインドでは、FacebookやGoogleなどの世界的なIT企業がインドの学生に積極的にアプローチして自社のエンジニアとして採用しています。
こうした世界的な人材獲得競争に対応するには、日本企業もグローバルスタンダードであるジョブ型人事制度を導入する必要があります。
日本では在籍年数や等級によって報酬が決まりますが、世界では仕事内容に対して報酬が決まる考え方が主流だからです。
こうした社会環境の変化により、ジョブ型人事制度は日本でも注目されるようになりました。
ジョブ型人事制度のメリット
ジョブ型人事制度はグローバルスタンダードな制度ですが、日本企業にとってどのようなメリットがあるのか確認してみましょう。
ジョブ型人事制度のメリット
賃金の適正化が可能になる
無駄な人員を削減し組織を効率化できる
賃金の適正化が可能になる
日本企業がジョブ型人事制度によって最も恩恵を受けると考えられるのが賃金の適正化です。
これまでは従業員が会社に所属していれば、在籍年数や等級に応じてある程度一律の賃金を支払う必要がありました。
この場合、仕事の成果や能力に限らず賃金を支払うため、結果的に日本企業はパフォーマンスの低い人材にも割高な賃金を支払い、パフォーマンスが高い人材には割安な賃金を支払ってきました。
ジョブ型人事制度を導入すれば、職務の難易度や責任に応じた適正な賃金の支払いが可能になります。
無駄な人員を削減し組織を効率化できる
ジョブ型人事制度では会社の中の職務をすべて定義します。
そのため、必要な職務に対して必要な人材だけを雇用することができるというメリットがあります。
従来のメンバーシップ型では、人に対して仕事をアサインするため、人の数だけ仕事を増やす必要がありました。
そのため本来は必要のない仕事が増えてしまい、組織パフォーマンスの低下につながっているケースもありました。
このように、ジョブ型人事制度は、企業の収益性と組織の生産性を高めることができます。
これらのメリットをいかすために、ジョブ型雇用を進めたい場合は、ジョブディスクリプションの作成や、適切な人事評価の制度設計が不可欠です。
そのような場合、組織人事コンサルティングを利用することがおすすめです。
▼「生産性」につていさらに詳しく
生産性とは?意味や向上させる方法と高めるための施策事例を解説
▼「人事コンサルティング」についてさらに詳しく
人事コンサルタントは必要?人事コンサルに依頼するメリットや選び方を解説
人事制度の課題を人事のプロと解決
⇒「HRBrain コンサルティング」
ジョブ型人事制度のデメリット
ジョブ型人事制度のデメリットについて確認してみましょう。
ジョブ型人事制度のデメリット
日本企業の「強み」が失われる
誰も対応しない仕事が発生する
日本企業の「強み」が失われる
ジョブ型人事制度では日本企業の強みが失われるデメリットがあります。
日本企業では職務をあえて定義しないことで、お互いに空気を読んで助け合う組織マネジメントが行われてきました。
こうした互いの持つ知恵を出し合う「すり合わせ」は、特に日本のものづくりを支え、日本を世界的な経済大国へと成長させてきました。
しかし、仕事内容と責任範囲が明確になるジョブ型人事制度では、自分の仕事は自分で完遂することが求められます。
実際に欧米企業では、ジョブディスクリプションに書かれた自分の仕事だけをこなし、他人の仕事を助けない働き方をすることは悪いことではなく、むしろ当然のこととされています。
日本企業がジョブ型人事制度を導入した場合、これまでの日本人独特の助け合いの文化が失われるリスクがあります。
誰も対応しない仕事が発生する
ジョブ型人事制度では、会社の職務が全て定義されるため、ジョブディスクリプションに書かれていない仕事はやらなくて良いという考え方です。
しかし、実際には仕事の繁閑によって、ジョブディスクリプションに書かれていない仕事でもやらなければならないシーンが発生します。
例えば、極端に言えば職場にゴミが落ちていたとしても、ジョブディスクリプションに職場の清掃について書かれていなければ、誰もゴミを拾う必要はありません。
どんなに職場が散らかっていても、掃除が職務として定義されていなければ掃除をする必要がないのです。
このように、ジョブ型人事制度を導入すると、ジョブディスクリプションに書かれていない限り、誰も対応しない仕事が発生する恐れがあります。
ジョブ型人事制度が採用や人材育成に与える影響
ジョブ型人事制度はこれまでの日本企業における採用や人材育成のあり方に大きな変化をもたらします。
実際にどのような影響があるのか確認してみましょう。
ジョブ型人事制度が採用に与える影響
ジョブ型人事制度では、「優秀な人材を採用できる可能性が広がる一方で、人材不足に陥るリスクがある」ということがいえます。
ジョブ型の採用では職務に合致した優秀な人材を獲得できるチャンスが広がります。
従来は年齢が若い人材は、例え市場価値が高い人材だとしても割安な賃金で採用してきました。
そのため若手優秀人材の早期離職を招くケースがありました。
しかしジョブ型人事制度では、職務に応じて報酬を設定できるため、若くて優秀な人材も高い報酬水準で採用できます。
高い報酬水準を提示できれば、より優秀な人材を採用できるだけでなく、早期離職の可能性も低くなります。
一方でジョブ型では、その職務を担える人材が市場に出回っていることが前提条件になります。
欧米企業では人材の流動性も高く、転職市場も活発なため、職務に合った人材の調達は比較的容易ですが、転職市場が欧米企業ほど活発ではない日本企業ではジョブ型人事制度の導入によって短期的に人材不足に陥る可能性があります。
▼「早期離職」についてさらに詳しく
早期離職の理由と問題とは?離職の原因と中途採用の定着率を上げる方法
早期離職の原因と対策について解説
⇒「原因と対策を考える若手の離職を防ぐためには」資料ダウンロード
ジョブ型人事制度が人材育成に与える影響
ジョブ型人事制度では、ひとりひとりの職務が定義されるため、能力開発も職務に合わせたものになります。
つまり職務が違えば、求められる能力や知識、スキルが異なるため、従来のメンバーシップ型のように従業員一律の教育や研修が難しくなります。
基本的には従業員自身が職務に必要な能力開発を自身で行う必要があります。
欧米企業では職務に合わせて自分で自分のスキルを高めることが当たり前とされており、会社側から研修を提供していない場合もあります。
このようにジョブ型人事制度では、従業員自身に能力開発が委ねられるため、従業員によって職務に対する知識やスキルにばらつきが起きることが考えられます。
▼「人材育成」につていさらに詳しく
人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説
ジョブ型人事制度の導入方法
ジョブ型人事制度は、メリットやデメリット、会社への影響をよく考えて導入する必要があります。
どのようにすればジョブ型人事制度をうまく導入できるのかについて確認してみましょう。
ジョブ型人事制度の導入方法
- 職務と職務要件を定義する
- 職務に対する報酬を設計する
- 管理職から導入する
職務と職務要件を定義する
「ジョブ型」の考え方に沿って、会社の中にある全ての職務と職務要件を定義しましょう。
職務と職務要件を定義する手順について確認してみましょう。
職務を定義する
職務は仕事内容と責任範囲、そして役職やレポートラインなどの役割を定義したものです。
職務分析をする
職務要件の定義をするための職務分析には、大きく分けて「記述法」「面接法」「観察法」の3つがあります。
従業員自身が職務を書きだす「記述法」
記述法は従業員自身が担当している職務を自ら書き出す方法で、もっとも少ない工数で職務を定義できるメリットがある一方で、職務内容の虚偽申告などの不正が起こる可能性があるデメリットがあります。
人事担当者や上司が職務をヒアリングする「面接法」
面接法は人事担当者または上司が対象者の職務をヒアリングして定義する方法で、不正を防げる一方で人事側の負担が大きくなるというデメリットがあるため、企業規模や組織風土によって検討しましょう。
人事担当者や上司が観察して職務を書きだす「観察法」
観察法とは、人事担当者または上司が実際の仕事を観察して職務を定義する方法で、客観的かつ正確で詳細な職務定義ができるメリットがある一方で、面接法よりも担当者の負担がさらに大きくなるというデメリットがあります。
職務要件をジョブディスクリプション(職務記述書)にまとめる
職務が定義できたら職務要件を「ジョブディスクリプション(職務記述書)」にまとめます。職務要件はその職務を担うために必要な能力や知識、スキル、人柄などの人材像をまとめたものです。ジョブディスクリプションは、職務と職務要件が記載されて初めて完成します。
また、自分の会社のジョブディスクリプションを作る余裕やノウハウがない場合には、コンサルタントに相談するのがおすすめです。過去の企業事例や経験を活かし、企業にぴったりのジョブディスクリプションのフォーマットや内容の制作が可能です。
ジョブディスクリプションの作成は「組織人事コンサルティング」に相談
⇒「HRBrain コンサルティング」
▼「組織風土」についてさらに詳しく
組織風土と組織文化の違いとは?良い組織にするためのポイントを解説
職務に対する報酬を設計する
ジョブ型人事制度の大きな特徴は職務によって報酬水準が決まることです。
ジョブディスクリプションが作成できたら、職務に対する報酬を設計しましょう。
報酬水準はその職務の市場価値を基準に決定します。
まずは営業、技術、人事などの職種によって報酬を決め、責任範囲や部下の人数、会社の中でのその職務の重要度などの重み付けを行って報酬を決定します。
仕事内容が増えるほど、責任範囲が広くなるほど、重要度が高くなるほどに報酬が上がるように設計しましょう。
管理職から導入する
これまでメンバーシップ型を運用してきた企業で、いきなり全従業員にジョブ型人事制度を導入してしまうと、混乱が生じる可能性があります。
まずは比較的、責任範囲が明確な管理職からジョブ型人事制度を導入していきましょう。
人事制度の設計や見直しのポイントを解説
⇒「ゼロから作る人事制度設計マニュアル」資料ダウンロード
ジョブ型人事制度の導入事例
ジョブ型人事制度の企業での導入事例について確認してみましょう。
ジョブ型人事制度の導入事:株式会社日立製作所
株式会社日立製作所は、ジョブ型人事制度を導入していることで有名な企業です。
グローバルな人事制度を設計するなかで、ジョブ型の人事制度が必要になりました。
ジョブ型人事制度の導入事:富士通株式会社
富士通株式会社は、2020年4月から幹部社員を中心にジョブ型人事制度を導入しました。
富士通も日立製作所と同様に、事業のグローバル化を背景にグローバルに統一された職務基準のもと、ジョブ型人事制度を導入することを決めています。
他にも、三菱ケミカル株式会社や株式会社ニトリなど、国内の大手企業でもジョブ型人事制度を導入している企業が多くあります。
▼「ジョブ型人事制度とジョブ型雇用の企業事例」についてさらに詳しく
【事例4選】ジョブ型雇用人事制度の実際とは?日本企業の代表的な事例を紹介
ジョブ型雇用の理想形!?Netflixの最強人事戦略と知るべき人事戦略トレンド
ジョブ型人事制度の導入は慎重に
ジョブ型人事制度では、その職務に対する、会社の中での仕事内容、責任範囲、役割、期待される成果などが「ジョブディスクリプション(職務記述書)」によって、ひとつひとつ定義されています。
ジョブ型人事制度は、そうした仕事内容と責任、役割によって報酬が定められ、責任の重さや仕事量によって報酬が上下することが特徴です。
ジョブ型人事制度は、「賃金の適正化が可能になる」「無駄な人員を削減し組織を効率化できる」などのメリットがある一方で、「助け合いなどの日本企業の強みが失われる」「誰も対応しない仕事が発生する」などのデメリットもあります。
また、同業他社がジョブ型人事制度の導入を決めたからといって焦って導入をする必要もありません。
雇用の流動性がまだまだ低い日本では、しばらくは従来のメンバーシップ型の方が日本企業の強みを発揮できる仕組みだと言えます。
本当に自社にとってジョブ型人事制度の導入が事業成長を実現するために最適な答えなのか、慎重に検討してジョブ型人事制度を導入するかどうかを決めましょう。
「HRBrain タレントマネジメント」は、ジョブ型人事制度に必須の「ジョブディスクリプション」の作成に必要な従業員ひとりひとりの職務内容をはじめ、あらゆるデータを一元管理し可視化します。
また、従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、研修などの育成履歴や、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、1on1やフィードバックなどの面談履歴、OKRなどの目標設定と進捗管理などを一元管理します。
従業員データをもとに、適材適所の人材配置や、自社に不足しているスキルや人材のピックアップも可能です。
HRBrain タレントマネジメントの特徴
検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現
運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。
柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を
従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。
人材データの見える化も柔軟で簡単に
データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。
▼「タレントマネジメント」についてさらに詳しく
【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説
タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで
▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ
【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ