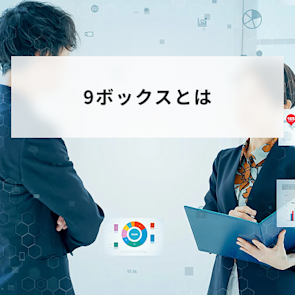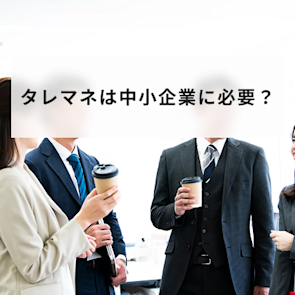等級制度とは?職能資格制度・職能等級制度・役割等級制度の3つの種類やメリットとデメリットと作り方について解説
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- 等級制度とは
- 等級制度を活用する目的
- 従業員の処遇を決定する基準になる
- 従業員が目指す業務レベルの基準になる
- 従業員の自律的なキャリア形成を促進する
- 等級制度の種類
- 職能資格制度
- 職務等級制度
- 役割等級制度
- 等級制度のメリットとデメリット
- 職能資格制度
- 職務等級制度
- 役割等級制度
- 等級制度の作り方
- 等級制度を導入する目的や方針を決定する
- 導入する等級制度の種類を決定する
- 等級の数を決定する
- 各等級の基準を決定する
- シミュレーションを行う
- 等級制度は自社の方針に合うものを選定することが重要
等級制度とは、従業員を能力、職務、役割などに応じてランク分けをする人事制度で、「職能資格制度」「職能等級制度」「役割等級制度」の3つの種類があります。
企業が事業を成長させ、発展していくためには、従業員のモチベーションを高めると同時に、適切な組織開発を進めることが大切です。
近年、従業員のモチベーションの維持や人事管理に関して、等級制度が重要と考えられています。
この記事では、等級制度の目的、「職能資格制度」「職能等級制度」「役割等級制度」の3つの種類の制度について、等級制度のメリットとデメリット、等級制度の作り方について解説します。
等級制度の導入に向けた従業員情報の一元管理なら
等級制度とは
等級制度とは、従業員を能力、職務、役割などに応じてランク分けをする人事制度で、「職能資格制度」「職能等級制度」「役割等級制度」の3つの種類があります。
等級制度は、従業員に対する責任や処遇の根拠となるもので、序列化した等級の高低によって給与や処遇が定められるため、人事評価制度のベースになるものと言えます。
また、人材育成や人材配置、企業風土の形成など、組織開発の役割を持ち、企業の経営戦略や事業戦略によって、導入する等級制度は異なります。
等級制度を通して従業員は、企業の「求める人材」や「期待する人材」を知ることができます。
人事制度を構成するものには、等級制度の他に、報酬制度と評価制度があり、人事制度の3本柱と考えられています。
▼「人事評価制度」についてさらに詳しく
人事評価とは?解決すべき9つの課題と人事評価制度のメリット5つを紹介
▼「人事制度」についてさらに詳しく
人事制度とは?目的と作り方や3つの要素について簡単に解説
▼「組織開発」についてさらに詳しく
組織開発とは?人材開発との違いや実施方法と企業事例を解説
▼「報酬制度」についてさらに詳しく
報酬制度(報酬管理)とは?目的や種類と人事管理や評価制度との関連性や適切な運用方法を解説
理想的な評価制度の運用
⇒「評価者研修に盛り込むべき必須コンテンツ」資料ダウンロード
等級制度を活用する目的
等級制度は、人事制度の土台にもなる重要な制度です。
なぜ企業で等級制度が重要と考えられ、活用されるようになったのか、企業が等級制度を活用する目的について、確認してみましょう。
等級制度を活用する目的
- 従業員の処遇を決定する基準になる
- 従業員が目指す業務レベルの基準になる
- 従業員の自律的なキャリア形成を促進する
従業員の処遇を決定する基準になる
企業が等級制度を活用する目的の1つ目は、「従業員の処遇を決定する基準になる」ことです。
等級制度では、各等級に達するために必要な要件の基準が明示されています。
基準を満たし、各等級に到達することで、等級に基づいた報酬額や職位が決まります。
また等級制度によって、処遇の基準が明確になると、従業員の納得感やエンゲージメントの向上につながることが期待できます。
▼「従業員エンゲージメント」についてさらに詳しく
従業員エンゲージメントとは?向上施策・事例も紹介
納得度の高い評価の実施方法
⇒「納得度の高い評価とは?」資料ダウンロード
従業員が目指す業務レベルの基準になる
企業が等級制度を活用する目的の2つ目は、「従業員が目指す業務レベルの基準になる」ことです。
等級制度では、各等級に達するために満たすべき基準が明示されています。
各等級の基準は、自社が「どのような人材を求めているか」というモデルを示すものでもあると言えます。
等級を上げて行くために、従業員自身が今後どのようなスキルや経験を身に付け、どのような人材になって行けば良いかという基準を示す意味でも、等級制度は大きな意味を持っています。
従業員の自律的なキャリア形成を促進する
企業が等級制度を活用する目的の3つ目は、「従業員の自律的なキャリア形成を促進する」ことです。
等級制度では、次の等級へランクアップするために必要なスキルが明示されているため、従業員が今後のキャリアプランを描く際に、具体的にどのようなアクションを起こすべきかを自分で考えることができるようになり、従業員のモチベーションの向上に役立ちます。
等級制度は、従業員の自律的なキャリア形成をサポートする意味でも重要と言えます。
▼「自律」についてさらに詳しく
自律型人材とは?自立との違いと育成方法について解説
▼「モチベーション」についてさらに詳しく
仕事のモチベーションを上げる方法とは?元人事が実体験をもとに解説
▼「キャリアプラン」についてさらに詳しく
キャリアプランとは?考え方と作り方の具体例や年代別の書き方について解説
等級制度の種類
等級制度は人事制度の一部で、3つの種類に分けられます。3つの等級制度について確認してみましょう。
等級制度の種類
- 職能資格制度
- 職務等級制度
- 役割等級制度
職能資格制度
職能資格制度とは、従業員の職務遂行能力をベースにした仕組みです。
職能資格制度では、特定の職務のみではなく、幅広い種類の職務に対応できることが評価の基準になり、勤続年数と職務遂行能力が比例して向上すると考えられています。
従来、日本で一般的だった「年功序列制度」や「終身雇用制度」が土台になっており、日本固有の考え方に近い制度と言えるでしょう。
職務等級制度
職務等級制度とは、担当する業務ごとに等級を設定し、遂行能力によって従業員を評価する制度です。
職務は業務のひとまとまりを指し、職務の難易度や責任レベルなどによって等級が決められます。
勤続年数などが評価に関係する職能資格制度とは異なり、勤続年数などとは無関係に、担当業務そのものが評価基準になる点が、職務等級制度の大きな特長です。
役割等級制度
役割等級制度とは、担当業務の役割に応じて等級が決まる制度で、「ミッション・グレード制」とも呼ばれます。
役割等級制度での役割とは「役職と職務」を指し、役割等級制度では各役割の内容や役割の達成度合いが評価の基準になります。
役割等級制度に画一的な仕組みはなく、具体的な役割の内容は企業によって異なります。
▼「役割等級制度」についてさらに詳しく
役割等級とはどんな制度?メリットとデメリットや制度の作り方と事例を解説
等級制度のメリットとデメリット
3つの等級制度には、それぞれのメリットとデメリットがあります。3つの等級制度のメリットとデメリットについて確認してみましょう。
職能資格制度
メリット
人材を長期的に確保できる
スピーディーな組織改編が行える
ゼネラリストを育成しやすくなる
デメリット
長期的に見ると人件費が高くなる
年功序列により若手のモチベーション低下の可能性がある
評価基準が曖昧になる
職務等級制度
メリット
給与と労働の関係が明確になる
人件費を抑えられる
スペシャリストの育成に役立つ
デメリット
人事担当者の負担が増える
従業員のモチベーションに影響する
中途半端に導入すると逆効果になるリスクがある
役割等級制度
メリット
合理的な人事評価が可能になる
組織の改編や社会全体の環境変化への柔軟性が高い
従業員の主体性や自発性を伸ばすことができる
デメリット
活用するための実績やノウハウが必要になる
役割の変更が生じた場合の運用に負担がかかる
従業員に不公平感が生じやすい
職能資格制度
メリット
人材を長期的に確保できる
職能資格制度のメリットは、「人材を長期的に確保できる」ことです。
職能資格制度は、年功序列や終身雇用の考え方が土台になっているため、従業員は長く勤め続け、多くのスキルや経験を身に付けることができれば、着実に等級を上げて行くことができます。
職能資格制度では、着実に等級を上げ、等級に応じた報酬や処遇を得ることができるため、従業員は安心して自社で働き続けることができることから、人材を長期的に確保することができます。
スピーディーな組織改編が行える
職能資格制度のメリットは、「スピーディーな組織改編が行える」ことです。
職能資格制度では、自社のあらゆる職務に対応できるということが評価されるため、多くの職種を経験し、幅広い職務に対応できる従業員を育成できる制度であると言えます。
そして、組織の改変を行いたい場合に、人員配置の検討を柔軟に行うことができるようになります。
スキルを持つ人材を外部に依頼することなく自社で確保できる点は、職能資格制度の大きなメリットと言えます。
▼「人員配置」についてさらに詳しく
【人材管理:人員配置編】人員配置のメリット・適切な手順や目的、ポイント
▼「人員配置計画」についてさらに詳しく
人員配置計画とは?メリット・やり方・注意点・種類まとめ
最適な人事配置を行うには
⇒「人事異動の業務効率化と『最適配置』実現のキーポイント」資料ダウンロード
ゼネラリストを育成しやすくなる
職能資格制度のメリットは、「ゼネラリストを育成しやすくなる」ことです。
職能資格制度では、幅広い職務に対応できることが評価の基準になるため、あらゆる部署や職種で経験を積んだゼネラリストを育成しやすくなります。
ゼネラリストは多くの業務経験に基づいた、多角的な視点や判断力を持っているため、ゼネラリストを育成できることは、事業成長の観点から企業にとって大きなメリットになります。
▼「人材育成」についてさらに詳しく
人材育成とは?何をやるの?基本的考え方と具体的な企画方法を解説
経営と連動した人材育成を実現する方法
⇒「失敗しない人材育成ハンドブック」資料ダウンロード
デメリット
長期的に見ると人件費が高くなる
職能資格制度のデメリットは、「長期的に見ると人件費が高くなる」ことです。
職能資格制度では、等級が下がることがほとんどなく、一般的に、長く勤めるほど等級が上がり、比例して従業員の報酬も高くなって行きます。
従業員の報酬が高くなっても、企業が急成長している時期であれば問題にならないかもしれませんが、業績が滞っている時期であれば、人件費の高さが事業の負担になる可能性があります。
年功序列により若手のモチベーション低下の可能性がある
職能資格制度のデメリットは、「功序列により若手のモチベーション低下の可能性がある」ことです。
職能資格制度は、長く勤め続けることで等級が上がる年功序列の性質があるため、勤続年数が浅い若手の従業員にとっては、等級を上げることに必然的に制約が生じてしまいます。
企業の中には、勤続年数に関係なく、業務の実績に基づいて評価を行う企業も多くあるため、年功序列の性質が強い職能資格制度を採用していると、若手従業員のモチベーションが低下してしまう可能性があるでしょう。
▼「モチベーション」についてさらに詳しく
モチベーションマネジメントとは?モチベーションを上げる方法や施策を解説
モチベーション管理システムとは?選び方についてのポイントを説明
評価基準が曖昧になる
職能資格制度のデメリットは、「評価基準が曖昧になる」ことです。
年功序列制度に近い職能資格制度では、業務上の実績やプロセスではなく、勤続年数や年齢などが評価基準に用いられることが多くあります。
客観的かつ明確な基準がないことから、評価基準が曖昧になってしまいます。
評価基準が曖昧な場合、評価が上司などの評価者の主観に左右されやすくなってしまいます。
客観的な評価を得られないことは、従業員の不満感やモチベーションの低下につながる可能性があるでしょう。
▼「評価者研修」についてさらに詳しく
評価者研修とは?人事評価の必要性と期待されることやメリットを解説
理想的な評価制度を実現する方法
⇒「評価者研修に盛り込むべき必須コンテンツ」資料ダウンロード
職務等級制度
メリット
給与と労働の関係が明確になる
職務等級制度のメリットは、「給与と労働の関係が明確になる」ことです。
職務等級制度では、職務内容を記載した「ジョブディスクリプション(職務記述書)」が作られ、従業員はジョブディスクリプションに記された業務のみに従事します。
また、給与は各職務内容のレベルに応じて設定されています。
勤続年数などで評価が決まる職能資格制度などと比較すると、給与と労働の関係性が明確であることから、従業員の納得感が高くなりやすい制度と言えます。
▼「ジョブディスクリプション(職務記述書)」についてさらに詳しく
ジョブディスクリプション(職務記述書)とは?書き方や必要性と注意点について解説
人件費を抑えられる
職務等級制度のメリットは、「人件費を抑えられる」ことです。
勤続年数に比例して等級が上がる職能資格制度では、勤続年数の長い従業員の割合が多くなるにつれて、人件費が高くなりがちです。
一方で職務等級制度では、スキルや経験を要する高いランクの職務に従事しない限り、等級が上がることはありません。
また、職務内容が明確であることから、従業員が自身の業務量を把握しやすくなります。
業務量を把握できると、業務の進め方を事前に計画できるため、労働時間を管理しやすくなります。
職務のレベルでのみ等級が上がることや、労働時間を管理しやすいことなどから、職務等級制度では人件費を抑えられることが期待できます。
▼「残業時間」についてさらに詳しく
残業時間の上限規制とは?上限を超えたときの罰則や36協定について分かりやすく解説
残業時間を削減する方法
⇒「残業を削減するには?知っておきたい7つのポイント」資料ダウンロード
スペシャリストの育成に役立つ
職務等級制度のメリットは、「スペシャリストの育成に役立つ」ことです。
職務等級制度では、担当する業務内容が明確にジョブディスクリプションに記載されているため、各従業員は自身の業務のみに専念できます。
また、職務等級制度では、担当職務に関する知識やスキルを習得することが、等級を上げることにつながります。
特定の業務に専念できることや、明確な評価基準によって従業員のモチベーションを高めやすいことなどから、職務等級制度はスペシャリストを育成しやすい環境づくりに役立つと言えるでしょう。
▼「スキル管理」についてさらに詳しく
スキル管理とは?目的や方法とスキルマップについて解説
▼「スキルマップ」についてさらに詳しく
スキルマップとは?そのメリットと導入方法・注目される背景を紹介
デメリット
人事担当者の負担が増える
職務等級制度のデメリットは、「人事担当者の負担が増える」ことです。
職務等級制度では、各従業員の職務内容を記載したジョブディスクリプションを作成する必要があります。
ジョブディスクリプションの作成では、各職務の分析や等級の区分、評価基準や評価項目の策定などを行わなければならず、多くの手間がかかります。
また、職務内容に変更が生じた際は、ジョブディスクリプションを修正する必要があります。
従業員のモチベーションに影響する
職務等級制度のデメリットは、「従業員のモチベーションに影響する」ことです。
職務等級制度では、担当職務によって等級が決まるため、長年勤め続けるのみでは処遇や報酬が上がって行きません。
従来の年功序列制度になじんでいて、特に勤続年数の長い従業員にとっては、職務等級制度ではモチベーションを維持することが難しい場合があります。
また、職務等級制度ではジョブディスクリプションによって、担当する業務内容が明示されます。
明示された職務をこなすことが評価につながることから、ジョブディスクリプションに記載されていない業務について、積極的に取り組まなくなる場合があります。
中途半端に導入すると逆効果になるリスクがある
職務等級制度のデメリットは、「中途半端に導入すると逆効果になるリスクがある」ことです。
職務等級制度には、従来の年功序列制度とは真逆の成果主義的な性質があります。
年功序列制度は基本的に昇進するのみであるのに対し、職務等級制度では担当職務によっては降格となる場合もあります。
職務等級制度のメリットや目的を十分に周知しないまま職務等級制度を導入してしまうと、従業員が仕事への熱意を失ったり不満を抱いたりする可能性があります。
従業員のモチベーションの低下や離職を防ぐためにも、職務等級制度を導入する際は、事前に十分な説明を行い、従業員が制度を受け入れやすい体制づくりを行うことが重要です。
▼「成果主義」についてさらに詳しく
成果主義とは?メリットとデメリットや能力主義との違いをわかりやすく解説
▼「離職防止」についてさらに詳しく
離職防止に効果的な施策9つ!離職の原因とその影響も解説
役割等級制度
メリット
合理的な人事評価が可能になる
役割等級制度のメリットは、「合理的な人事評価が可能になる」ことです。
役割等級制度では、役割の難易度や達成度合いに応じて評価が行われるため、自社への貢献度や業績が直接的に評価に反映される、合理的な人事評価制度と言えます。
また、評価者の主観が入りにくい公正な評価を受けられることは、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上などにつながることが期待できます。
組織の改編や社会全体の環境変化への柔軟性が高い
役割等級制度のメリットは、「組織の改編や社会全体の環境変化への柔軟性が高い」ことです。
役割等級制度では、各等級の役割が大まかに決められているため、部署の異動や業務の変更が生じた場合でも、役割自体は変えずに維持することが可能です。
また役割を維持することができることは、配置転換に対する障壁が小さくなることにつながり、組織全体の改変時や社会全体の環境が大きく変わる際にも、影響を受けづらく、変化に柔軟な組織づくりにつながります。
従業員の主体性や自発性を伸ばすことができる
役割等級制度のメリットは、「従業員の主体性や自発性を伸ばすことができる」ことです。
役割等級制度は、従業員ひとりひとりに役割と責任を与えることで、各自が責任を持って働くことができる制度です。
勤続年数などではなく、自身の役割の達成度合いによって評価されることは、従業員が主体性を持って目標に向かうモチベーションにつながります。
また、役割が具体的に明示されると、今後自分に必要とされるスキルや経験を予測することができ、従業員が自主性や自発性を伸ばしやすくなります。
▼「主体性」についてさらに詳しく
主体性とは?意味と自主性との違いやある人とない人の特徴や高める方法を解説
デメリット
活用するための実績やノウハウが必要になる
役割等級制度のデメリットは、「活用するための実績やノウハウが必要になる」ことです。
役割等級制度は、制度の設計方法が難しく、他の等級制度と比べると導入企業が少ない傾向にあり、役割等級制度を自社の目的に合わせて運用する難易度は、非常に高いと言えます。
役割等級制度を活用するノウハウについては、自社で試行錯誤しながら蓄積していく必要があります。
▼「人事制度設計」についてさらに詳しく
人事制度設計のポイントとは?設計方法を3つの人事制度を交えて解説
人事制度の設計や見直しに
⇒「ゼロから作る人事制度設計マニュアル」資料ダウンロード
役割の変更が生じた場合の運用に負担がかかる
役割等級制度のデメリットは、「役割の変更が生じた場合の運用に負担がかかる」ことです。
役割等級制度の運用中に業務内容の変更や組織内の変更が生じた場合、役割の内容を見直す必要があります。
場合によっては、費用をかけてコンサルタントなど、外部の専門家の力を借りる必要があるなど、業務や組織自体の変更に伴って役割を定義し直す場合に、手間やコストが掛かってしまう場合があります。
▼「人事制度コンサルタント」
人事制度コンサルタントとは?評価制度設計を依頼するメリットと依頼の流れ
従業員に不公平感が生じやすい
役割等級制度のデメリットは、「従業員に不公平感が生じやすい」ことです。
役割等級制度では、担当する役割によっては等級が下がる場合があります。
役割という自身の能力とは別の要因によって等級が下がることに対して、従業員が不公平感を持つ場合があります。
役割等級制度を導入する際は、管理者層が従業員ひとりひとりと十分なコミュニケーションを取るなどして、従業員のモチベーションが低下することがないよう配慮することが重要です。
等級制度の作り方
等級制度を導入する際は、自社の方向性や事業方針に合うものを選択することが大切です。
等級制度を導入する場合、どのような流れで進めると良いのか、等級制度の作り方について5段階に分けて確認してみましょう。
等級制度の作り方
- 等級制度を導入する目的や方針を決定する
- 導入する等級制度の種類を決定する
- 等級の数を決定する
- 各等級の基準を決定する
- シミュレーションを行う
等級制度を導入する目的や方針を決定する
等級制度の作り方の1つ目は、「等級制度を導入する目的や方針を決定する」ことです。
導入目的や方針を考える際は、等級制度によって自社がどのようになっていきたいのか、将来のビジョンを描くことが大切です。
将来のビジョンを描いた後は、自社が現在抱えている課題を洗い出し、課題を解消するために何が必要かを分析すると良いでしょう。
▼「ビジョン」についてさらに詳しく
ビジョン
導入する等級制度の種類を決定する
等級制度の作り方の2つ目は、「導入する等級制度の種類を決定する」ことです。
導入目的や方針を策定した後は、採用する等級制度を決定します。
採用する等級制度は、経営方針や将来のビジョン、それぞれの制度のメリットやデメリットなどを検討し、総合的に選ぶことが大切です。
自社の目標を達成するためにも、長期的に無理なく取り入れられる等級制度を選択することが重要です。
等級の数を決定する
等級制度の作り方の3つ目は、「等級の数を決定する」ことです。
導入する等級制度が決まった後は、それぞれの等級の数を決めます。
あまりに等級の数が少ない場合、1つの等級の幅が広くなり過ぎてしまい、同じ等級の従業員の能力や自社への貢献度に大きな差が生じてしまいます。
反対に、等級の数が多すぎる場合、等級間の差が小さくなり過ぎてしまいます。
等級は、自社の企業規模や組織の性質を考慮して、適切な数を設定することが大切です。
各等級の基準を決定する
等級制度の作り方の4つ目は、「各等級の基準を決定する」ことです。
等級の数が決まったら、等級ごとの評価基準について決定します。
評価基準とは、各等級ごとに期待する役割や能力基準などを指します。
基準を決める際は、全職種共通とするか、職種別とするかを考える必要があります。
職種別の場合は、各職種に応じた具体的な基準を設定し、全職種共通の基準とする場合は、全ての職種に適用できるような基準を設定します。
シミュレーションを行う
等級制度の作り方の5つ目は、「シミュレーションを行う」ことです。
等級制度について全てを策定できたら、実際に制度を導入する前にシミュレーションをするようにしましょう。
シミュレーションは、作成した等級制度を実際の従業員に当てはめて行います。
シミュレーションを行うことによって、等級制度の評価基準や全体の仕組みに問題点や矛盾点がないかをチェックすることができます。
等級制度は自社の方針に合うものを選定することが重要
等級制度は、目指すべき業務レベルの基準を従業員に示し、組織開発を行ううえで大変重要な意味を持ちます。
いくつかの種類がある等級制度の中から、自社に合う等級制度を選ぶためには、各制度のメリットとデメリットを正確に理解することが大切です。
また、等級制度を導入する際は、導入目的を明確に定めたうえで、十分にシミュレーションを行いましょう。
等級制度を長期的に社内で活用するためには、事前に万全な準備をし、社内の体制を整えることが大切です。
そのために、スキルや評価などの従業員情報を一元管理し、可視化するなどし、適切な等級制度の運用を目指しましょう。
「HRBrain タレントマネジメント」は、等級制度を適切に運用するために必要な人材データの管理と可視化を、簡単かつシンプルに実現します。
さらに、従業員のスキルマップや、これまでの実務経験、育成履歴、異動経験、人事評価などの従業員データの管理と合わせて、OKRなどの目標管理、1on1やフィードバックなどの面談履歴などの一元管理も可能です。
HRBrain タレントマネジメントの特徴
検索性と実用性の高い「データベース構築」を実現
運用途中で項目の見直しが発生しても柔軟に対応できるので安心です。
柔軟な権限設定で最適な人材情報管理を
従業員、上司、管理者それぞれで項目単位の権限設定が可能なので、大切な情報を、最適な状態で管理できます。
人材データの見える化も柔軟で簡単に
データベースの自由度の高さや、データの見える化をより簡単に、ダッシュボードの作成も実務運用を想定しています。
▼「タレントマネジメントシステム」についてさらに詳しく
【完全版】タレントマネジメントとは?基本・実践、導入方法まで解説タレントマネジメントシステムの課題とは? 目的・導入の課題と成功事例まで
▼「タレントマネジメント」お役立ち資料まとめ
【人事担当者必見】タレントマネジメントに関するお役立ち資料まとめ